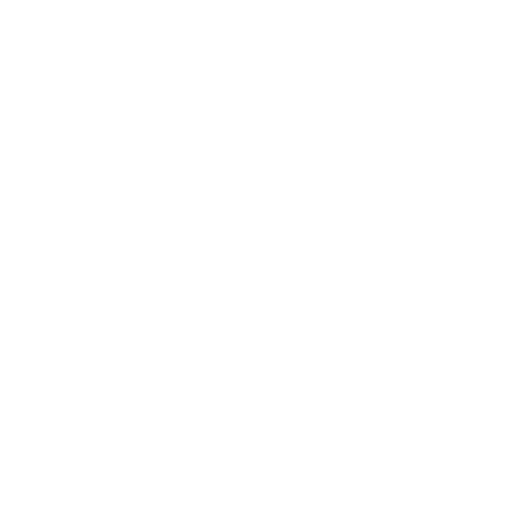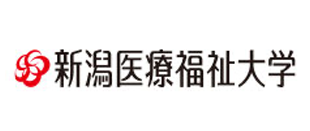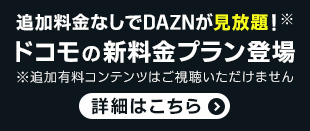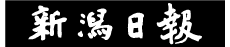【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第21回
2009/8/6
「これは学ぶべきだろう」
J1第19節、新潟×山形。
あ、痛たたた。開口一番、そんなコラムもどうかと思うが、あ、痛たたた。
「逃げつぶれ」だ。今シーズン、特にホームで繰り返されてきた「逃げつぶれ」を又、見てしまった。もったいないのぅ。勝負弱いのぅ。ってどこのおじいさんだ俺は。
経過。後半2分にマルシオのFKがオレンジ色のゴールネットを揺らす。前半、山形の守備ブロックに苦労していたから、願ってもない先制点だ。このままじっくり戦局を進めればいい。1対0のまま勝ち切るのもいいし、出てきたところをカウンターで仕留める2対0の完勝も素晴らしい。
嫌な感じはあった。それは「終盤に弱いジンクス」みたいなものでなく、あくまでサッカー的に説明できる話だ。劣勢のなか、山形が落ち着いていた。全然バタバタしたところがない。それどころか後半投入の赤星、財前が効いている。いつの間にか新潟の足が止まり、攻撃が単調になった。
後半43分だ。矢野貴章が中盤でボールを奪われ、チームは逆をとられる。奪ったのは山形・秋葉勝だ。この選手はずっとこれを狙っていた。すばやく左サイドの財前に通され、これを財前がベテランらしい心憎いセンタリング。新潟は戻りながらの守備で一歩追いつけない。長谷川が文句のないゴール。3人が3人共、見事な仕事をした。
トータルで見ると山形のゲームプランがうまくハマった試合ではなかったろうか。「辛抱して辛抱して、最後にひと勝負」だ。チームがそれを意思して、チューンナップされている。守備意識があって、運動量があって、終盤になるほど集中力が高まる。これは好チームだ。劣勢に立っても自分たちを信じている。
これは学ぶべきだろう。「J1の先輩」なんてふんぞり返っても仕方ない。只今の順位も関係ない。忘れてはいけない。新潟はチャレンジャーだ。一戦一戦学び、成長していくことが大事だ。何故、新潟は終盤に弱いのだろう。それは「何故、山形は終盤に強いのだろう」を考えることで見えてくる。
山形は「力道山のプロレス」だ。「辛抱して辛抱して、最後にひと勝負」は、サポーターも感情移入しやすい。選手もイメージを共有しやすい。物語が時間経過と共にタテに流れる。大量失点して、型崩れした場合は捨てるしかない。ハッキリしている。新潟も以前はこれだった。
今の新潟はいつが勝負どころになるかわからない。そういうスタイルなのだ。ポゼッションを握って、一から組み立てているわけじゃない。狩りとったときが勝負どころだ。物語は「起・承・転・結」とタテに流れない。基本は急展開だ。だから選手の判断が高度になる。又、わかり合ってる必要がある。
が、考え方は違っても学ぶべきところはある。新潟は終盤をハッキリさせた方がいい。例えばジャズのインプロヴィゼーションが最後、主題に戻って終わるようなイメージだ。ジャズではプレーヤーが終わり方だけ決めておく。
新潟が試合の最後に立ち戻るべき主題は「勝ち切ること」だ。そこへ向かってチームの総力を結集する必要がある。今シーズンは高い授業料をずいぶん払った。今節、又、山形が思い知らせてくれただろう。このゲームは87分勝っていても半分でしかない。終盤に全てがある。つまり、守り勝つのであっても「最後にひと勝負」に変わりはない。
附記1 しかし、引き分けなのに負けたような気分になり、しかも順位が上がるという不思議な第19節でした。もしかするとJ史上、「サポーターが最も悔しがった2位浮上」かも知れない。
2、「ビッグスワンに来て、不思議な感じがした。アルビのサポーターの拍手が嬉しかった」(山形・宮沢克行選手)
読者もむしゃくしゃしてると思うけれど、このコメントに胸を張って下さい。まぁ、かつてのアルビ戦士をホームへ迎える際、どうすべきかには色んな意見があるでしょう。「ブーイングで迎えるのが礼儀だ」みたいな考え方もわかる。だけど、宮沢選手を拍手で迎えたのは、イングランドでどうやってるのかは知らないけど、非常に「天地人ダービー」にふさわしかったと思います。兼続がゴール裏にいたら、やっぱりそうしたんじゃないでしょうか。
3、僕から見ると、それは(イングランドでどうやってるのかは知らないけど)、新潟の土地に根づいた思想っていうのかなぁ、新潟の強さです。兼続からずっと時間軸を流れているものです。NHKを見てると、兼続は「お人好しと笑われてもいい、人を大事にするのだ、愛なのだ」ばっかりやってるじゃないですか。僕はそれが新潟のストロングポイントだと思うなぁ。
4、だから、ファビーニョだって帰ってきたんだと思うなぁ。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
※アルビレックス新潟からのお知らせ
コラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。
更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!
J1第19節、新潟×山形。
あ、痛たたた。開口一番、そんなコラムもどうかと思うが、あ、痛たたた。
「逃げつぶれ」だ。今シーズン、特にホームで繰り返されてきた「逃げつぶれ」を又、見てしまった。もったいないのぅ。勝負弱いのぅ。ってどこのおじいさんだ俺は。
経過。後半2分にマルシオのFKがオレンジ色のゴールネットを揺らす。前半、山形の守備ブロックに苦労していたから、願ってもない先制点だ。このままじっくり戦局を進めればいい。1対0のまま勝ち切るのもいいし、出てきたところをカウンターで仕留める2対0の完勝も素晴らしい。
嫌な感じはあった。それは「終盤に弱いジンクス」みたいなものでなく、あくまでサッカー的に説明できる話だ。劣勢のなか、山形が落ち着いていた。全然バタバタしたところがない。それどころか後半投入の赤星、財前が効いている。いつの間にか新潟の足が止まり、攻撃が単調になった。
後半43分だ。矢野貴章が中盤でボールを奪われ、チームは逆をとられる。奪ったのは山形・秋葉勝だ。この選手はずっとこれを狙っていた。すばやく左サイドの財前に通され、これを財前がベテランらしい心憎いセンタリング。新潟は戻りながらの守備で一歩追いつけない。長谷川が文句のないゴール。3人が3人共、見事な仕事をした。
トータルで見ると山形のゲームプランがうまくハマった試合ではなかったろうか。「辛抱して辛抱して、最後にひと勝負」だ。チームがそれを意思して、チューンナップされている。守備意識があって、運動量があって、終盤になるほど集中力が高まる。これは好チームだ。劣勢に立っても自分たちを信じている。
これは学ぶべきだろう。「J1の先輩」なんてふんぞり返っても仕方ない。只今の順位も関係ない。忘れてはいけない。新潟はチャレンジャーだ。一戦一戦学び、成長していくことが大事だ。何故、新潟は終盤に弱いのだろう。それは「何故、山形は終盤に強いのだろう」を考えることで見えてくる。
山形は「力道山のプロレス」だ。「辛抱して辛抱して、最後にひと勝負」は、サポーターも感情移入しやすい。選手もイメージを共有しやすい。物語が時間経過と共にタテに流れる。大量失点して、型崩れした場合は捨てるしかない。ハッキリしている。新潟も以前はこれだった。
今の新潟はいつが勝負どころになるかわからない。そういうスタイルなのだ。ポゼッションを握って、一から組み立てているわけじゃない。狩りとったときが勝負どころだ。物語は「起・承・転・結」とタテに流れない。基本は急展開だ。だから選手の判断が高度になる。又、わかり合ってる必要がある。
が、考え方は違っても学ぶべきところはある。新潟は終盤をハッキリさせた方がいい。例えばジャズのインプロヴィゼーションが最後、主題に戻って終わるようなイメージだ。ジャズではプレーヤーが終わり方だけ決めておく。
新潟が試合の最後に立ち戻るべき主題は「勝ち切ること」だ。そこへ向かってチームの総力を結集する必要がある。今シーズンは高い授業料をずいぶん払った。今節、又、山形が思い知らせてくれただろう。このゲームは87分勝っていても半分でしかない。終盤に全てがある。つまり、守り勝つのであっても「最後にひと勝負」に変わりはない。
附記1 しかし、引き分けなのに負けたような気分になり、しかも順位が上がるという不思議な第19節でした。もしかするとJ史上、「サポーターが最も悔しがった2位浮上」かも知れない。
2、「ビッグスワンに来て、不思議な感じがした。アルビのサポーターの拍手が嬉しかった」(山形・宮沢克行選手)
読者もむしゃくしゃしてると思うけれど、このコメントに胸を張って下さい。まぁ、かつてのアルビ戦士をホームへ迎える際、どうすべきかには色んな意見があるでしょう。「ブーイングで迎えるのが礼儀だ」みたいな考え方もわかる。だけど、宮沢選手を拍手で迎えたのは、イングランドでどうやってるのかは知らないけど、非常に「天地人ダービー」にふさわしかったと思います。兼続がゴール裏にいたら、やっぱりそうしたんじゃないでしょうか。
3、僕から見ると、それは(イングランドでどうやってるのかは知らないけど)、新潟の土地に根づいた思想っていうのかなぁ、新潟の強さです。兼続からずっと時間軸を流れているものです。NHKを見てると、兼続は「お人好しと笑われてもいい、人を大事にするのだ、愛なのだ」ばっかりやってるじゃないですか。僕はそれが新潟のストロングポイントだと思うなぁ。
4、だから、ファビーニョだって帰ってきたんだと思うなぁ。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
※アルビレックス新潟からのお知らせ
コラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。
更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!