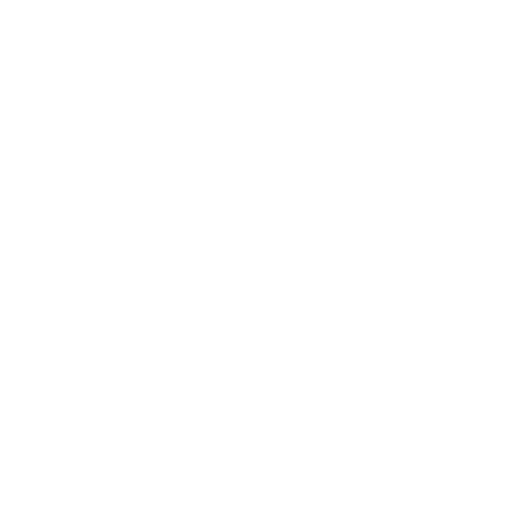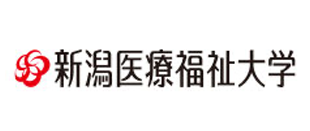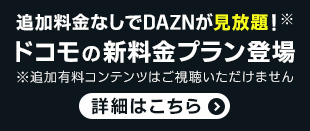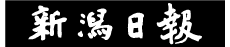【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第23回
2009/8/20
「イッツ・ニュー」
開幕以来、これが実に毎週「新潟」という文字を書いている。初めての経験だ。僕は生まれてから秋田県民、群馬県民、北海道民、和歌山県民、福岡県民、神奈川県民、東京都民と様々なケンミン的なものになったが、例えば毎週「神奈川」という文字を書いたことがあるかと言えば、ない。たぶん新潟県民の大半の皆さんも毎週は「新潟」と書いてないでしょう。
で、発見したのだが、「新潟」は「新」「潟」なのだ。
イッツ・ニュー。
新しいことを天下に示している。
「新潟」という以上、どこかに対応する「古潟」と呼ぶべきものがあって然るべきと思うが、それはどこなんでしょう。折から選挙で「新党」が旗挙げしたりしているが、「新党」を考えてみると「古党」は概念の上にしか存在しない。あんまり「我々、古党のマニュフェストは…」という演説も聞かないでしょう。こういうのは「新しい方から見たときに古い」というニュアンスであって、既成政党の側は「自分らはフツーだ」と考えるだろう。
となると、どこなんだろうなぁ、当の本人は自覚していない「古潟県」というのは。自分らはフツーだ、と思って暮らしてるんだと思うんですよ。
「新」という言葉には、もうそれだけでバリューというのか勢いというのか、魅力がありますね。
「新曲」「新人」「新発売」「新製品」。
「新米」「新そば」「新記録」。
本体部分は「曲」であったり「人」であったり「そば」であったりするんだけど、「新」が上につくと輝いて見える。ワクワクする。楽しみになる。意味を持った漢字ではあるけれど、用いられ方は「!」とか「☆」みたいに本体部分の「曲」や「人」や「そば」にスポットライトを当て、輝かせる効果とも思える。
というのは、以前「新幹線」というものについて考えたんですよ。あれは本当に新しいのか。御存知の通り、東海道新幹線の開業は昭和39年、東京オリンピックに合わせてです。45年前ですよ。45年たってるものを「新」と言い張るのは無理があるでしょう。「リリースされて45年の新曲」「入社45年の新人」とはいくら何でも言わない。っていうか「入社45年の新人」は大卒で入ってたら66歳で、もう定年退職してます。
気持ちの問題なんだなぁ。意味を離れて、バリュー感を強調する為に「新」「幹線」は使われている。だから、新しいかどうかが問題じゃなくて、「スゴ幹線」とか「メッチャ幹線」と言ってる状態です。
で、「新潟」ですけど、越後府を新潟府に改称して、「新」を打ち出した最初が明治元年ですよ。「新幹線」の比じゃない。「新」としてはとてつもなく年季が入ってます。えーと、141年か。これはインパクトあります。141年ずっと新しい。
僕はこれは意欲じゃないかと思います。手元に平成18年版の「新潟県民手帳」がありますが、その6ページ、「新潟県民歌」に横溢するのはそういうものです。
やるぞー。
やる気満々という気概。
それがある限り、いつだって新しいということじゃないですか。
「新潟県民歌」作詩・高下玉衛
一、世紀明けゆく西北の
山河新たに旭は映えて
県民二百五十万
希望に燃えてこぞり起つ
ここぞ民主の新潟県
二、五穀の宝庫土壌肥えて
尽きぬ越後の野の幸に
文化産業絢爛と
花咲き薫るこの繁華
興せ自由の新潟県
三、日本海の若潮に
弥彦妙高佐渡晴れて
世界をむすぶ観光の
絵巻彩なすわが郷土
拓け詩の国新潟県
四、越佐の天地玲瓏と
今ぞ平和の鐘は鳴る
ああ新しき憲法の
聖き理想を炬と翳し
築け栄ある新潟県
附記1、「新潟県民手帳」は、その前年の暮れ、反町康治監督の取材をした帰り、紀伊國屋書店で購入したものです。そのときの取材は「カーテンコール」という文章になった。
2、で、手帳は一年間、愛用した。
3、JOMOカップはジウトン頑張ってましたね。あの若さで本当に得難い経験をしたと思います。母国の名監督、オリヴェイラさんに認められての選出&フル出場は相当嬉しいと思いますよ。
4、本稿執筆現在、地震で東名道の路肩が崩落して、えらいことになってます。復旧工事の人はお盆返上ですね。次節・清水戦にクルマで行かれる方は時間の余裕を見たほうがよさそうです。ただでさえ、ETC割引で渋滞の予測が立たないと言われてたわけですから。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
※アルビレックス新潟からのお知らせ
コラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。
更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!
開幕以来、これが実に毎週「新潟」という文字を書いている。初めての経験だ。僕は生まれてから秋田県民、群馬県民、北海道民、和歌山県民、福岡県民、神奈川県民、東京都民と様々なケンミン的なものになったが、例えば毎週「神奈川」という文字を書いたことがあるかと言えば、ない。たぶん新潟県民の大半の皆さんも毎週は「新潟」と書いてないでしょう。
で、発見したのだが、「新潟」は「新」「潟」なのだ。
イッツ・ニュー。
新しいことを天下に示している。
「新潟」という以上、どこかに対応する「古潟」と呼ぶべきものがあって然るべきと思うが、それはどこなんでしょう。折から選挙で「新党」が旗挙げしたりしているが、「新党」を考えてみると「古党」は概念の上にしか存在しない。あんまり「我々、古党のマニュフェストは…」という演説も聞かないでしょう。こういうのは「新しい方から見たときに古い」というニュアンスであって、既成政党の側は「自分らはフツーだ」と考えるだろう。
となると、どこなんだろうなぁ、当の本人は自覚していない「古潟県」というのは。自分らはフツーだ、と思って暮らしてるんだと思うんですよ。
「新」という言葉には、もうそれだけでバリューというのか勢いというのか、魅力がありますね。
「新曲」「新人」「新発売」「新製品」。
「新米」「新そば」「新記録」。
本体部分は「曲」であったり「人」であったり「そば」であったりするんだけど、「新」が上につくと輝いて見える。ワクワクする。楽しみになる。意味を持った漢字ではあるけれど、用いられ方は「!」とか「☆」みたいに本体部分の「曲」や「人」や「そば」にスポットライトを当て、輝かせる効果とも思える。
というのは、以前「新幹線」というものについて考えたんですよ。あれは本当に新しいのか。御存知の通り、東海道新幹線の開業は昭和39年、東京オリンピックに合わせてです。45年前ですよ。45年たってるものを「新」と言い張るのは無理があるでしょう。「リリースされて45年の新曲」「入社45年の新人」とはいくら何でも言わない。っていうか「入社45年の新人」は大卒で入ってたら66歳で、もう定年退職してます。
気持ちの問題なんだなぁ。意味を離れて、バリュー感を強調する為に「新」「幹線」は使われている。だから、新しいかどうかが問題じゃなくて、「スゴ幹線」とか「メッチャ幹線」と言ってる状態です。
で、「新潟」ですけど、越後府を新潟府に改称して、「新」を打ち出した最初が明治元年ですよ。「新幹線」の比じゃない。「新」としてはとてつもなく年季が入ってます。えーと、141年か。これはインパクトあります。141年ずっと新しい。
僕はこれは意欲じゃないかと思います。手元に平成18年版の「新潟県民手帳」がありますが、その6ページ、「新潟県民歌」に横溢するのはそういうものです。
やるぞー。
やる気満々という気概。
それがある限り、いつだって新しいということじゃないですか。
「新潟県民歌」作詩・高下玉衛
一、世紀明けゆく西北の
山河新たに旭は映えて
県民二百五十万
希望に燃えてこぞり起つ
ここぞ民主の新潟県
二、五穀の宝庫土壌肥えて
尽きぬ越後の野の幸に
文化産業絢爛と
花咲き薫るこの繁華
興せ自由の新潟県
三、日本海の若潮に
弥彦妙高佐渡晴れて
世界をむすぶ観光の
絵巻彩なすわが郷土
拓け詩の国新潟県
四、越佐の天地玲瓏と
今ぞ平和の鐘は鳴る
ああ新しき憲法の
聖き理想を炬と翳し
築け栄ある新潟県
附記1、「新潟県民手帳」は、その前年の暮れ、反町康治監督の取材をした帰り、紀伊國屋書店で購入したものです。そのときの取材は「カーテンコール」という文章になった。
2、で、手帳は一年間、愛用した。
3、JOMOカップはジウトン頑張ってましたね。あの若さで本当に得難い経験をしたと思います。母国の名監督、オリヴェイラさんに認められての選出&フル出場は相当嬉しいと思いますよ。
4、本稿執筆現在、地震で東名道の路肩が崩落して、えらいことになってます。復旧工事の人はお盆返上ですね。次節・清水戦にクルマで行かれる方は時間の余裕を見たほうがよさそうです。ただでさえ、ETC割引で渋滞の予測が立たないと言われてたわけですから。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
※アルビレックス新潟からのお知らせ
コラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。
更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!