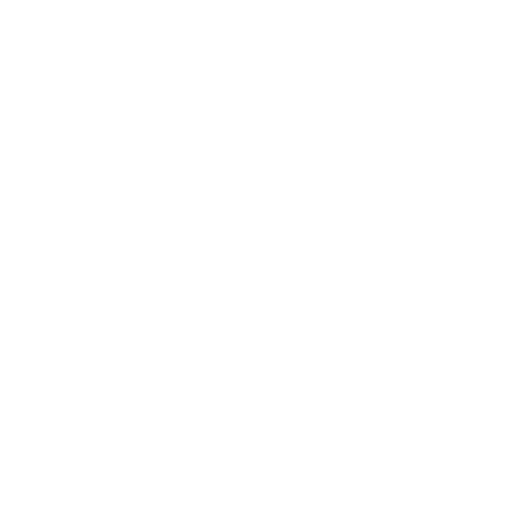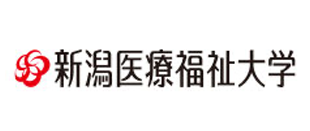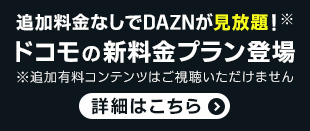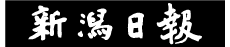【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第27回
2009/9/16
「オレンジに反応する」
日本代表のオランダ戦を御覧になって、オレンジ色に染まったアルケ・スタディオン(エンスヘーデ)の光景に反応した読者は多いんじゃないでしょうか。御存知の通り、オランダのナショナルカラーはオレンジです。サッカーの代表ユニホームもオレンジだし、冬季五輪のときは長身のスケート選手がオレンジの「もじもじくん」になる。これは王室オラニエ家(「オラニエ」はオランダ語でオレンジの意)に由来するそうです。女王誕生日等、王室行事の日は国じゅうがオレンジ色を着た人であふれ返る。
つまり、国民ひとり当たりの「オレンジの服持ってる率」ということで言うと、たぶんオランダがダントツで世界一です。オレンジのTシャツ、ジーンズ、スカート、セーターやアウターの類、帽子やアフロ・カツラ、何でも売っている。新潟サポも気がつくとオレンジのアイテムが増えてってると思うけど、向こうは国民的にやっている。だから、オレンジの仮装アイテムをKLMオランダ航空に乗って買いだしに行く手はありますね。ただサイズが難しい。オランダ人って本当に背が高いんですよ。僕は初めて行ったとき、アムステルダムの空港で、小の便器がものすごく高い位置なんで仰天した。僕は170センチあるから日本人としては標準だと思うけど、冗談抜きでつま先立ちで用を足しました。
代表戦は代表戦で課題の見えた試合でした。本稿はそれを考える主旨ではないけれど、「失点後の落ちつき」とか「ペース配分」とか、もちろん「決定力」とか、代表にかぎらず日本サッカー共通の課題でもあるようなものがはっきり見えた。
読者はたぶん矢野貴章選手のメンバー落ちでテンション低かったと思うんですけど、代表を見ていて、もしかしたら新潟の試合を連想したんじゃないですか。代表はやっぱり代表です。新潟が苦手なものは代表も苦手にしている。
ただ今週のテーマはあくまで「オレンジに反応する」です。オランダ代表のユニホームを見て、あぁ、白パンに青みがかったグレーのソックスって組み合わせもいいなぁ、と思う目線を大事にしたい。
一冊、オレンジ本を紹介しましょう。
その名も『オレンジの呪縛―オランダ代表はなぜ勝てないか?』(デイヴィッド・ウイナー著、講談社)。これは面白い本ですよ。著者のデイヴィッド・ウイナーは名前でわかる通り、非オランダ人(イギリス人)です。ただ10代で「トータルフットボール」の洗礼を浴び、オランダに魅せられ、ついにはアムステルダムへ住みついてしまった。本を開いていきなり笑うのは「トータルフットボールの精神に敬意を表して」章の番号がバラバラに始まるんですね。まず5章が来て、次が7章、9章、14章、10章、1章と続く。
副題の「オランダ代表はなぜ勝てないか?」には説明が必要ですね。先週の親善試合は3対0で勝ってるし。まぁ、アレです、オランダ代表は歴代、不思議なチームなんですよ。名勝負を演じることが多い。革新的なシステムを発明する。タレントの宝庫である。理詰めの美しいサッカーをする。けれど、勝負弱い。ホントにドイツの勝負強さと対照的です。
そういえばオランダはアヤックス・スタイル、「4-3-3」の本場でもあります。終章「レクイエム」には「『4-3-3』をめぐる神学論争」という項があって、これがなかなか興味深い。
「4-4-2は、平凡な選手にとってはすぐれたシステムだろう。ゴール前に多くの選手を配置して相手の突破を防ぎ、中盤には身体能力を生かしたプレーが得意な選手を起用し、前線にはゴール前だけで仕事をするストライカーを置く。PSVがそのいい例だ。たしかに成功は収めるかもしれないが、魅力的なプレーをしたチームとして記憶されることはまずないだろう。
4-4-2と4-3-3の決定的な違いは、守備、中盤、前線の三つのラインで多様なプレーができるかどうかにある。4-4-2では当然ながら、4人のDF、4人のMF、2人のFWとラインは硬直的になるが、4-3-3では、正しい指導を行うことで、ラインの数を増やすことが可能になるのだ。センターバックが少し前に上がることで、残った3人のディフェンスラインと中盤の間に新たなラインができるし、ウインガーが前に出れば、また別のラインを生み出すことになる」(同書より、ヨハン・クライフ)
いや、それを否定するフォッペ・デ・ハーンの意見も傾聴に価します。オレンジと「4-3-3」を考える上でも(そして、もちろん異国のフットボール・カルチャーに触れる意味でも)、是非、手にとっていただきたい一冊です。
附記1、次節・千葉戦、第三舞台の大高洋夫さんと御一緒することになりました。知らなかったけど、大高さんは新潟日報で月イチのコラム書いてるんですね。
2、大高さんと知り合うきっかけになったのは、昔、フジ深夜でやってた『たほいや』です。懐かしいなぁ。それ以来、ウマが合ってずっとつきあいが続いている。
3、代表戦、試合自体はガーナ戦の方が面白かったですね。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
※アルビレックス新潟からのお知らせ
コラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。
更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!
日本代表のオランダ戦を御覧になって、オレンジ色に染まったアルケ・スタディオン(エンスヘーデ)の光景に反応した読者は多いんじゃないでしょうか。御存知の通り、オランダのナショナルカラーはオレンジです。サッカーの代表ユニホームもオレンジだし、冬季五輪のときは長身のスケート選手がオレンジの「もじもじくん」になる。これは王室オラニエ家(「オラニエ」はオランダ語でオレンジの意)に由来するそうです。女王誕生日等、王室行事の日は国じゅうがオレンジ色を着た人であふれ返る。
つまり、国民ひとり当たりの「オレンジの服持ってる率」ということで言うと、たぶんオランダがダントツで世界一です。オレンジのTシャツ、ジーンズ、スカート、セーターやアウターの類、帽子やアフロ・カツラ、何でも売っている。新潟サポも気がつくとオレンジのアイテムが増えてってると思うけど、向こうは国民的にやっている。だから、オレンジの仮装アイテムをKLMオランダ航空に乗って買いだしに行く手はありますね。ただサイズが難しい。オランダ人って本当に背が高いんですよ。僕は初めて行ったとき、アムステルダムの空港で、小の便器がものすごく高い位置なんで仰天した。僕は170センチあるから日本人としては標準だと思うけど、冗談抜きでつま先立ちで用を足しました。
代表戦は代表戦で課題の見えた試合でした。本稿はそれを考える主旨ではないけれど、「失点後の落ちつき」とか「ペース配分」とか、もちろん「決定力」とか、代表にかぎらず日本サッカー共通の課題でもあるようなものがはっきり見えた。
読者はたぶん矢野貴章選手のメンバー落ちでテンション低かったと思うんですけど、代表を見ていて、もしかしたら新潟の試合を連想したんじゃないですか。代表はやっぱり代表です。新潟が苦手なものは代表も苦手にしている。
ただ今週のテーマはあくまで「オレンジに反応する」です。オランダ代表のユニホームを見て、あぁ、白パンに青みがかったグレーのソックスって組み合わせもいいなぁ、と思う目線を大事にしたい。
一冊、オレンジ本を紹介しましょう。
その名も『オレンジの呪縛―オランダ代表はなぜ勝てないか?』(デイヴィッド・ウイナー著、講談社)。これは面白い本ですよ。著者のデイヴィッド・ウイナーは名前でわかる通り、非オランダ人(イギリス人)です。ただ10代で「トータルフットボール」の洗礼を浴び、オランダに魅せられ、ついにはアムステルダムへ住みついてしまった。本を開いていきなり笑うのは「トータルフットボールの精神に敬意を表して」章の番号がバラバラに始まるんですね。まず5章が来て、次が7章、9章、14章、10章、1章と続く。
副題の「オランダ代表はなぜ勝てないか?」には説明が必要ですね。先週の親善試合は3対0で勝ってるし。まぁ、アレです、オランダ代表は歴代、不思議なチームなんですよ。名勝負を演じることが多い。革新的なシステムを発明する。タレントの宝庫である。理詰めの美しいサッカーをする。けれど、勝負弱い。ホントにドイツの勝負強さと対照的です。
そういえばオランダはアヤックス・スタイル、「4-3-3」の本場でもあります。終章「レクイエム」には「『4-3-3』をめぐる神学論争」という項があって、これがなかなか興味深い。
「4-4-2は、平凡な選手にとってはすぐれたシステムだろう。ゴール前に多くの選手を配置して相手の突破を防ぎ、中盤には身体能力を生かしたプレーが得意な選手を起用し、前線にはゴール前だけで仕事をするストライカーを置く。PSVがそのいい例だ。たしかに成功は収めるかもしれないが、魅力的なプレーをしたチームとして記憶されることはまずないだろう。
4-4-2と4-3-3の決定的な違いは、守備、中盤、前線の三つのラインで多様なプレーができるかどうかにある。4-4-2では当然ながら、4人のDF、4人のMF、2人のFWとラインは硬直的になるが、4-3-3では、正しい指導を行うことで、ラインの数を増やすことが可能になるのだ。センターバックが少し前に上がることで、残った3人のディフェンスラインと中盤の間に新たなラインができるし、ウインガーが前に出れば、また別のラインを生み出すことになる」(同書より、ヨハン・クライフ)
いや、それを否定するフォッペ・デ・ハーンの意見も傾聴に価します。オレンジと「4-3-3」を考える上でも(そして、もちろん異国のフットボール・カルチャーに触れる意味でも)、是非、手にとっていただきたい一冊です。
附記1、次節・千葉戦、第三舞台の大高洋夫さんと御一緒することになりました。知らなかったけど、大高さんは新潟日報で月イチのコラム書いてるんですね。
2、大高さんと知り合うきっかけになったのは、昔、フジ深夜でやってた『たほいや』です。懐かしいなぁ。それ以来、ウマが合ってずっとつきあいが続いている。
3、代表戦、試合自体はガーナ戦の方が面白かったですね。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
※アルビレックス新潟からのお知らせ
コラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。
更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!