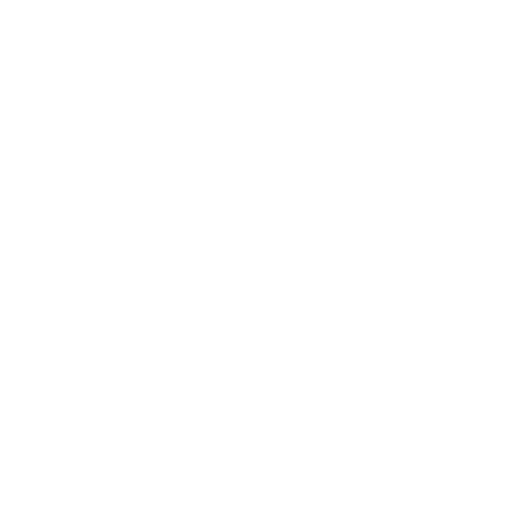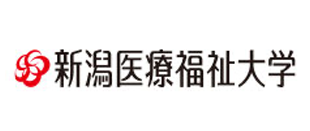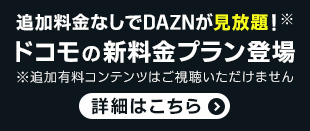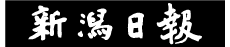【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第95回(前編)
2011/6/16
「拠って来たるところ」
ナビスコがお休みだったので、今週は本の話。
去年、高円寺のブックイベントで『「裏日本」はいかにつくられたか』(阿部恒久・著、日本経済新聞社)という本を発見、オフ期間に熟読したのだった。著者の阿部さんは1948年新潟市生まれ、共立女子大教授(日本近代史)とクレジットされている。問題意識のコアの部分に「新潟人のアイデンティティ」があることは間違いないと思う。
読者のうち、若い方はもしかすると「表日本」「裏日本」という言葉自体になじみが少ないかもしれない。かつては教科書に記載されていたが、現在は差別語ということになってメディア上でも扱われない言葉だ。言葉はそうだが、概念はどうかというと存外根強く残っているかもしれない。どうだろう、太平洋側は明るくメジャーで、日本海側は暗くもの悲しいといった語られ方をすることがないか。著者の阿部さんはその拠って来たるところを明らかにする。それは豪雪地帯みたいな自然条件のせいではない。
江戸時代、例えば北前船の航路を考えても日本海側に「裏」といったイメージはなかった。むしろ物流の大動脈だ。太平洋側の航路がマイナー(非主流)で、小規模な漁村が点在していたのに比べ、日本海側には物流拠点として栄えた土地が多かった。それが近代になって急速に「裏日本」化していくにあたっては国策が関与している。読者はここ数年、大河ドラマの後、暮れにNHKが放送する『坂の上の雲』を御覧になってるかもしれない。明治の日本は貧乏だった。貧乏だったが近代化する必要があった。
で、どうしたかというと国策で近代化資本を集中投下する。近代化資本というとわかりにくいが、要するに税金だ。貧しい農業国の税金をかき集めて、高等教育機関を作る。工場を作る。鉄道、道路、港湾整備等のインフラを作る。どこに? 太平洋側に。例えば新潟県(当初は越後府、のち新潟県、柏崎県等)は人口も多く、当時最大の産業が農業であった以上、税金も多く払っていたのだが、完全にワリを食った。
そりゃ「遅れた地域」が形成されるわけである。産業育成も高等教育も格差がつくられる。叉、当時の大地主層が子弟を東京へ遊学させ、県下の教育発展に消極的であったのも一因となった。人口流出は松方デフレに始まり、日清戦争後には顕著となる。「裏日本」化が形成され、固定されていく。歴史にイフが許されるなら、例えば明治期、帝国大学や国策企業が設立された新潟を想像してみよう。もしかすると関東サポは地元を出なかったかもしれない。アルビレックス新潟は「自動車会社がバックの金満クラブ」であったかもしれない。
ところが新潟は放っておかれる。悲願の高等教育機関が設置されたのは、明治43年、官立新潟医学専門学校だった。叉、国家機関の設置という意味では日露戦争後、上越・高田町に帝国陸軍第13師団が設置されたことも見逃せない。これは日露戦争中に誘致運動が巻き起こった。今の上越市、高田は近代に入り、軍都として名をなすことになる。
ひとつ惜しかったなぁと思うのは、明治21年、設立された「日本石油会社」だ。これは新潟県下における「最初の資本主義企業」だった。官費に頼らず、純然と大地主らの出資で発起される。のちに頑迷な保守性にとらわれる大地主層も明治初期はやる気まんまんだった。これがサウジアラビアくらい石油が出ててごらんなさい。いまごろアルビ・田村社長は何かこう頭巾みたいな、アラブの、「ヤシュマーグ」っていうらしいですが、あぁいうのかぶって「うーん、今年はベッカム獲っちゃう?」とか言ってかねない。他クラブからは「新潟のオイルマネーに気をつけろ」とか言われていかねない。
その「日本石油会社」は明治後期の「新潟鐵工所」設立につながっていき、色々あって、第二次大戦中、うちの父の学徒動員先にもなる(終戦まで東京・鎌田の同工場でポンポン船の焼玉エンジン作ってた)わけだ。これが戦後、解体されずに健在なら、アルビレックス新潟のユニホームスポンサーになってた気がする。「新潟鐵工所」という名の大企業にイメージがわかない読者は「日立製作所」を思い浮かべてほしい。今、そんな印象を持つ人はいないが、「HITACHI」は充分、茨城県の町工場みたいなネーミングじゃないか。
戦後に入っても「表日本」「裏日本」の構造は維持される。高度成長が始まって首都圏及び「表日本」工業都市への人口集中が加速する。集団就職がその象徴だ。東北も含めた「裏」側は、「表」への労働力供給源に固定される。僕は「田中角栄」という存在はこの文脈のなかで見るべきだと思う。「コンピューターつきブルドーザー」とか「金権体質の土建屋政治家」とか、とかく馬力を強調された彼の初期衝動は何だったかというと「遅れた地域」の情念であったろう。
−後編に続く−
ナビスコがお休みだったので、今週は本の話。
去年、高円寺のブックイベントで『「裏日本」はいかにつくられたか』(阿部恒久・著、日本経済新聞社)という本を発見、オフ期間に熟読したのだった。著者の阿部さんは1948年新潟市生まれ、共立女子大教授(日本近代史)とクレジットされている。問題意識のコアの部分に「新潟人のアイデンティティ」があることは間違いないと思う。
読者のうち、若い方はもしかすると「表日本」「裏日本」という言葉自体になじみが少ないかもしれない。かつては教科書に記載されていたが、現在は差別語ということになってメディア上でも扱われない言葉だ。言葉はそうだが、概念はどうかというと存外根強く残っているかもしれない。どうだろう、太平洋側は明るくメジャーで、日本海側は暗くもの悲しいといった語られ方をすることがないか。著者の阿部さんはその拠って来たるところを明らかにする。それは豪雪地帯みたいな自然条件のせいではない。
江戸時代、例えば北前船の航路を考えても日本海側に「裏」といったイメージはなかった。むしろ物流の大動脈だ。太平洋側の航路がマイナー(非主流)で、小規模な漁村が点在していたのに比べ、日本海側には物流拠点として栄えた土地が多かった。それが近代になって急速に「裏日本」化していくにあたっては国策が関与している。読者はここ数年、大河ドラマの後、暮れにNHKが放送する『坂の上の雲』を御覧になってるかもしれない。明治の日本は貧乏だった。貧乏だったが近代化する必要があった。
で、どうしたかというと国策で近代化資本を集中投下する。近代化資本というとわかりにくいが、要するに税金だ。貧しい農業国の税金をかき集めて、高等教育機関を作る。工場を作る。鉄道、道路、港湾整備等のインフラを作る。どこに? 太平洋側に。例えば新潟県(当初は越後府、のち新潟県、柏崎県等)は人口も多く、当時最大の産業が農業であった以上、税金も多く払っていたのだが、完全にワリを食った。
そりゃ「遅れた地域」が形成されるわけである。産業育成も高等教育も格差がつくられる。叉、当時の大地主層が子弟を東京へ遊学させ、県下の教育発展に消極的であったのも一因となった。人口流出は松方デフレに始まり、日清戦争後には顕著となる。「裏日本」化が形成され、固定されていく。歴史にイフが許されるなら、例えば明治期、帝国大学や国策企業が設立された新潟を想像してみよう。もしかすると関東サポは地元を出なかったかもしれない。アルビレックス新潟は「自動車会社がバックの金満クラブ」であったかもしれない。
ところが新潟は放っておかれる。悲願の高等教育機関が設置されたのは、明治43年、官立新潟医学専門学校だった。叉、国家機関の設置という意味では日露戦争後、上越・高田町に帝国陸軍第13師団が設置されたことも見逃せない。これは日露戦争中に誘致運動が巻き起こった。今の上越市、高田は近代に入り、軍都として名をなすことになる。
ひとつ惜しかったなぁと思うのは、明治21年、設立された「日本石油会社」だ。これは新潟県下における「最初の資本主義企業」だった。官費に頼らず、純然と大地主らの出資で発起される。のちに頑迷な保守性にとらわれる大地主層も明治初期はやる気まんまんだった。これがサウジアラビアくらい石油が出ててごらんなさい。いまごろアルビ・田村社長は何かこう頭巾みたいな、アラブの、「ヤシュマーグ」っていうらしいですが、あぁいうのかぶって「うーん、今年はベッカム獲っちゃう?」とか言ってかねない。他クラブからは「新潟のオイルマネーに気をつけろ」とか言われていかねない。
その「日本石油会社」は明治後期の「新潟鐵工所」設立につながっていき、色々あって、第二次大戦中、うちの父の学徒動員先にもなる(終戦まで東京・鎌田の同工場でポンポン船の焼玉エンジン作ってた)わけだ。これが戦後、解体されずに健在なら、アルビレックス新潟のユニホームスポンサーになってた気がする。「新潟鐵工所」という名の大企業にイメージがわかない読者は「日立製作所」を思い浮かべてほしい。今、そんな印象を持つ人はいないが、「HITACHI」は充分、茨城県の町工場みたいなネーミングじゃないか。
戦後に入っても「表日本」「裏日本」の構造は維持される。高度成長が始まって首都圏及び「表日本」工業都市への人口集中が加速する。集団就職がその象徴だ。東北も含めた「裏」側は、「表」への労働力供給源に固定される。僕は「田中角栄」という存在はこの文脈のなかで見るべきだと思う。「コンピューターつきブルドーザー」とか「金権体質の土建屋政治家」とか、とかく馬力を強調された彼の初期衝動は何だったかというと「遅れた地域」の情念であったろう。
−後編に続く−