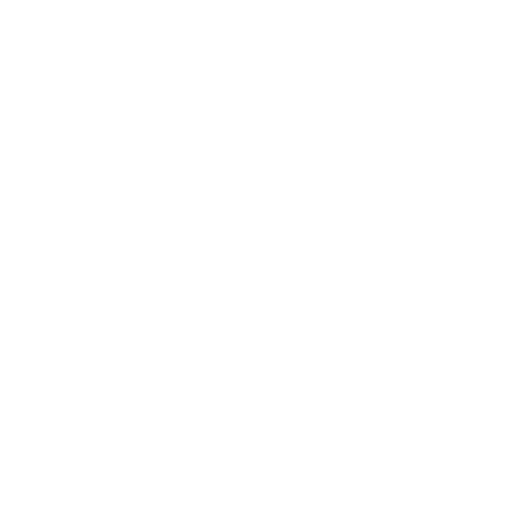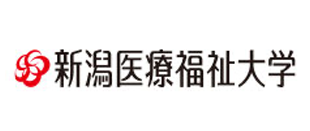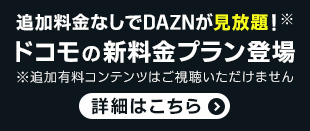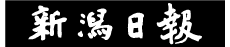【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第116回(後編)
2011/11/10
が、その輝かしい育成の歴史の一方で「異端」の指導方針には批判も多かった。ガンバ大阪の育成組織を日本有数のものにした上野山信行氏(現・Jリーグ技術委員長)は本書のなかでヴェルディ育成の影響をこう語る。
「参考にしたのはピッチのなか全部です。育成年代の大会をみるたびに、技術、戦術、サッカーの中身をつぶさに研究した。盗めるものは盗めと。一方、ピッチ外は見習わなかった。中学生の選手がつばを吐く。審判に文句を言う。これではあかん。社会に出ていく子を育てているのにきちんと指導できていない。ヴェルディはここで止まるなと思った。確かに巧い。でもそこに慢心している。反省がない。謙虚さがない」(第4章「凋落 −Jリーグ以降の忘れもの−」より)
読者のうちアルビレックス新潟がJ1に昇格した後、サッカーに関心を持った世代や層も多いだろうと想像している。たぶん東京ヴェルディというクラブにそれほど強烈な印象を抱いてない筈だ。僕の目にもその時期、ヴェルデイは独善的に、Jの潮流から浮き上がって見えた。そして迷走を繰り返して経営危機まで行ってしまった。
だけど、リスペクトを失ってはならないと思う。そこにあるのはクラブチームの開拓者の栄光と挫折だ。先人の切り拓いた道を後続はたどる。海江田さんはこの本を「ランド」の芝生が匂いたつような作りにした。育成指導者の熱をそのまま伝えようとした。まぁ、全体像は本書を手にとってもらうとして、ひとつ、おお、最高だなぁと思うくだりを引用しよう。冨樫剛一氏(現・東京ヴェルディコーチ)がジュニアユースの指導をしたときだ。対人練習ばかりやらされる選手から不満が出た「なぜチームとして勝つための練習をしてくれないんですか?」。冨樫さんはこう答えたらしい。
「チームで勝とうとするのはもっと先でいい。もちろん負けていい試合はひとつもないけどな。プロでしっかり通用する選手を育てるのが俺の仕事だ。お前たちが10年、15年プレーするために、いま何をすべきなのか考えてやっている。1対1に強くなければ局面を打開できない。ゴール前も崩せない。ディフェンスは4バックだろうが3バックだろうがやられる。だから、まずはそれをトレーニングする。1対1に強い個々がつながってグループになれば、もっと強くなると思わないか? 戦術的なトレーニングはユースに上がってからできる。プロになればいろいろな監督と仕事をする。それはできませんでは通用しないよ」(第3章 「育成 −プロを育てる指導理論−」より)
もちろん海江田哲朗はヴェルディ再起のカギを育成に見ている。「ランド」に集まる人々の熱量に希望を抱いている。本当に学ぶところの多い本だ。芝生の匂いをかぎたくなってくる。
附記1、面と向かって「面白くて不愉快でした」言いやがった海江田さんは本書を送ってくれて、「えのきどさんの励ましに乗せられてどうにか書くことができました」と今度は殊勝な添え書きをはさんでくれました。えらいですね、僕って男は。生意気な後輩もちゃんと励ましてる。
2、実は今日の対戦相手・柏レイソルには竹本一彦、小見幸隆両氏の存在を通して読売クラブのDNAが持ち込まれているんですね。いや、前日に書いてますけど、どんな試合でした?
3、僕は実家が小田急線の向ヶ丘遊園にあって、読売ランドは2つ先の駅です。卒業した川崎市立生田中学校は生田駅を真ん中にして「遊園」「ランド」と3駅が学区でした。読売ランドのサッカーグラウンドはジャイアンツ球場&寮、読売日本交響楽団練習場、日本テレビ生田スタジオなんかと並んでました。あと遊園地の読売ランドには「近藤玲子水中バレエ団」があった。
4、新潟日報電子版(10月29日付、「アルビのある風景」)に先日のサッカー講座の記事が出ています。これは新潟県外から購読する媒体だそうです。電子版のオリジナル記事なんだなぁ。
「参考にしたのはピッチのなか全部です。育成年代の大会をみるたびに、技術、戦術、サッカーの中身をつぶさに研究した。盗めるものは盗めと。一方、ピッチ外は見習わなかった。中学生の選手がつばを吐く。審判に文句を言う。これではあかん。社会に出ていく子を育てているのにきちんと指導できていない。ヴェルディはここで止まるなと思った。確かに巧い。でもそこに慢心している。反省がない。謙虚さがない」(第4章「凋落 −Jリーグ以降の忘れもの−」より)
読者のうちアルビレックス新潟がJ1に昇格した後、サッカーに関心を持った世代や層も多いだろうと想像している。たぶん東京ヴェルディというクラブにそれほど強烈な印象を抱いてない筈だ。僕の目にもその時期、ヴェルデイは独善的に、Jの潮流から浮き上がって見えた。そして迷走を繰り返して経営危機まで行ってしまった。
だけど、リスペクトを失ってはならないと思う。そこにあるのはクラブチームの開拓者の栄光と挫折だ。先人の切り拓いた道を後続はたどる。海江田さんはこの本を「ランド」の芝生が匂いたつような作りにした。育成指導者の熱をそのまま伝えようとした。まぁ、全体像は本書を手にとってもらうとして、ひとつ、おお、最高だなぁと思うくだりを引用しよう。冨樫剛一氏(現・東京ヴェルディコーチ)がジュニアユースの指導をしたときだ。対人練習ばかりやらされる選手から不満が出た「なぜチームとして勝つための練習をしてくれないんですか?」。冨樫さんはこう答えたらしい。
「チームで勝とうとするのはもっと先でいい。もちろん負けていい試合はひとつもないけどな。プロでしっかり通用する選手を育てるのが俺の仕事だ。お前たちが10年、15年プレーするために、いま何をすべきなのか考えてやっている。1対1に強くなければ局面を打開できない。ゴール前も崩せない。ディフェンスは4バックだろうが3バックだろうがやられる。だから、まずはそれをトレーニングする。1対1に強い個々がつながってグループになれば、もっと強くなると思わないか? 戦術的なトレーニングはユースに上がってからできる。プロになればいろいろな監督と仕事をする。それはできませんでは通用しないよ」(第3章 「育成 −プロを育てる指導理論−」より)
もちろん海江田哲朗はヴェルディ再起のカギを育成に見ている。「ランド」に集まる人々の熱量に希望を抱いている。本当に学ぶところの多い本だ。芝生の匂いをかぎたくなってくる。
附記1、面と向かって「面白くて不愉快でした」言いやがった海江田さんは本書を送ってくれて、「えのきどさんの励ましに乗せられてどうにか書くことができました」と今度は殊勝な添え書きをはさんでくれました。えらいですね、僕って男は。生意気な後輩もちゃんと励ましてる。
2、実は今日の対戦相手・柏レイソルには竹本一彦、小見幸隆両氏の存在を通して読売クラブのDNAが持ち込まれているんですね。いや、前日に書いてますけど、どんな試合でした?
3、僕は実家が小田急線の向ヶ丘遊園にあって、読売ランドは2つ先の駅です。卒業した川崎市立生田中学校は生田駅を真ん中にして「遊園」「ランド」と3駅が学区でした。読売ランドのサッカーグラウンドはジャイアンツ球場&寮、読売日本交響楽団練習場、日本テレビ生田スタジオなんかと並んでました。あと遊園地の読売ランドには「近藤玲子水中バレエ団」があった。
4、新潟日報電子版(10月29日付、「アルビのある風景」)に先日のサッカー講座の記事が出ています。これは新潟県外から購読する媒体だそうです。電子版のオリジナル記事なんだなぁ。