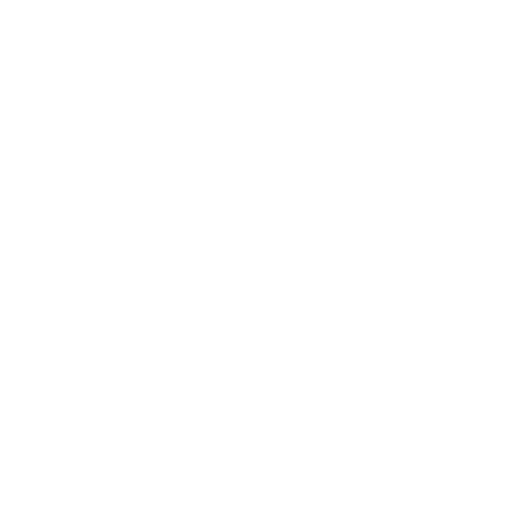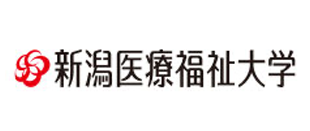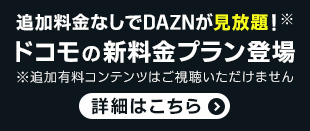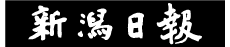【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第174回
2013/6/13
「北&日本海の問題」
NHKの朝ドラ『あまちゃん』が人気沸騰中だ。ここ最近はアキ(能年玲奈)とユイ(橋本愛)の歌う劇中歌『潮騒のメモリー』(脚本家の宮藤官九郎さんが作詞を手がける)が話題になっていて、先日、上野広小路で見かけた板前らしき男性も「♪北へ行くのね ここも北なのに」と口ずさんでいたくらいだ。あぁ、この人も『あまちゃん』見てるんだなぁと楽しくなった。しかし、5大会連続5回めのW杯出場が決まったというのに『あまちゃん』の話題かといぶかしく思われる読者がいるかも知れない。僕は「北」というのは相対的な問題だと言いたいのだ。
「北」は相対的な問題だ。たぶん北極点以外の場所は「どこから見たときに北」ということでしかない。例えば仙台市は僕の住む東京都台東区から見ると充分、北だが、新幹線で仙台へ移動するとそこはもはや「現在地」でしかなく、例えば青森市が北になる。で、今度は新幹線で青森へ移動するとまたまたそこは「現在地」になってしまって、まぁ、今度は函館市が北になる。僕らは「北」にたどり着くことがないのだ。「北」は蜃気楼のように逃げていく。
だから「北の酒場通り」でも「北へ帰ろう」でもいいが、人がそういうことを言うとき、揺るぎなく「中央/地方」の図式が出来上がっていると見るべきだろう。暗黙の了解事項は「中央(東京)から見たときに北」だ。あんまり「現在地」の側からは発想されない。「現在地」が仙台市でも青森市でも函館市でもいいけれど、そこに住んでる人にとってはそこがフツーというか基準点だ。世界の中心だ。橋本愛~っ。←世界の中心で愛を叫んでみたわけだが、これでは同時に橋本という名字も叫んでいるなぁ(笑)。
僕は「現在地」の側からの発想を大切にしたいと思う。なんだけど、案外、そこに住んでる人が「北」とか言うんだよね。くどいけれど、そこで暮らしているかぎり、その「現在地」はフツーであり、基準点だ。いっぺん視線を迂回させて、「中央(東京)」から見るような手順を踏まないと「北」という自意識は発生しない。まぁ、観光収益等、その種のエキゾティシズムが商売の役に立つ場合もあるでしょう。あるいは「中央(東京)」発のメディアにすっかりやられて、疑問を感じなくなってしまう場合もあるでしょう。
で、そういえばエッセイスト・酒井順子さんの「日本海」についての秀逸な考察があったぞと思い出した。酒井さんは小学館の『本の窓』というPR誌で「裏から見た日本」という連載を執筆中だ。今年の2月号に載った第4回「ああ、演歌が沁みる日本海」が大変考えさせられる内容だった。
彼女はまず「山と海の二軸で考えたとき、演歌に似合うのは海」「海もまた、どこの海でもいいというわけではないのです。太平洋や東シナ海に演歌が似合うかといったら、即座にNO。暖かそうな海は、人の気持ちを弛緩させます。演歌は日本酒と同様、味わいが『しまって』いることが重要なのです」と思索をすすめる。そして、日本海が演歌と相性のいい最大の理由として「そこが裏だから」と指摘する。
「演歌は、日の当たる道を晴れ晴れとした気持ちで歩む人を歌うものではありません。何らかの理由によって、人生の裏街道や日陰の道を歩む人、そして失意の中にある人について描かれる歌が圧倒的に多い。だからこそ、裏の海であるところの日本海が、歌の舞台として選ばれやすいのです」(『裏から見た日本』より引用)
まぁ、念のため言うが、僕はかねて「表日本/裏日本」という枠組みには反対の立場だ。酒井さんとは面識もあるが、彼女が「表日本/裏日本」を無批判に受容しているとは思わない。関心は現象面にあるのだ。だからこそ考察は日本海ソングの細部に及んでいき、「演歌において、人は決して車を運転しません。特に日本海に来る人の交通手段は、ほぼ確実に鉄道です」「本当の日本海の色は、時に沖縄の海のように青く澄んでいたりもするのですが、演歌のなかでは『なまり色』でないとお話になりません。それはもちろん、歌の主人公の心象風景もまた、なまり色だから」等の冴えたツッコミを生む。
「ここで気づくのは、日本海が持つ一定のイメージです。失恋した男なり女なりが汽車に乗って日本海を眺めると、外は悪天候で海鳥が鳴いている…という情景を描けば、それなりの日本海ソングはできあがる。この定型感は和歌の世界にも通じてるような気がして、海鳥が『鳴く』のと恋に破れた旅人が『泣く』のは掛詞のようだし、また『海』『波』『涙』『流れる』『濡れる』は縁語のよう。してみると『日本海』および『能登』等の日本海沿岸部の地名は、演歌における歌枕の役割を果たしているようにも思うのでした」(同じく引用)
その例として酒井さんはジェロの『海雪』に登場する出雲崎を挙げる。『海雪』を作詞した秋元康氏は「僕は一度も出雲崎に行ったことがない」「たまたま僕の事務所のスタッフの父親の出身地だったから」、この良寛さんの生まれた土地の名をピックアップしたそうだ。
これはすごいと思う。出雲崎へ一度も行ったことのない作詞家が描いた情景が、出雲崎とは縁もゆかりもないピッツバーグ出身の歌手によって歌われ、それが出雲崎へ一度も行ったことのない聴衆(僕もそうだ。酒井順子さんも行ったことがない由。読者のなかにもひょっとするといらっしゃるかもしれない)に届く。そこに共通のイメージが結ばれる。
まぁ、歌枕性や、観光資源としてのエキゾティシズムはそういうことなんだけど(そして実に面白いのだけど)、本稿の趣旨は「まぁ、それはそうと出雲崎に住んでる人だっているんだぞ」というところなんだなぁ。出雲崎に住んでる人の身にもなってほしいんだよ。出雲崎に住んでる人にとっては、そこはフツーかつ基準点であって、「悲しみの日本海」じゃない。てか、やってられんよ、そんなやたらとウエットなこと言われちゃ。
附記1、日本代表・W杯出場決定おめでとう! 初めてホームゲームで決まったわけですけど、やっぱり祝祭性ありますね。5大会連続ってことは20年、W杯に出続けることになります。なるほどなぁ、10代のファンにとってはW杯出場が当たり前なんだ(!)。
2、だけど前回、南ア大会出場決定のときは矢野貴章がピッチに立ってて盛り上がりましたね。アルビサポ的にはちょっぴりトーンダウンでしょうか。
3、先週末、都立汐入公園をウォーキングしてたら祭囃子が聴こえてきて、南千住の胡録(ころく)神社というところの祭礼でした。で、ここね、知らなかったんだけど永禄4年の川中島合戦の折、戦さに敗れ落ちのびた上杉家の家臣・高田嘉左衛門以下の12名が住みついた土地なんだって。胡録神社はその落武者でもあり、開拓者でもあった集団の信仰が由緒となったらしい。ただアレですよ、川中島合戦で上杉家負けてないでしょう。政治力はともかく、戦闘では引き分けはあっても負けてはいない。だから局地戦で敗退して、もう戦さはこりごりだよ、関東に住んじゃおうって決断したグループだったんですかねぇ。近所の神社が「川中島」とつながってたなんて驚きでした。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!

NHKの朝ドラ『あまちゃん』が人気沸騰中だ。ここ最近はアキ(能年玲奈)とユイ(橋本愛)の歌う劇中歌『潮騒のメモリー』(脚本家の宮藤官九郎さんが作詞を手がける)が話題になっていて、先日、上野広小路で見かけた板前らしき男性も「♪北へ行くのね ここも北なのに」と口ずさんでいたくらいだ。あぁ、この人も『あまちゃん』見てるんだなぁと楽しくなった。しかし、5大会連続5回めのW杯出場が決まったというのに『あまちゃん』の話題かといぶかしく思われる読者がいるかも知れない。僕は「北」というのは相対的な問題だと言いたいのだ。
「北」は相対的な問題だ。たぶん北極点以外の場所は「どこから見たときに北」ということでしかない。例えば仙台市は僕の住む東京都台東区から見ると充分、北だが、新幹線で仙台へ移動するとそこはもはや「現在地」でしかなく、例えば青森市が北になる。で、今度は新幹線で青森へ移動するとまたまたそこは「現在地」になってしまって、まぁ、今度は函館市が北になる。僕らは「北」にたどり着くことがないのだ。「北」は蜃気楼のように逃げていく。
だから「北の酒場通り」でも「北へ帰ろう」でもいいが、人がそういうことを言うとき、揺るぎなく「中央/地方」の図式が出来上がっていると見るべきだろう。暗黙の了解事項は「中央(東京)から見たときに北」だ。あんまり「現在地」の側からは発想されない。「現在地」が仙台市でも青森市でも函館市でもいいけれど、そこに住んでる人にとってはそこがフツーというか基準点だ。世界の中心だ。橋本愛~っ。←世界の中心で愛を叫んでみたわけだが、これでは同時に橋本という名字も叫んでいるなぁ(笑)。
僕は「現在地」の側からの発想を大切にしたいと思う。なんだけど、案外、そこに住んでる人が「北」とか言うんだよね。くどいけれど、そこで暮らしているかぎり、その「現在地」はフツーであり、基準点だ。いっぺん視線を迂回させて、「中央(東京)」から見るような手順を踏まないと「北」という自意識は発生しない。まぁ、観光収益等、その種のエキゾティシズムが商売の役に立つ場合もあるでしょう。あるいは「中央(東京)」発のメディアにすっかりやられて、疑問を感じなくなってしまう場合もあるでしょう。
で、そういえばエッセイスト・酒井順子さんの「日本海」についての秀逸な考察があったぞと思い出した。酒井さんは小学館の『本の窓』というPR誌で「裏から見た日本」という連載を執筆中だ。今年の2月号に載った第4回「ああ、演歌が沁みる日本海」が大変考えさせられる内容だった。
彼女はまず「山と海の二軸で考えたとき、演歌に似合うのは海」「海もまた、どこの海でもいいというわけではないのです。太平洋や東シナ海に演歌が似合うかといったら、即座にNO。暖かそうな海は、人の気持ちを弛緩させます。演歌は日本酒と同様、味わいが『しまって』いることが重要なのです」と思索をすすめる。そして、日本海が演歌と相性のいい最大の理由として「そこが裏だから」と指摘する。
「演歌は、日の当たる道を晴れ晴れとした気持ちで歩む人を歌うものではありません。何らかの理由によって、人生の裏街道や日陰の道を歩む人、そして失意の中にある人について描かれる歌が圧倒的に多い。だからこそ、裏の海であるところの日本海が、歌の舞台として選ばれやすいのです」(『裏から見た日本』より引用)
まぁ、念のため言うが、僕はかねて「表日本/裏日本」という枠組みには反対の立場だ。酒井さんとは面識もあるが、彼女が「表日本/裏日本」を無批判に受容しているとは思わない。関心は現象面にあるのだ。だからこそ考察は日本海ソングの細部に及んでいき、「演歌において、人は決して車を運転しません。特に日本海に来る人の交通手段は、ほぼ確実に鉄道です」「本当の日本海の色は、時に沖縄の海のように青く澄んでいたりもするのですが、演歌のなかでは『なまり色』でないとお話になりません。それはもちろん、歌の主人公の心象風景もまた、なまり色だから」等の冴えたツッコミを生む。
「ここで気づくのは、日本海が持つ一定のイメージです。失恋した男なり女なりが汽車に乗って日本海を眺めると、外は悪天候で海鳥が鳴いている…という情景を描けば、それなりの日本海ソングはできあがる。この定型感は和歌の世界にも通じてるような気がして、海鳥が『鳴く』のと恋に破れた旅人が『泣く』のは掛詞のようだし、また『海』『波』『涙』『流れる』『濡れる』は縁語のよう。してみると『日本海』および『能登』等の日本海沿岸部の地名は、演歌における歌枕の役割を果たしているようにも思うのでした」(同じく引用)
その例として酒井さんはジェロの『海雪』に登場する出雲崎を挙げる。『海雪』を作詞した秋元康氏は「僕は一度も出雲崎に行ったことがない」「たまたま僕の事務所のスタッフの父親の出身地だったから」、この良寛さんの生まれた土地の名をピックアップしたそうだ。
これはすごいと思う。出雲崎へ一度も行ったことのない作詞家が描いた情景が、出雲崎とは縁もゆかりもないピッツバーグ出身の歌手によって歌われ、それが出雲崎へ一度も行ったことのない聴衆(僕もそうだ。酒井順子さんも行ったことがない由。読者のなかにもひょっとするといらっしゃるかもしれない)に届く。そこに共通のイメージが結ばれる。
まぁ、歌枕性や、観光資源としてのエキゾティシズムはそういうことなんだけど(そして実に面白いのだけど)、本稿の趣旨は「まぁ、それはそうと出雲崎に住んでる人だっているんだぞ」というところなんだなぁ。出雲崎に住んでる人の身にもなってほしいんだよ。出雲崎に住んでる人にとっては、そこはフツーかつ基準点であって、「悲しみの日本海」じゃない。てか、やってられんよ、そんなやたらとウエットなこと言われちゃ。
附記1、日本代表・W杯出場決定おめでとう! 初めてホームゲームで決まったわけですけど、やっぱり祝祭性ありますね。5大会連続ってことは20年、W杯に出続けることになります。なるほどなぁ、10代のファンにとってはW杯出場が当たり前なんだ(!)。
2、だけど前回、南ア大会出場決定のときは矢野貴章がピッチに立ってて盛り上がりましたね。アルビサポ的にはちょっぴりトーンダウンでしょうか。
3、先週末、都立汐入公園をウォーキングしてたら祭囃子が聴こえてきて、南千住の胡録(ころく)神社というところの祭礼でした。で、ここね、知らなかったんだけど永禄4年の川中島合戦の折、戦さに敗れ落ちのびた上杉家の家臣・高田嘉左衛門以下の12名が住みついた土地なんだって。胡録神社はその落武者でもあり、開拓者でもあった集団の信仰が由緒となったらしい。ただアレですよ、川中島合戦で上杉家負けてないでしょう。政治力はともかく、戦闘では引き分けはあっても負けてはいない。だから局地戦で敗退して、もう戦さはこりごりだよ、関東に住んじゃおうって決断したグループだったんですかねぇ。近所の神社が「川中島」とつながってたなんて驚きでした。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!