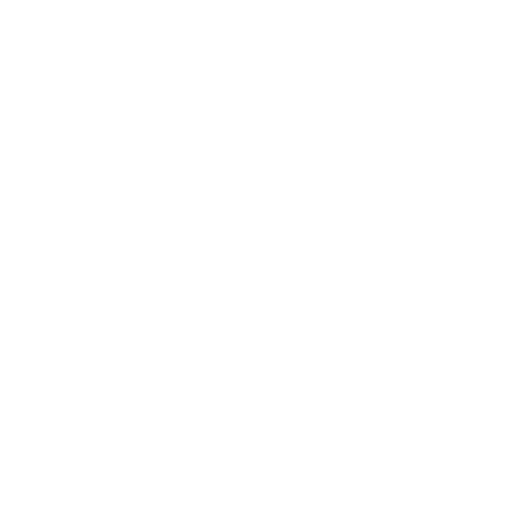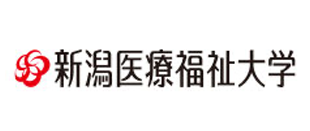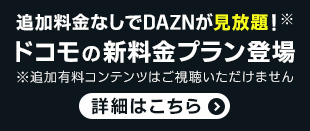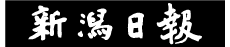【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第175回
2013/6/20
「勘を磨く近道はあるのか?」
『井上ひさしコレクション/ことばの巻』(井上ひさし著、岩波書店)を読んでいたら、以下の箇所に行き当たった。引用しますから、まぁ読んでみて下さい。同書は先年、亡くなられた井上さんの雑文集成シリーズの一冊。初出は1977年4月号の『小説現代』とのこと。
「喜劇役者にとって気になる存在というものがある。それは客だろうか。じつはちがう。どこかにお調子者が『お客様は神様です』という台詞(せりふ)を発明したが、こんなものは嘘っぱちもいいところだ。<客が新しい才能を見出す、しかも神の如き叡智をもって>などというのは迷信の最たるもので、客は追従するだけである。べつに言えば、才能を発見することにおいてもっとも怠慢なのは観客なのだ。どこかで『何某(なにがし)はおもしろい』という風評が立つ。客はこの風評を口真似するだけだ。だれかが折紙をつけてくれないと、そのよさが理解できないおろかものの集合体、それが客というものの正体である。だから喜劇役者たちは、はじめはあまりお客のことを気にしない。ただし、客の気持ちが動きだしたらはなしは別である。なにしろスターになるためには、全観客の一致した認知が必要だから。
はやばやと種明ししてしまうと、喜劇役者が気にするのは裏方たちの反応である。もっとも裏方全員に<新しい才能をいちはやく嗅(か)ぎ当てる叡智>が授けられているわけではない。そのころの小屋には、文芸部、大道具係、照明係、効果係、楽団員、楽屋番などをひっくるめて、二十五、六名の親方が常駐していたが、この叡智に恵まれていたのは片手で数えるぐらいしかいなかったろう。大道具主任や照明主任や楽屋番のおばさんなどがそうで、いずれも五十を越えた人たちばかりである」(『トンカチの親方』より)
もう、ものすごく先が読みたくなる導入だ。話はコメディアンの才能を百発百中、予知する大道具係の老人へとつながっていく。若き日、浅草のストリップ劇場・フランス座の文芸部に籍をおいた井上さんならではの話だ。ちなみに萩本欽一、渥美清といったスターはこうしたストリップ劇場の幕間のショーから巣立っていった。
しかし、引用した箇所を読んで「ドキリ」、もしくは「ニヤリ」と来てしまった読者も多いのじゃないか。僕はジャンルを越えて、是非、サッカーファンにこの文章をご覧いただきたかった。当然、自戒を込めてということでもある。何しろ最初に「ドキリ」「ニヤリ」と来て、引用することに決めたのは他ならぬ僕自身だ。
もちろん井上さんが言ってるのは喜劇、お笑いの観客であって、サッカーファン、サポーターについてではない。観客論として、おそらく日本一、「パフォーマー(選手)を後押しする」ことに自覚的なのはJリーグのサポーターじゃないかと思う(僕が不案内なジャンルで言うと、細分化されたアイドルの世界もそうなのかも知れない)。だもんで「客はこの風評を口真似するだけだ」「だれかが折紙をつけてくれないと、そのよさが理解できないおろかものの集合体」といった指摘がそのまま通じるとは僕も考えない。
が、いいセンはついている。僕のようなライターは何とか「才能を発見することにおいてもっとも怠慢」という状態を脱しようと努力する。そういう仕事だ。が、誰かが折紙をつけてくれて、それでやっと、あぁ、俺の感じていたことで良かったのかと安心することだって多い。だから、いいセンついているというのは「君たち、サポーターの駄目なところをついているよ」というのじゃなしに、本当に急所をつかれた感じなのだ。
たぶんサッカー界にも「大道具係の老人」みたいな人はいる筈だ。ま、スポーツの世界だから年齢的には老人じゃないだろうけれど。そして、選手らが観客よりも、と書くと語弊があろうから、ここは観客同様に、とするが、選手どうしや裏方を含めた身内の評判を気にするだろうことは間違いがない。
では、「口真似するだけ」の「おろかもの」の観客であるような僕らが、少しでも見巧者に近づくにはどうしたらいいだろう。井上ひさしさんは見巧者、目ききの共通項を「芸人を大勢みてきている」ことだという。文中、若き日の井上さんに「大道具係の老人」はこう言うのだ。
「でもねぇ、役者のよさなんてものはよくわからん。いいからいいのだ、というほかないのだよ。そのへんは将棋と同じさ。悪手は駒を置いたとたんぴんとくる。すぐわかる。ところが好手は、王と飛車の両取りなんてバカな手は別として、ほんとうの好手というやつは、駒を置いたときすぐにわからない」
だから、数多く見るしかないんだろうかねぇ。年季が加わると、あぁ、こういう選手は伸びる、こういう選手は伸びない、あるいはこういう監督は成功する、失敗するみたいなことが感覚的にわかるようになるんだろうかねぇ。
附記1、あと『「どす」と「です」と「だす」』という1979年初出の文章もものすごくサッカーに通じている気がして、どっちを採用しようか迷いました。このなかに京ことばの凄みに関するくだりがあって、例えば「命令表現が極度に発達し、洗練されている」例として、「早くしなさい」という命令表現に三十三種の言い方があるというのを紹介している。いいですか、列記しますよ。
早うセー/早うシー/早うシーナ/早うセンカ/早うセンカイ/早うセンカイナ/早うシンカ/早うオシ/早うオシーナ/早うオシンカ/早うオシンカイナ/早うシナハイ/早うシナハイナ/早うオシナハイ/早うオシナハイナ/早うオシナハンカ/早うオシナハンカイナ/早うオシヤス/早うオシヤスナ/早うオシヤハンカ/早うオシヤハンカイナ/早うシテクレ/早うシテクレンカ/早うシテクレンカイナ/早うシトークレヤス/早うシトークレヤスナ/早うオシヤシトークレヤスナ/早うシテクレハラシマヘンカ/早うシトークレヤサシマヘンカ/早うシヤハレ/早うシヤガレ/早うシクサレ/早うシクサランカイ
僕は近代化以降ならば新潟の仮想敵は東京であるべきだと思いますが、文化的には同じグループですよね。命令表現なんて幼稚で一本調子です。だから「京都人は、ひとにものを頼んだり、命令したりすることに長じている」わけです。
で、僕のイメージするサッカーのコーディネーション能力ってこういうことなんですよ。戦術バリエーションみたいなことをイメージしてもいいけど、個々の選手の対応力とか、バランスが崩れたときにまとめる力みたいなほうが近い。だから京都人が状況によって三十三通りの「早くしなさい」を使い分けてるように、巧い選手っていうのは具体的なイメージのストックがあって、他のチョイスはあり得ないってたったひとつが高解像度で見えている。
だから新潟人(東京人でもいいけど)と京都人が対峙したら、カンタンに丸め込まれるわけですよね。こういう1対1のイメージです。これはね、具体的なバリエーション持ってる相手に敵わない。センスってこういうことですね。で、京都人には新潟人(や東京人)のやることがスッカスカに見える筈なんです。
2、は今週はもう入りませんね(笑)。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!

『井上ひさしコレクション/ことばの巻』(井上ひさし著、岩波書店)を読んでいたら、以下の箇所に行き当たった。引用しますから、まぁ読んでみて下さい。同書は先年、亡くなられた井上さんの雑文集成シリーズの一冊。初出は1977年4月号の『小説現代』とのこと。
「喜劇役者にとって気になる存在というものがある。それは客だろうか。じつはちがう。どこかにお調子者が『お客様は神様です』という台詞(せりふ)を発明したが、こんなものは嘘っぱちもいいところだ。<客が新しい才能を見出す、しかも神の如き叡智をもって>などというのは迷信の最たるもので、客は追従するだけである。べつに言えば、才能を発見することにおいてもっとも怠慢なのは観客なのだ。どこかで『何某(なにがし)はおもしろい』という風評が立つ。客はこの風評を口真似するだけだ。だれかが折紙をつけてくれないと、そのよさが理解できないおろかものの集合体、それが客というものの正体である。だから喜劇役者たちは、はじめはあまりお客のことを気にしない。ただし、客の気持ちが動きだしたらはなしは別である。なにしろスターになるためには、全観客の一致した認知が必要だから。
はやばやと種明ししてしまうと、喜劇役者が気にするのは裏方たちの反応である。もっとも裏方全員に<新しい才能をいちはやく嗅(か)ぎ当てる叡智>が授けられているわけではない。そのころの小屋には、文芸部、大道具係、照明係、効果係、楽団員、楽屋番などをひっくるめて、二十五、六名の親方が常駐していたが、この叡智に恵まれていたのは片手で数えるぐらいしかいなかったろう。大道具主任や照明主任や楽屋番のおばさんなどがそうで、いずれも五十を越えた人たちばかりである」(『トンカチの親方』より)
もう、ものすごく先が読みたくなる導入だ。話はコメディアンの才能を百発百中、予知する大道具係の老人へとつながっていく。若き日、浅草のストリップ劇場・フランス座の文芸部に籍をおいた井上さんならではの話だ。ちなみに萩本欽一、渥美清といったスターはこうしたストリップ劇場の幕間のショーから巣立っていった。
しかし、引用した箇所を読んで「ドキリ」、もしくは「ニヤリ」と来てしまった読者も多いのじゃないか。僕はジャンルを越えて、是非、サッカーファンにこの文章をご覧いただきたかった。当然、自戒を込めてということでもある。何しろ最初に「ドキリ」「ニヤリ」と来て、引用することに決めたのは他ならぬ僕自身だ。
もちろん井上さんが言ってるのは喜劇、お笑いの観客であって、サッカーファン、サポーターについてではない。観客論として、おそらく日本一、「パフォーマー(選手)を後押しする」ことに自覚的なのはJリーグのサポーターじゃないかと思う(僕が不案内なジャンルで言うと、細分化されたアイドルの世界もそうなのかも知れない)。だもんで「客はこの風評を口真似するだけだ」「だれかが折紙をつけてくれないと、そのよさが理解できないおろかものの集合体」といった指摘がそのまま通じるとは僕も考えない。
が、いいセンはついている。僕のようなライターは何とか「才能を発見することにおいてもっとも怠慢」という状態を脱しようと努力する。そういう仕事だ。が、誰かが折紙をつけてくれて、それでやっと、あぁ、俺の感じていたことで良かったのかと安心することだって多い。だから、いいセンついているというのは「君たち、サポーターの駄目なところをついているよ」というのじゃなしに、本当に急所をつかれた感じなのだ。
たぶんサッカー界にも「大道具係の老人」みたいな人はいる筈だ。ま、スポーツの世界だから年齢的には老人じゃないだろうけれど。そして、選手らが観客よりも、と書くと語弊があろうから、ここは観客同様に、とするが、選手どうしや裏方を含めた身内の評判を気にするだろうことは間違いがない。
では、「口真似するだけ」の「おろかもの」の観客であるような僕らが、少しでも見巧者に近づくにはどうしたらいいだろう。井上ひさしさんは見巧者、目ききの共通項を「芸人を大勢みてきている」ことだという。文中、若き日の井上さんに「大道具係の老人」はこう言うのだ。
「でもねぇ、役者のよさなんてものはよくわからん。いいからいいのだ、というほかないのだよ。そのへんは将棋と同じさ。悪手は駒を置いたとたんぴんとくる。すぐわかる。ところが好手は、王と飛車の両取りなんてバカな手は別として、ほんとうの好手というやつは、駒を置いたときすぐにわからない」
だから、数多く見るしかないんだろうかねぇ。年季が加わると、あぁ、こういう選手は伸びる、こういう選手は伸びない、あるいはこういう監督は成功する、失敗するみたいなことが感覚的にわかるようになるんだろうかねぇ。
附記1、あと『「どす」と「です」と「だす」』という1979年初出の文章もものすごくサッカーに通じている気がして、どっちを採用しようか迷いました。このなかに京ことばの凄みに関するくだりがあって、例えば「命令表現が極度に発達し、洗練されている」例として、「早くしなさい」という命令表現に三十三種の言い方があるというのを紹介している。いいですか、列記しますよ。
早うセー/早うシー/早うシーナ/早うセンカ/早うセンカイ/早うセンカイナ/早うシンカ/早うオシ/早うオシーナ/早うオシンカ/早うオシンカイナ/早うシナハイ/早うシナハイナ/早うオシナハイ/早うオシナハイナ/早うオシナハンカ/早うオシナハンカイナ/早うオシヤス/早うオシヤスナ/早うオシヤハンカ/早うオシヤハンカイナ/早うシテクレ/早うシテクレンカ/早うシテクレンカイナ/早うシトークレヤス/早うシトークレヤスナ/早うオシヤシトークレヤスナ/早うシテクレハラシマヘンカ/早うシトークレヤサシマヘンカ/早うシヤハレ/早うシヤガレ/早うシクサレ/早うシクサランカイ
僕は近代化以降ならば新潟の仮想敵は東京であるべきだと思いますが、文化的には同じグループですよね。命令表現なんて幼稚で一本調子です。だから「京都人は、ひとにものを頼んだり、命令したりすることに長じている」わけです。
で、僕のイメージするサッカーのコーディネーション能力ってこういうことなんですよ。戦術バリエーションみたいなことをイメージしてもいいけど、個々の選手の対応力とか、バランスが崩れたときにまとめる力みたいなほうが近い。だから京都人が状況によって三十三通りの「早くしなさい」を使い分けてるように、巧い選手っていうのは具体的なイメージのストックがあって、他のチョイスはあり得ないってたったひとつが高解像度で見えている。
だから新潟人(東京人でもいいけど)と京都人が対峙したら、カンタンに丸め込まれるわけですよね。こういう1対1のイメージです。これはね、具体的なバリエーション持ってる相手に敵わない。センスってこういうことですね。で、京都人には新潟人(や東京人)のやることがスッカスカに見える筈なんです。
2、は今週はもう入りませんね(笑)。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!