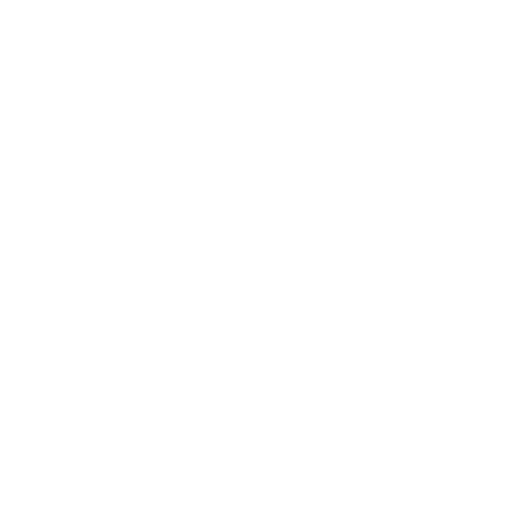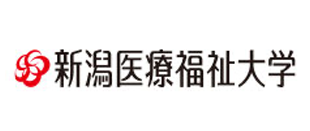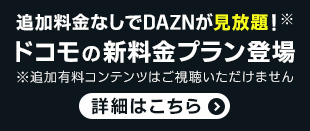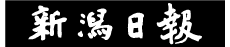【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第73回
2010/10/21
「新潟の10番」
天皇杯3回戦、新潟×町田。
マルシオの復帰戦。試合の意味はそれに尽きる。
1ヶ月の戦線離脱は本当に長かった。誰もがこの日を待ちわびていた。ビッグスワンのピッチに立つ「新潟の10番」を見て、サポーターは全員、ホッと胸をなでおろした。全員というのは(疑いなく)文字通りの全員だ。新潟日報の復帰報道を知らなかったわけじゃない。ていうか、そんなの目を皿のようにして読み込んだ。自分の目で見るまで安心できなかったのだ。
「待ってたぞ!」「おかえり!」の代わりに大声で彼の名を呼ぶ。マルシオ!マルシオ! 町田ゼルビアがいかに好チームだろうと、2回戦で東京Vを破って意気盛んだろうと、悪いけど負ける気がしない。「新潟の10番」がピッチへ帰ってきた。
しかし、今年もあり得ないほどトゥーマッチなシーズンだ。波乱万丈。開幕から勝利に見離され、気の早いサポはJ1残留争いの覚悟を固める。そうしたらミシェウの本格化、チョ・ヨンチョルの急成長もあって黒崎アルビの快進撃が始まる。どんな相手とやっても自分のスタイルを貫く戦いぶりだ。日程にも助けられ、苦手の夏場も勢いが止まらない。これは楽しみなチームができあがった、新潟は初めて本当の優勝争いを経験するぞと思ったら、矢野貴章がドイツ電撃移籍だ。それはめでたい話だし、気持ちよく送り出そう、チームは「ポスト貴章」システムの構築だと思い直してたら、マルシオ、ミシェウの戦線離脱でそれどころじゃなくなってしまった。11月はヨンチョルが欠けるのがわかっている。
ジェットコースター。ロバート・コクランら『24』のシナリオチームを持って来てもここまでトゥーマッチな台本は用意できないだろう(それとも彼らなら「黒崎監督暗殺計画」とか「マスコットのスワンちゃんが実は敵のスパイ」とか、奇想天外な台本を用意するのか)。選手が揃わないとやりくりのイメージばかりが先に立って、なかなか新チーム構想を描けない。特にマルシオの復帰はマストだった。マルシオ不在で攻撃の連携を作っても、どうしても意味合いが薄い。
試合。立ち上がりアグレッシブに奪いに来て、町田元気いいなぁと思う。マルシオに人数かけて寄せるのは(気持ちはわかるけど)勘弁してーと思う。復帰戦で削られ、傷んじゃったら元も子もない。ところが当方の心配をよそにマルシオは悠然とふるまっている。
町田の元気いいのは続かなかった。初手の鬼プレスにまったく動じず、新潟は(マルシオに呼吸を合わすかのように)悠然とふるまいだす。ゲームを支配した。この時間帯の妙味。僕は腕相撲を連想していた。腕相撲は手を合わせた瞬間、当人に勝ち負けがわかる。サッカー選手にもそれがあるのではないか。町田は「うわ、こりゃ勝てないや」と思ってるくらい萎縮(いしゅく)していた。
ゴールは田中亜土夢だ。前半24分、左サイド・内田潤のクロスに頭で合わせた。ヨンチョルの11月離脱を思えば、一番決めてほしい選手だ。ひたむきに続ければ必ず結果に結びつく。亜土夢には自信を持ってほしい。自信というのはですね、「ひたむきに続ければ必ず結果に結びつく」を自分で信じることです。
前半ロスタイムには、そんな亜土夢への想いを後押しするかのような幸運が舞い込む。西大伍のグラウンダーのクロスが、嘘みたいにスーッと亜土夢のとこまで流れ着くのだ。敵DFは人数はいた。が、ぜんぜん対応できない。亜土夢はそれを蹴り込むだけでよかった。何と亜土夢2得点!
僕はNHK-BSでテレビ観戦だったが、前半終了時のインタビューで町田・相馬直樹監督が「勇気が足りない」を連発していたのが印象に残る。相馬さんは本当にカンカンだった。そりゃそうだなぁと思うのは、さっきの腕相撲の例えだ。一瞬で勝負が決まる腕相撲と違って、サッカーはひと試合のなかに山あり谷ありだ。萎縮していて勝てるわけがない。いや、一瞬で勝負が決まるタイプの競技だって同じかもしれない。完全に余談になるけれど、相撲の白鵬のお父さんのエピソードを紹介させてほしい。
これは『相撲よ!』(白鵬・著、角川書店)に登場するエピソードだ。御存知の通り、白鵬のお父さん、ジグジドゥ・ムンフバトさんはモンゴル相撲の大横綱であり、かつモンゴル初の五輪メダリスト(メキシコ五輪レスリング重量級・銀)だ。簡単に言って「国民的英雄」だ。したがって白鵬は長嶋一茂を百倍にしたようなお坊ちゃんであり、
大都市・ウランバートルのど真ん中、東京で言ったら銀座三越の隣りに家がある状態で育った。で、鬼神のように強かったお父さんには、モンゴル人なら誰でも知っている名言が残っている。僕は強者のメンタリティーをこれほどハッキリ言葉にした例を知らない。勝負事の大体のところはこの言葉に集約されるのではないか。
「勝つ俺があわててないのに、負けるお前がなぜあわてる?」
余談が長くなった。だけど、これは深いでしょう。JFLの超新星・町田は相馬監督にネジを巻かれて、後半、積極的に人数をかけて来た。そうなると試合は互角に均衡する。前半のリードのおかげで、新潟は何とか逃げ切りに成功した。もって他山の石としたい。サッカーは勇気だ。特に格上に挑むときには。
附記1、「新潟の10番」というタイトルのわりに途中から白鵬のお父さんの話になって、マルシオのことぜんぜん出てこない文ですけど、僕ね、町田を萎縮させたの、煎じつめるとマルシオだと思うんですよ。マルシオの存在感に敵も味方もすっかり持っていかれた。だからこの原稿はやっぱりマルシオのことを書いてるんですよ。
2、代表の日韓戦はヨンチョルが出なくて残念でした。しかし、ザッケローニ監督はほんのわずかの指導で守備戦術をオーガナイズしてましたね。いや、アルゼンチンに勝ったって歴史的なことですよ。ホームだろうが、相手のコンディションが整ってなかろうが、そういう但し書きが何個ついたとしてもアルゼンチンに勝ったんですから。W杯16強に続く日本サッカーの快挙ですね。
3、は特に思いつきませんでした。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
天皇杯3回戦、新潟×町田。
マルシオの復帰戦。試合の意味はそれに尽きる。
1ヶ月の戦線離脱は本当に長かった。誰もがこの日を待ちわびていた。ビッグスワンのピッチに立つ「新潟の10番」を見て、サポーターは全員、ホッと胸をなでおろした。全員というのは(疑いなく)文字通りの全員だ。新潟日報の復帰報道を知らなかったわけじゃない。ていうか、そんなの目を皿のようにして読み込んだ。自分の目で見るまで安心できなかったのだ。
「待ってたぞ!」「おかえり!」の代わりに大声で彼の名を呼ぶ。マルシオ!マルシオ! 町田ゼルビアがいかに好チームだろうと、2回戦で東京Vを破って意気盛んだろうと、悪いけど負ける気がしない。「新潟の10番」がピッチへ帰ってきた。
しかし、今年もあり得ないほどトゥーマッチなシーズンだ。波乱万丈。開幕から勝利に見離され、気の早いサポはJ1残留争いの覚悟を固める。そうしたらミシェウの本格化、チョ・ヨンチョルの急成長もあって黒崎アルビの快進撃が始まる。どんな相手とやっても自分のスタイルを貫く戦いぶりだ。日程にも助けられ、苦手の夏場も勢いが止まらない。これは楽しみなチームができあがった、新潟は初めて本当の優勝争いを経験するぞと思ったら、矢野貴章がドイツ電撃移籍だ。それはめでたい話だし、気持ちよく送り出そう、チームは「ポスト貴章」システムの構築だと思い直してたら、マルシオ、ミシェウの戦線離脱でそれどころじゃなくなってしまった。11月はヨンチョルが欠けるのがわかっている。
ジェットコースター。ロバート・コクランら『24』のシナリオチームを持って来てもここまでトゥーマッチな台本は用意できないだろう(それとも彼らなら「黒崎監督暗殺計画」とか「マスコットのスワンちゃんが実は敵のスパイ」とか、奇想天外な台本を用意するのか)。選手が揃わないとやりくりのイメージばかりが先に立って、なかなか新チーム構想を描けない。特にマルシオの復帰はマストだった。マルシオ不在で攻撃の連携を作っても、どうしても意味合いが薄い。
試合。立ち上がりアグレッシブに奪いに来て、町田元気いいなぁと思う。マルシオに人数かけて寄せるのは(気持ちはわかるけど)勘弁してーと思う。復帰戦で削られ、傷んじゃったら元も子もない。ところが当方の心配をよそにマルシオは悠然とふるまっている。
町田の元気いいのは続かなかった。初手の鬼プレスにまったく動じず、新潟は(マルシオに呼吸を合わすかのように)悠然とふるまいだす。ゲームを支配した。この時間帯の妙味。僕は腕相撲を連想していた。腕相撲は手を合わせた瞬間、当人に勝ち負けがわかる。サッカー選手にもそれがあるのではないか。町田は「うわ、こりゃ勝てないや」と思ってるくらい萎縮(いしゅく)していた。
ゴールは田中亜土夢だ。前半24分、左サイド・内田潤のクロスに頭で合わせた。ヨンチョルの11月離脱を思えば、一番決めてほしい選手だ。ひたむきに続ければ必ず結果に結びつく。亜土夢には自信を持ってほしい。自信というのはですね、「ひたむきに続ければ必ず結果に結びつく」を自分で信じることです。
前半ロスタイムには、そんな亜土夢への想いを後押しするかのような幸運が舞い込む。西大伍のグラウンダーのクロスが、嘘みたいにスーッと亜土夢のとこまで流れ着くのだ。敵DFは人数はいた。が、ぜんぜん対応できない。亜土夢はそれを蹴り込むだけでよかった。何と亜土夢2得点!
僕はNHK-BSでテレビ観戦だったが、前半終了時のインタビューで町田・相馬直樹監督が「勇気が足りない」を連発していたのが印象に残る。相馬さんは本当にカンカンだった。そりゃそうだなぁと思うのは、さっきの腕相撲の例えだ。一瞬で勝負が決まる腕相撲と違って、サッカーはひと試合のなかに山あり谷ありだ。萎縮していて勝てるわけがない。いや、一瞬で勝負が決まるタイプの競技だって同じかもしれない。完全に余談になるけれど、相撲の白鵬のお父さんのエピソードを紹介させてほしい。
これは『相撲よ!』(白鵬・著、角川書店)に登場するエピソードだ。御存知の通り、白鵬のお父さん、ジグジドゥ・ムンフバトさんはモンゴル相撲の大横綱であり、かつモンゴル初の五輪メダリスト(メキシコ五輪レスリング重量級・銀)だ。簡単に言って「国民的英雄」だ。したがって白鵬は長嶋一茂を百倍にしたようなお坊ちゃんであり、
大都市・ウランバートルのど真ん中、東京で言ったら銀座三越の隣りに家がある状態で育った。で、鬼神のように強かったお父さんには、モンゴル人なら誰でも知っている名言が残っている。僕は強者のメンタリティーをこれほどハッキリ言葉にした例を知らない。勝負事の大体のところはこの言葉に集約されるのではないか。
「勝つ俺があわててないのに、負けるお前がなぜあわてる?」
余談が長くなった。だけど、これは深いでしょう。JFLの超新星・町田は相馬監督にネジを巻かれて、後半、積極的に人数をかけて来た。そうなると試合は互角に均衡する。前半のリードのおかげで、新潟は何とか逃げ切りに成功した。もって他山の石としたい。サッカーは勇気だ。特に格上に挑むときには。
附記1、「新潟の10番」というタイトルのわりに途中から白鵬のお父さんの話になって、マルシオのことぜんぜん出てこない文ですけど、僕ね、町田を萎縮させたの、煎じつめるとマルシオだと思うんですよ。マルシオの存在感に敵も味方もすっかり持っていかれた。だからこの原稿はやっぱりマルシオのことを書いてるんですよ。
2、代表の日韓戦はヨンチョルが出なくて残念でした。しかし、ザッケローニ監督はほんのわずかの指導で守備戦術をオーガナイズしてましたね。いや、アルゼンチンに勝ったって歴史的なことですよ。ホームだろうが、相手のコンディションが整ってなかろうが、そういう但し書きが何個ついたとしてもアルゼンチンに勝ったんですから。W杯16強に続く日本サッカーの快挙ですね。
3、は特に思いつきませんでした。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。