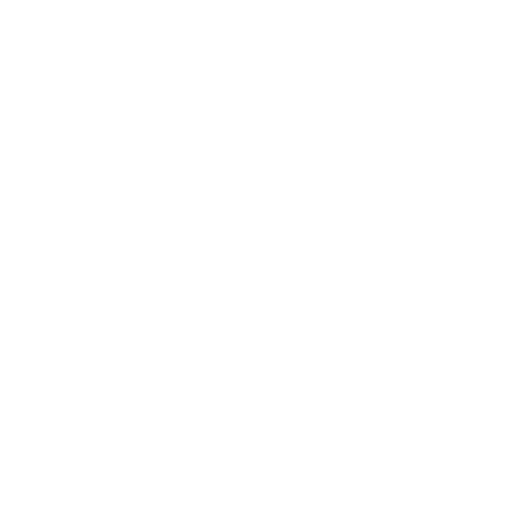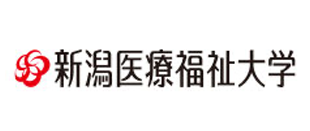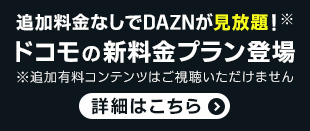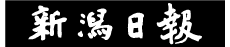【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第84回(前編)
2011/3/31
「鳥を勉強する」
連休中は『鳥脳力』(渡辺茂・著、化学同人・刊)を読んで過ごした。TBSラジオの仕事で著者の渡辺茂・慶大教授(比較認知神経学)をゲストにお招きすることになり、まぁ、予習をしておく必要があった。それに電力不足の状況下、窓際のソファで本を読むのは節電に最も協力できる。テレビを見て、原発事故の対応にダメ出ししていても実際問題、僕には水をかけて炉の温度を下げることができない。気をもんでくたくたになっても仕方ないのだ。「何故、無意味に(水平打ちしかできない)機動隊の放水車を出して、時間を浪費し、隊員を危険にさらすような不手際が起きたのか」といった疑問は忘れないようにして、後で検証するしかない。
そうしたら『鳥脳力』がとんでもなく面白い本だった。読者はアルビレックス新潟という、白鳥のクラブのサポーターなのだが、鳥について考えてみたことがあるだろうか。そもそも鳥とは何だろうか。渡辺教授は15ページめにいきなり結論を提示している。鳥とは「絶滅しなかった恐竜」なのだった。
「つまりは、恐竜は絶滅しなかったのである。なぜなら鳥は恐竜から進化した動物ではなく、生き残った恐竜だからである。正確には鳥は恐竜綱竜盤目獣脚亜目に属する、れっきとした恐竜である。したがって、恐竜は鳥型恐竜と非鳥型恐竜に分かれたといえる。実際、南極の白亜紀後期の地層からカモの化石が見つかっており、恐竜の絶滅以前に非鳥型恐竜と鳥(鳥型恐竜)は共存していたことになる。そして鳥型恐竜は現代鳥として生き残ったのである」(同書・第1章冒頭より)
そりゃ主力を抜かれても厳しいJ1戦線を生き残るわけである。僕は去年、ふとしたときに白鳥は渡り鳥ではないかと気づき、「渡り鳥のクラブ」であるなら選手の流出もあきらめざるを得ないのかと暗然とした。(ちなみに当時、「スワンちゃんが実は敵のスパイであった」という物語を『24』のシナリオチームに書かせたらどうなるかという、意味のわからないアイデアを夢想したのだが、想定したクライマックスシーンでスワンちゃんがアルビくんに言う台詞は「わたしたち、しょせん渡り鳥なのよ!」だった)しかし、そんなことよりも生き残るという特性の方がはるかに年季が入っていたのだ。叉、これで従来、「ラテン語で王の意」とだけ説明されてきた「REX」も意味を際立たせる。「A-REX」はひょっとすると「T-REX」(ティラノザウルス)に物凄く近い言葉ではないか。
つまり、鳥の知覚研究はスリリングなことに恐竜の知覚研究でもあるのだ。渡辺教授は豊富な実験例を示し、研究者たちの鳥脳へのアプローチを紹介してくれる。例えば伝書鳩の歴史から語り起こす「鳥脳のナヴィゲーション・システム」は興味深い。ゲーム中のサッカー選手も同じだが、動きながら(鳥の場合は飛びながら)、ときに反転したりして、空間認知するのは情報処理として大変なことである。
僕はセルジオ越後さんを助手席に乗せてクルマを運転したことがあり、道に迷って「角を曲がって曲がって曲がって曲がる(しかも90度ではない)」ような場面で、即座に「方向、こっちよ」と言われ仰天した経験がある。あぁ、反転しながらゴールの方向がわかってる習慣を持つ人なのだ、と感心した。あれはセルジオさんじゃなくて鳥でもよかったのか。
−後編に続く−
連休中は『鳥脳力』(渡辺茂・著、化学同人・刊)を読んで過ごした。TBSラジオの仕事で著者の渡辺茂・慶大教授(比較認知神経学)をゲストにお招きすることになり、まぁ、予習をしておく必要があった。それに電力不足の状況下、窓際のソファで本を読むのは節電に最も協力できる。テレビを見て、原発事故の対応にダメ出ししていても実際問題、僕には水をかけて炉の温度を下げることができない。気をもんでくたくたになっても仕方ないのだ。「何故、無意味に(水平打ちしかできない)機動隊の放水車を出して、時間を浪費し、隊員を危険にさらすような不手際が起きたのか」といった疑問は忘れないようにして、後で検証するしかない。
そうしたら『鳥脳力』がとんでもなく面白い本だった。読者はアルビレックス新潟という、白鳥のクラブのサポーターなのだが、鳥について考えてみたことがあるだろうか。そもそも鳥とは何だろうか。渡辺教授は15ページめにいきなり結論を提示している。鳥とは「絶滅しなかった恐竜」なのだった。
「つまりは、恐竜は絶滅しなかったのである。なぜなら鳥は恐竜から進化した動物ではなく、生き残った恐竜だからである。正確には鳥は恐竜綱竜盤目獣脚亜目に属する、れっきとした恐竜である。したがって、恐竜は鳥型恐竜と非鳥型恐竜に分かれたといえる。実際、南極の白亜紀後期の地層からカモの化石が見つかっており、恐竜の絶滅以前に非鳥型恐竜と鳥(鳥型恐竜)は共存していたことになる。そして鳥型恐竜は現代鳥として生き残ったのである」(同書・第1章冒頭より)
そりゃ主力を抜かれても厳しいJ1戦線を生き残るわけである。僕は去年、ふとしたときに白鳥は渡り鳥ではないかと気づき、「渡り鳥のクラブ」であるなら選手の流出もあきらめざるを得ないのかと暗然とした。(ちなみに当時、「スワンちゃんが実は敵のスパイであった」という物語を『24』のシナリオチームに書かせたらどうなるかという、意味のわからないアイデアを夢想したのだが、想定したクライマックスシーンでスワンちゃんがアルビくんに言う台詞は「わたしたち、しょせん渡り鳥なのよ!」だった)しかし、そんなことよりも生き残るという特性の方がはるかに年季が入っていたのだ。叉、これで従来、「ラテン語で王の意」とだけ説明されてきた「REX」も意味を際立たせる。「A-REX」はひょっとすると「T-REX」(ティラノザウルス)に物凄く近い言葉ではないか。
つまり、鳥の知覚研究はスリリングなことに恐竜の知覚研究でもあるのだ。渡辺教授は豊富な実験例を示し、研究者たちの鳥脳へのアプローチを紹介してくれる。例えば伝書鳩の歴史から語り起こす「鳥脳のナヴィゲーション・システム」は興味深い。ゲーム中のサッカー選手も同じだが、動きながら(鳥の場合は飛びながら)、ときに反転したりして、空間認知するのは情報処理として大変なことである。
僕はセルジオ越後さんを助手席に乗せてクルマを運転したことがあり、道に迷って「角を曲がって曲がって曲がって曲がる(しかも90度ではない)」ような場面で、即座に「方向、こっちよ」と言われ仰天した経験がある。あぁ、反転しながらゴールの方向がわかってる習慣を持つ人なのだ、と感心した。あれはセルジオさんじゃなくて鳥でもよかったのか。
−後編に続く−