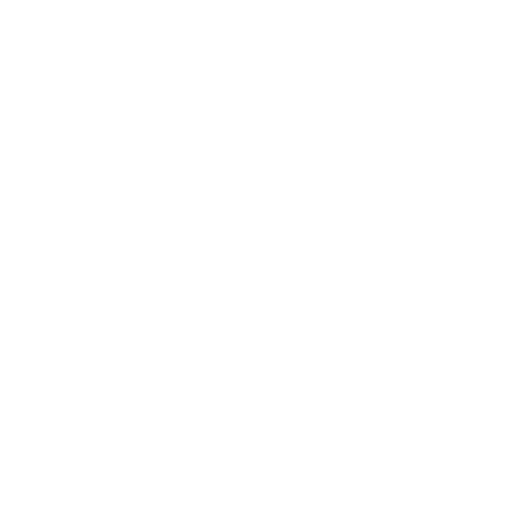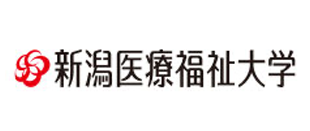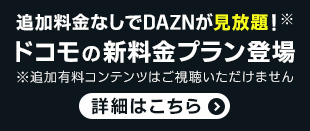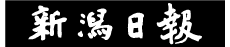【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第88回(後編)
2011/4/28
新潟は3月5日の開幕・福岡戦と完全に同じスタメン。緊張感が出てきた。やっぱりね、勝負事は実感のなかで戦わないと雰囲気が出ない。養老孟司さんのベストセラー『バカの壁』(新潮新書)に「脳内の一次方程式」という話が出てくるでしょう。人間の脳の出入力を「y=ax」という方程式モデルで説明した話。これ、今回の震災ほどわかりやすい状況はないですね。
だからxが入力、yが出力なんです。で、変数aが「現実の重み」。いや、だから震災後、ダルビッシュが「野球をやってる場合かと考えてしまう」とか言ったりしてたでしょ。みんなそういう気持ちになった。北尾トロさんは原稿が書けないとこぼしていた。報道に圧倒される。被災地の惨状、原発の危機を思うと、今、自分がやってることに現実感が持てない。変数aが限りなくゼロに近づく。
「サッカー選手が試合(形式)をやる」でも「北尾トロが原稿を書く」でも何でもいいですが、ベストの出力をするには自分に現実感が必要なんですね。現実感が喪失されると「俺、今、何やってるんだろう」と手につかない感じになる。人が会社を辞めちゃうようなときもそうじゃないですか。現実感が消えてどうでもよくなってしまう。反対に意欲満々で仕事をしてるときはaの値がめちゃ高い。当然、出力yもハイパフォーマンスになる。
だから「震災後、小説が読めなくなった」みたいな感覚はaがゼロになって、読んでも頭のなかを素通りしちゃうんですね。たぶんこれから僕らの敵はこいつです。サッカーを見て、現実に思えなくなる感覚。「今、ここに世界の中心があって、人生のすべてをぶつける価値がある」の希薄化。
簡単に振り返ると前半は新潟のリズム、後半は足が止まって富山にペースを握られた。これは本チャンじゃないからこんなもんかもしれない。前半のリズムが新潟の方向性だ。次週、リーグ戦が再開すれば「現実の重み」が選手の出力をアップさせるのは間違いない。「昨年のJ2下位チーム相手にスコアレスドロー」はあまり意味を持たない気がする。それより途中交代で入って早々と引っ込んだ菊地は大丈夫だろうか。震災中断の唯一、前向きな要素として菊地の復活を考えていたのでちょっと心配になった
。
試合後、セレモニーが行なわれ、両軍監督のスピーチが場内に響く。そして両チームいっしょに場内を一周する。サポーターは何度もエールの交換をした。新潟応援席は「復興までの長い道のり、富山も新潟も支え合ってがんばろう」の即席断幕を掲げる。ユーストの小窓のなかでも、その文字ははっきりわかった。
附記1、さぁ、再・開幕です。俺は自分の「変数a」を高めるために高速バス往復おさえましたよ。アルビレックス新潟のすべてをぶつけるべき試合です。世界の中心をスワンに作りましょう。
2、開幕節は前日(23日)、K’sスタジアムの水戸×徳島に行くつもりです。茨城県の被災状況も見て来ようと思います。
3、今週22日、東邦出版のチャリティー電子書籍『サッカーのチカラ 〜FOOTBALL WRITER’S AID〜』が発売になります。これは107人のライターが全員ギャラ返上という、すがすがしい企画です。お歴々のなかに僕も参加させていただいてる。版元の東邦出版も利益をとりません。クレジット決済等の必要経費を除いて全額、日本サッカー協会を通じて被災地へ寄付。PCやスマートフォンでも読めますよ。よかったら買ってください。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
コラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!
だからxが入力、yが出力なんです。で、変数aが「現実の重み」。いや、だから震災後、ダルビッシュが「野球をやってる場合かと考えてしまう」とか言ったりしてたでしょ。みんなそういう気持ちになった。北尾トロさんは原稿が書けないとこぼしていた。報道に圧倒される。被災地の惨状、原発の危機を思うと、今、自分がやってることに現実感が持てない。変数aが限りなくゼロに近づく。
「サッカー選手が試合(形式)をやる」でも「北尾トロが原稿を書く」でも何でもいいですが、ベストの出力をするには自分に現実感が必要なんですね。現実感が喪失されると「俺、今、何やってるんだろう」と手につかない感じになる。人が会社を辞めちゃうようなときもそうじゃないですか。現実感が消えてどうでもよくなってしまう。反対に意欲満々で仕事をしてるときはaの値がめちゃ高い。当然、出力yもハイパフォーマンスになる。
だから「震災後、小説が読めなくなった」みたいな感覚はaがゼロになって、読んでも頭のなかを素通りしちゃうんですね。たぶんこれから僕らの敵はこいつです。サッカーを見て、現実に思えなくなる感覚。「今、ここに世界の中心があって、人生のすべてをぶつける価値がある」の希薄化。
簡単に振り返ると前半は新潟のリズム、後半は足が止まって富山にペースを握られた。これは本チャンじゃないからこんなもんかもしれない。前半のリズムが新潟の方向性だ。次週、リーグ戦が再開すれば「現実の重み」が選手の出力をアップさせるのは間違いない。「昨年のJ2下位チーム相手にスコアレスドロー」はあまり意味を持たない気がする。それより途中交代で入って早々と引っ込んだ菊地は大丈夫だろうか。震災中断の唯一、前向きな要素として菊地の復活を考えていたのでちょっと心配になった
。
試合後、セレモニーが行なわれ、両軍監督のスピーチが場内に響く。そして両チームいっしょに場内を一周する。サポーターは何度もエールの交換をした。新潟応援席は「復興までの長い道のり、富山も新潟も支え合ってがんばろう」の即席断幕を掲げる。ユーストの小窓のなかでも、その文字ははっきりわかった。
附記1、さぁ、再・開幕です。俺は自分の「変数a」を高めるために高速バス往復おさえましたよ。アルビレックス新潟のすべてをぶつけるべき試合です。世界の中心をスワンに作りましょう。
2、開幕節は前日(23日)、K’sスタジアムの水戸×徳島に行くつもりです。茨城県の被災状況も見て来ようと思います。
3、今週22日、東邦出版のチャリティー電子書籍『サッカーのチカラ 〜FOOTBALL WRITER’S AID〜』が発売になります。これは107人のライターが全員ギャラ返上という、すがすがしい企画です。お歴々のなかに僕も参加させていただいてる。版元の東邦出版も利益をとりません。クレジット決済等の必要経費を除いて全額、日本サッカー協会を通じて被災地へ寄付。PCやスマートフォンでも読めますよ。よかったら買ってください。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。