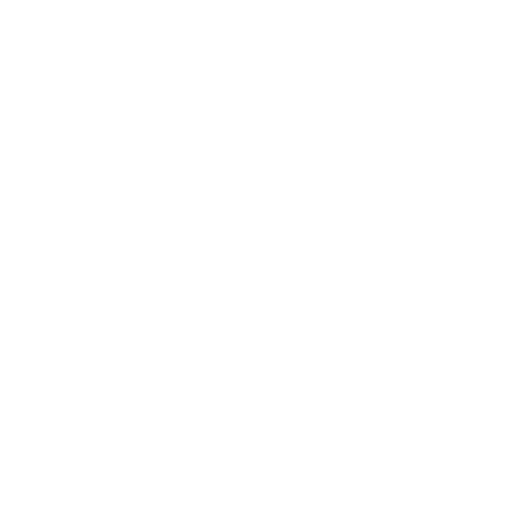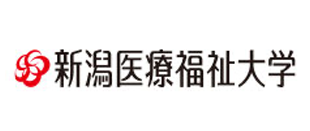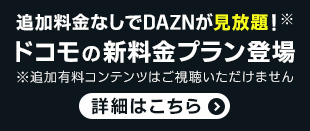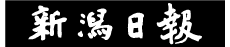【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第104回(前編)
2011/8/18
「アンデルセンとアンデルソンなどの話」
J1第20節、新潟×清水
だが、いきなりカンケイのない話から入る。過去、鳥の「鳥脳力」を扱ったり、わけわかんないことで定評のある当コラムの真骨頂といえるかもしれない。3連勝の話をストップして、アンデルセンについて語ろう。あ、これは誤記ではありませんよ、アンデルソンではなくアンデルセン。そんなバカなと思うでしょう。デンマークの国民的童話作家、H・C・アンデルセン。『人魚姫』や『あかい靴』、『マッチ売りの少女』等で読者も御存知の方だ。
僕はチームマスコットの「アルビくん」一家について関心を持続している。スタジアム周辺で見かけたときは(特にスワンちゃんに何らかの動きがないか)必ず注視するようにしているし、かなり接近して王冠の様式を確認したこともある。文献資料の検討も怠りなく、07年発行の『アーとルーとビィの冒険1/ビィのひみつ』も入手した。この年、チーム創設12年めのサポーターズイヤーを寿(ことほ)ぐように一家に可愛い三つ子が誕生したのだ。
実は「アルビくん」一家の物語にはアンデルセン童話『みにくいアヒルの子』が埋め込まれている。3番めの弟、ビィくんは何故かグレーの身体に生まれついたのだ。といって両親とはぐれてアヒルの群れで育ったわけではないから、ビィくん本人は大して気にしていない。ま、せいぜい何でかなぁと不思議に思ってたくらいのことだ。文献によるとビィくんは「ビッグスワンのどこかに住む占い師」(!)から重大な秘密を打ち明けられる。「ビィは アルビレックス新潟が優勝したとき まっしろな白鳥へと 生まれかわる!!」
『BS歴史館』(NHK-BSプレミアム)がアンデルセンをとり上げた回は当然、録画した。すると『みにくいアヒルの子』が書かれた時代背景が興味深いものだった。北欧デンマークはヨーロッパの辺境だ。
同時代、既にイギリスは産業革命期にあり、市民階級が勃興しているけれど、デンマークはその波から立ち遅れていた。スタジオゲストに入った鹿島茂氏(フランス文学)が強調していたのは、アンデルセンの作家としての「新しさ」だ。つまり、アンデルセンは近代的自我を予言していたというのだ。
『みにくいアヒルの子』は違和感の物語だ。フツーは「劣等感が晴れる物語」として読まれることが多い。が、灰色のみにくいアヒルの子が抱えているのは「自分は何者だろう」という問いだ。封建社会のなかで人はそんな問いに直面しないで済んだ。職人の子は職人であり、貴族の子は貴族だ。ところが貧しい職人の子として生まれたアンデルセンはいまだ封建社会の只中であったデンマークにいながら、その終わりを予感する。平たく言うと「何者かになれるかもしれない」と願う。
『みにくいアヒルの子』は時代より早く「何者かになれるかもしれない」と思った者の孤独が表出された物語だ。まだ何者でもない自分への違和感、劣等感が繰り返し語られる。これは後にカフカが『変身』で描いた主題とまっすぐつながるものだ。『変身』の主人公は時代がすすんで「何者かになれるかもしれない」が、芋虫に変身してしまった。
では、ビィくんのグレーの身体に話を戻そう。僕らは驚かねばならない。07年、おそらく世界のサッカー界でも稀な「チームが優勝しないことに違和感を表出するマスコット」が誕生していた。彼は地方クラブは所詮、地方クラブであるといった自足に対し、羽根色をもって異を唱える。たぶん新しい自我を体現した存在なのだろう。僕は彼の読書傾向が知りたい。もし控え室でフーコーでも読んでいるようならあらためて報告したい。
−後編に続く−
J1第20節、新潟×清水
だが、いきなりカンケイのない話から入る。過去、鳥の「鳥脳力」を扱ったり、わけわかんないことで定評のある当コラムの真骨頂といえるかもしれない。3連勝の話をストップして、アンデルセンについて語ろう。あ、これは誤記ではありませんよ、アンデルソンではなくアンデルセン。そんなバカなと思うでしょう。デンマークの国民的童話作家、H・C・アンデルセン。『人魚姫』や『あかい靴』、『マッチ売りの少女』等で読者も御存知の方だ。
僕はチームマスコットの「アルビくん」一家について関心を持続している。スタジアム周辺で見かけたときは(特にスワンちゃんに何らかの動きがないか)必ず注視するようにしているし、かなり接近して王冠の様式を確認したこともある。文献資料の検討も怠りなく、07年発行の『アーとルーとビィの冒険1/ビィのひみつ』も入手した。この年、チーム創設12年めのサポーターズイヤーを寿(ことほ)ぐように一家に可愛い三つ子が誕生したのだ。
実は「アルビくん」一家の物語にはアンデルセン童話『みにくいアヒルの子』が埋め込まれている。3番めの弟、ビィくんは何故かグレーの身体に生まれついたのだ。といって両親とはぐれてアヒルの群れで育ったわけではないから、ビィくん本人は大して気にしていない。ま、せいぜい何でかなぁと不思議に思ってたくらいのことだ。文献によるとビィくんは「ビッグスワンのどこかに住む占い師」(!)から重大な秘密を打ち明けられる。「ビィは アルビレックス新潟が優勝したとき まっしろな白鳥へと 生まれかわる!!」
『BS歴史館』(NHK-BSプレミアム)がアンデルセンをとり上げた回は当然、録画した。すると『みにくいアヒルの子』が書かれた時代背景が興味深いものだった。北欧デンマークはヨーロッパの辺境だ。
同時代、既にイギリスは産業革命期にあり、市民階級が勃興しているけれど、デンマークはその波から立ち遅れていた。スタジオゲストに入った鹿島茂氏(フランス文学)が強調していたのは、アンデルセンの作家としての「新しさ」だ。つまり、アンデルセンは近代的自我を予言していたというのだ。
『みにくいアヒルの子』は違和感の物語だ。フツーは「劣等感が晴れる物語」として読まれることが多い。が、灰色のみにくいアヒルの子が抱えているのは「自分は何者だろう」という問いだ。封建社会のなかで人はそんな問いに直面しないで済んだ。職人の子は職人であり、貴族の子は貴族だ。ところが貧しい職人の子として生まれたアンデルセンはいまだ封建社会の只中であったデンマークにいながら、その終わりを予感する。平たく言うと「何者かになれるかもしれない」と願う。
『みにくいアヒルの子』は時代より早く「何者かになれるかもしれない」と思った者の孤独が表出された物語だ。まだ何者でもない自分への違和感、劣等感が繰り返し語られる。これは後にカフカが『変身』で描いた主題とまっすぐつながるものだ。『変身』の主人公は時代がすすんで「何者かになれるかもしれない」が、芋虫に変身してしまった。
では、ビィくんのグレーの身体に話を戻そう。僕らは驚かねばならない。07年、おそらく世界のサッカー界でも稀な「チームが優勝しないことに違和感を表出するマスコット」が誕生していた。彼は地方クラブは所詮、地方クラブであるといった自足に対し、羽根色をもって異を唱える。たぶん新しい自我を体現した存在なのだろう。僕は彼の読書傾向が知りたい。もし控え室でフーコーでも読んでいるようならあらためて報告したい。
−後編に続く−