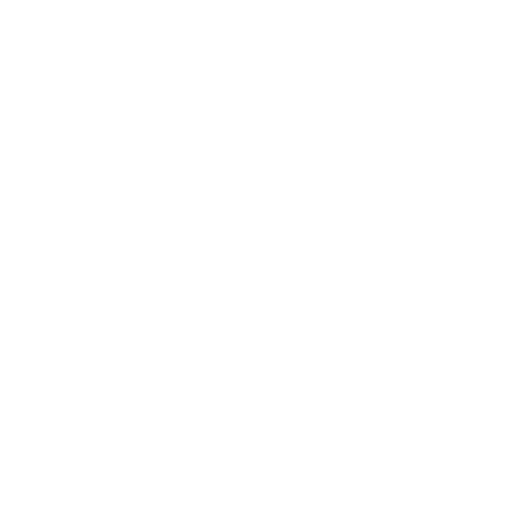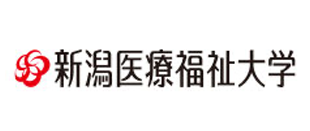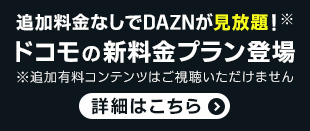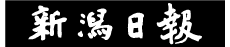【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第116回(前編)
2011/11/10
「芝生の匂い」
今週は木曜・柏戦の試合前、こうよく晴れた昼下がりに原稿がアップされる想定で書く。首都圏は25℃の夏日予報だ。祝日(文化の日)開催のゲームがモバアルの原稿アップの日と重なってしまった。まぁ、僕も新聞記者くらい頑張れば夕方、試合が終わってその夜のうちに記事がアップされるのは可能だろう。だけど、自分が大変な上にアルビ・栗原広報の負担がどえらいことになる。あくまで栗原さんの負担軽減策ですよ。栗原さんあっての散歩道だから。柏戦については次週へ送ります。
で、何書こうかなぁと考えたんだけど、『異端者たちのセンターサークル』(海江田哲朗・著、白夜書房・サッカー小僧新書)という新刊がすごく良かったのでその話にしたい。読者は海江田哲朗さんを御存知だろうか。気鋭のサッカーライターだ。定点観測的に見つめているのは東京ヴェルディ。たぶんヴェルディサポにとっての海江田さんは、アルビに置き換えると大中祐二さんと僕を足して2で割ったくらいの感じじゃないか。
試合会場で顔見知りになり、いつだったかの帰り道、お互い色川武大の愛読者ということで話が合った。なかなかサッカーライターで色川さんを読んでる人はいない。別名義の阿佐田哲也ですら読んでない。もう、金子達仁とかサイモン・クーパーとかサッカーまわりの狭いとこしか読んでないのだ。教養というとおこがましいから言わないけれど、圧倒的に読書量が足りない。だから皆、おんなじようなことばっかり書いている。僕は海江田さんを気に入った。何しろ(サッカーマガジンで書いてた、ひとの原稿つかまえて)「読むといつも面白くて不愉快でした」と言ってのけた奴だ。ライター魂が燃えている。
『異端者たちのセンターサークル』は海江田さんが避けて通れないところを書いた本だ。それはすなわち、「東京ヴェルディとは何か?」だ。日本初のクラブチーム・読売クラブが育んできたものは何か? その栄光はどうして失われたか? 消えたものは何か? 足りなかったものは何か? 失われず受け継がれるものは何か?
僕の世代は読売クラブの放った光芒を知っている。J発足前、世の中に実業団サッカーしかなかった頃に文字通り「異端」として彼らは存在した。だから他は古河だろうが三菱だろうがヤンマーだろうがサラリーマンのサッカー部なのだ。タテ社会だ。会社の意向で動く。そのなかにテクニック重視の自由なクラブチームが乗り込んでいった。語感としては「私立」だ。サッカー以外の何にも縛られない。
その本拠は通称「ランド」と呼ばれる、読売ランドの練習グラウンドだった。「ランド」には非・学校体育的なサッカー少年が集まるようになる。ブラジルの風を感じさせるトップチームと、それに憧れて集まる生意気な少年たち。海江田さんはその育成の系譜をタテ糸に物語を紡いでいく。
その発端に登場するひとりが今日の対戦相手・柏レイソルの強化本部・統括ディレクターを務める小見幸隆氏だ。小見さんはかつてヴェルディの監督さんを務めたから読者もイメージがあるだろう。今日も日立台のどこかにいる。読売クラブ創設の1969年、高校2年生の小見さんは芝生でサッカーがやれるのに惹かれて門を叩く。年会費1万円のほかは毎月500円の負担だ。そうして最初の「読売ユース」が形成されてゆく。高体連のサッカー部からは「クラブの奴」と呼ばれた。
そのうちに12歳の都並敏史、戸塚哲也がやって来てすっかりなついてしまう。チンチンにしても挑戦をやめない。何でも尋ねてくる。今、クラブチームもユース、ジュニアユース等の仕組みも当たり前になったが、そんな自由な気風のグラウンドはないだろう。その気風はずっと続いていく。サッカーは自分で考えるもの。工夫するもの。年齢とカンケイなく巧い奴がエラい。「ランド」はいつしか「首都圏で暮らすサッカー少年の一番星が目指す場所」になる。天才少年の系譜は戸塚哲也、菊原志郎、山口貴之、財前宣之と続く。
‐後編に続く‐
今週は木曜・柏戦の試合前、こうよく晴れた昼下がりに原稿がアップされる想定で書く。首都圏は25℃の夏日予報だ。祝日(文化の日)開催のゲームがモバアルの原稿アップの日と重なってしまった。まぁ、僕も新聞記者くらい頑張れば夕方、試合が終わってその夜のうちに記事がアップされるのは可能だろう。だけど、自分が大変な上にアルビ・栗原広報の負担がどえらいことになる。あくまで栗原さんの負担軽減策ですよ。栗原さんあっての散歩道だから。柏戦については次週へ送ります。
で、何書こうかなぁと考えたんだけど、『異端者たちのセンターサークル』(海江田哲朗・著、白夜書房・サッカー小僧新書)という新刊がすごく良かったのでその話にしたい。読者は海江田哲朗さんを御存知だろうか。気鋭のサッカーライターだ。定点観測的に見つめているのは東京ヴェルディ。たぶんヴェルディサポにとっての海江田さんは、アルビに置き換えると大中祐二さんと僕を足して2で割ったくらいの感じじゃないか。
試合会場で顔見知りになり、いつだったかの帰り道、お互い色川武大の愛読者ということで話が合った。なかなかサッカーライターで色川さんを読んでる人はいない。別名義の阿佐田哲也ですら読んでない。もう、金子達仁とかサイモン・クーパーとかサッカーまわりの狭いとこしか読んでないのだ。教養というとおこがましいから言わないけれど、圧倒的に読書量が足りない。だから皆、おんなじようなことばっかり書いている。僕は海江田さんを気に入った。何しろ(サッカーマガジンで書いてた、ひとの原稿つかまえて)「読むといつも面白くて不愉快でした」と言ってのけた奴だ。ライター魂が燃えている。
『異端者たちのセンターサークル』は海江田さんが避けて通れないところを書いた本だ。それはすなわち、「東京ヴェルディとは何か?」だ。日本初のクラブチーム・読売クラブが育んできたものは何か? その栄光はどうして失われたか? 消えたものは何か? 足りなかったものは何か? 失われず受け継がれるものは何か?
僕の世代は読売クラブの放った光芒を知っている。J発足前、世の中に実業団サッカーしかなかった頃に文字通り「異端」として彼らは存在した。だから他は古河だろうが三菱だろうがヤンマーだろうがサラリーマンのサッカー部なのだ。タテ社会だ。会社の意向で動く。そのなかにテクニック重視の自由なクラブチームが乗り込んでいった。語感としては「私立」だ。サッカー以外の何にも縛られない。
その本拠は通称「ランド」と呼ばれる、読売ランドの練習グラウンドだった。「ランド」には非・学校体育的なサッカー少年が集まるようになる。ブラジルの風を感じさせるトップチームと、それに憧れて集まる生意気な少年たち。海江田さんはその育成の系譜をタテ糸に物語を紡いでいく。
その発端に登場するひとりが今日の対戦相手・柏レイソルの強化本部・統括ディレクターを務める小見幸隆氏だ。小見さんはかつてヴェルディの監督さんを務めたから読者もイメージがあるだろう。今日も日立台のどこかにいる。読売クラブ創設の1969年、高校2年生の小見さんは芝生でサッカーがやれるのに惹かれて門を叩く。年会費1万円のほかは毎月500円の負担だ。そうして最初の「読売ユース」が形成されてゆく。高体連のサッカー部からは「クラブの奴」と呼ばれた。
そのうちに12歳の都並敏史、戸塚哲也がやって来てすっかりなついてしまう。チンチンにしても挑戦をやめない。何でも尋ねてくる。今、クラブチームもユース、ジュニアユース等の仕組みも当たり前になったが、そんな自由な気風のグラウンドはないだろう。その気風はずっと続いていく。サッカーは自分で考えるもの。工夫するもの。年齢とカンケイなく巧い奴がエラい。「ランド」はいつしか「首都圏で暮らすサッカー少年の一番星が目指す場所」になる。天才少年の系譜は戸塚哲也、菊原志郎、山口貴之、財前宣之と続く。
‐後編に続く‐