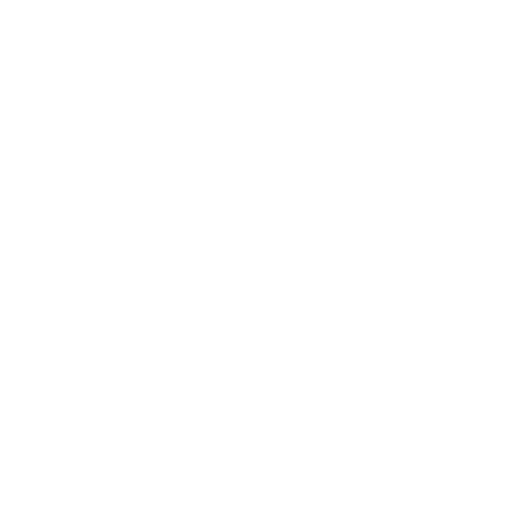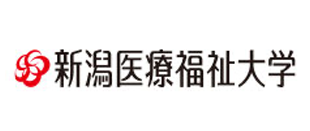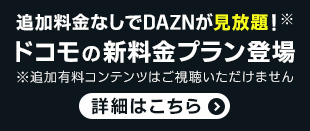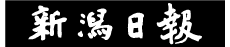【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第134回
2012/6/14
「この空の花」
試合のない土曜日、有楽町スバル座に『この空の花ー長岡花火物語』(大林宣彦監督)を見に行った。今週は映画コラムにさせていただく。聖籠の様子は日本一のアルビ記者・大中祐二さんに任せた。『この空の花』は新潟先行ロードショーだから、もう御覧になった読者もおられるだろう。抜群の出来だ。ちなみに僕が今年見た映画では『ヒミズ』(園子温監督)と1、2を争う。まぁ、『ヒミズ』は暴力シーンが多くて好き嫌いが分かれると思う(でも僕はラスト号泣)ので一本、映画を挙げろと言われたら迷いなく『この空の花』だ。
『ヒミズ』と『この空の花』には共通点があって、2011年に撮影されたことが映画に織り込まれているところだ。孤立無援の青春と純愛を描いた『ヒミズ』は、その孤立無援っぷりを際立たせるように東日本大震災の被災地ロケを断行している。劇中は原発事故のニュースを効果的に使って「先行する世代の無責任さ」を印象づける。『この空の花』には被災地自体は登場しない代わり、大震災が新潟県にどう反響し、どう意味づけられていったかを正確に描いている。南相馬から避難してきた高校生が登場するし、中越地震の記憶や、長岡花火を自粛すべきか話し合うシーンも描かれる。それから夏の大雨だな。たぶんほとんどの日本人が震災と原発で忘れてしまっている水害を入れ込んでる。
とんでもない情報量の映画だ。意図したところはたぶん「土地のタテ糸を通す」こと。長岡にまつわる人々の記憶が丹念に語られていく。僕は大林さんの実験的手法に慣れてる上、当連載を通じて新潟県に予備知識も持っている。一般の映画ファンは大丈夫かなぁと心配になった。戊辰戦争・河井継之助、長岡空襲・山本五十六、投下された模擬原子爆弾、幻の新潟市原爆投下計画…。早口の台詞まわし、矢継ぎ早のスーパーが長岡という土地のディテールを拾っていく。
物語は松雪泰子扮する地方紙記者・玲子がかつての恋人から手紙をもらうところから始まる。かつての恋人(高嶋政宏)は山古志に住んで、長岡の高校教師を務めている。手紙は長岡への誘いだった。もうすぐ上演する予定の高校演劇を見に来てほしい。その上で長岡花火を見てほしい。玲子は長岡の地を踏む。土地の記憶に向き合っていく。それは生者と死者の声がハーモニーとなって溶け合う「ワンダーランド」だった。
大林演出の凄みは生者と死者を区別しない点だ。映画のヒロイン・花(新人・猪俣南)は長岡空襲で死んだ赤ん坊だった。が、大林監督は死者に肉体を与え、高校演劇の舞台に立たせる。死者は生者と同じように観客へ語りかける。それは幽霊ではないのだ。同じ長岡の人なのだ。故郷はそういう風にできている。沢山の死者がつないだものが現在を成立させている。
基調を成すテーマは「想像力」だ。想像力を失くして石ころのような心になってはいけない。想像力を働かせれば見えないものが見えてくる。それは死者の声でもある。災厄の光景でもある。東日本大震災の被災者の姿でもある。自分がどこに生まれどこへ向かうのか、どうして故郷の風景に心ひきつけられるのか、それはかつて生きた誰かと同じことなのか、の答えでもある。
長岡花火は圧倒的に美しい。が、美しいだけじゃ足りない。足りないものは何かというと「想像力」だ。そこに込められた意味。託されたもの。夜空を見上げる死者たちのまなざし。故郷を思う生者たちの暮らし。それがあって美しいのだと『この空の花』は伝える。
以前、あるサポーターが「アルビは花火のようなクラブになるといい」という話を聞かせてくれたことがある。花火というと一瞬輝いて、やがて消えてゆくといったイメージがあって「?」と思う。その人が言ったのは大輪の打ち上げ花火だ。それは花火会場にいる人は大層盛り上がる。美しさに息をのむ。家族連れは子供の顔が輝くのを見てニッコリする。花火会場はお祭りだ。けれど遠くで見ている人もいる。大輪の花火は遠くで見ている人のことも照らす。その人を少し幸福にする。新聞を開いて「へぇ、アルビ頑張ったなぁ」という人を忘れちゃいけないと言うのだった。そういう人の心にもちゃんと届いていることを忘れちゃいけないと言うのだった。
有楽町スバル座からの帰り道、僕は100年後のアルビレックス新潟を想った。「Jリーグ百年構想」とは別の話だ。何なら200年後だっていい。今、スタジアムにいる人は皆、亡くなっている。アルビはどうだろう。その100年か200年の間に何度かJ2へ落ちただろうか。2012年はどうだったかも教えてもらいたい。そんな先にもクラブは存続してるのか。世界へ飛び立つスターは何人出た?
100年200年が経ち、皆、いなくなった後で、例えば古町に所在するアルビレックススタジアムからコールが聴こえる。チームは序盤に失点を食らったのか。励ます調子だ。アルービレックス! あなたはもういない。が、あなたはどこかにいる。アルービレックス! そのコールと溶け合っている。
できたら誰か100年200年前も必死だったんだと「想像力」を働かせてほしい。でないと何もかも消えてなくなってしまうようだ。アルービレックス! 消えてなくなるもんか。序盤の失点にうろたえるな。自分らのリズムをとり戻せ。今日は勝つぞ。アルービレックス!
歴史のタテ糸というのは、たぶんそんな感じなのだと思う。時の重みに耐える強度は、そのときそのときの切実な「現在」が作ってゆく。切実な「現在」は発火し、遠くで見れば花火のように輝く。ぼんやり見ればただ美しいだけだろう。僕らは悔いのないよう「現在」を生きるしかない。
附記1、つまり、アルビサポ必見の映画ですね。2時間40分、圧倒されます。僕は6月2日に見に行ったけど、考えたら前日行けば「映画サービスデー」だった。でも、ぜんぜん1800円惜しくないな。
2、大林宣彦監督は昔、雑誌の対談でご一緒したことがあります。そのときも『北京的西瓜』というドキュメンタリー手法を大胆に取り入れた実験作を公開するタイミングだった。
3、ナビスコ連戦は上野監督代行のまま行くんですね。新監督を迎えるなら早くチームに合流してもらったほうがいいんだけどなぁ。これは上野さんで勝負かけるということか、それとも交渉が難航してるということなのか。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!

試合のない土曜日、有楽町スバル座に『この空の花ー長岡花火物語』(大林宣彦監督)を見に行った。今週は映画コラムにさせていただく。聖籠の様子は日本一のアルビ記者・大中祐二さんに任せた。『この空の花』は新潟先行ロードショーだから、もう御覧になった読者もおられるだろう。抜群の出来だ。ちなみに僕が今年見た映画では『ヒミズ』(園子温監督)と1、2を争う。まぁ、『ヒミズ』は暴力シーンが多くて好き嫌いが分かれると思う(でも僕はラスト号泣)ので一本、映画を挙げろと言われたら迷いなく『この空の花』だ。
『ヒミズ』と『この空の花』には共通点があって、2011年に撮影されたことが映画に織り込まれているところだ。孤立無援の青春と純愛を描いた『ヒミズ』は、その孤立無援っぷりを際立たせるように東日本大震災の被災地ロケを断行している。劇中は原発事故のニュースを効果的に使って「先行する世代の無責任さ」を印象づける。『この空の花』には被災地自体は登場しない代わり、大震災が新潟県にどう反響し、どう意味づけられていったかを正確に描いている。南相馬から避難してきた高校生が登場するし、中越地震の記憶や、長岡花火を自粛すべきか話し合うシーンも描かれる。それから夏の大雨だな。たぶんほとんどの日本人が震災と原発で忘れてしまっている水害を入れ込んでる。
とんでもない情報量の映画だ。意図したところはたぶん「土地のタテ糸を通す」こと。長岡にまつわる人々の記憶が丹念に語られていく。僕は大林さんの実験的手法に慣れてる上、当連載を通じて新潟県に予備知識も持っている。一般の映画ファンは大丈夫かなぁと心配になった。戊辰戦争・河井継之助、長岡空襲・山本五十六、投下された模擬原子爆弾、幻の新潟市原爆投下計画…。早口の台詞まわし、矢継ぎ早のスーパーが長岡という土地のディテールを拾っていく。
物語は松雪泰子扮する地方紙記者・玲子がかつての恋人から手紙をもらうところから始まる。かつての恋人(高嶋政宏)は山古志に住んで、長岡の高校教師を務めている。手紙は長岡への誘いだった。もうすぐ上演する予定の高校演劇を見に来てほしい。その上で長岡花火を見てほしい。玲子は長岡の地を踏む。土地の記憶に向き合っていく。それは生者と死者の声がハーモニーとなって溶け合う「ワンダーランド」だった。
大林演出の凄みは生者と死者を区別しない点だ。映画のヒロイン・花(新人・猪俣南)は長岡空襲で死んだ赤ん坊だった。が、大林監督は死者に肉体を与え、高校演劇の舞台に立たせる。死者は生者と同じように観客へ語りかける。それは幽霊ではないのだ。同じ長岡の人なのだ。故郷はそういう風にできている。沢山の死者がつないだものが現在を成立させている。
基調を成すテーマは「想像力」だ。想像力を失くして石ころのような心になってはいけない。想像力を働かせれば見えないものが見えてくる。それは死者の声でもある。災厄の光景でもある。東日本大震災の被災者の姿でもある。自分がどこに生まれどこへ向かうのか、どうして故郷の風景に心ひきつけられるのか、それはかつて生きた誰かと同じことなのか、の答えでもある。
長岡花火は圧倒的に美しい。が、美しいだけじゃ足りない。足りないものは何かというと「想像力」だ。そこに込められた意味。託されたもの。夜空を見上げる死者たちのまなざし。故郷を思う生者たちの暮らし。それがあって美しいのだと『この空の花』は伝える。
以前、あるサポーターが「アルビは花火のようなクラブになるといい」という話を聞かせてくれたことがある。花火というと一瞬輝いて、やがて消えてゆくといったイメージがあって「?」と思う。その人が言ったのは大輪の打ち上げ花火だ。それは花火会場にいる人は大層盛り上がる。美しさに息をのむ。家族連れは子供の顔が輝くのを見てニッコリする。花火会場はお祭りだ。けれど遠くで見ている人もいる。大輪の花火は遠くで見ている人のことも照らす。その人を少し幸福にする。新聞を開いて「へぇ、アルビ頑張ったなぁ」という人を忘れちゃいけないと言うのだった。そういう人の心にもちゃんと届いていることを忘れちゃいけないと言うのだった。
有楽町スバル座からの帰り道、僕は100年後のアルビレックス新潟を想った。「Jリーグ百年構想」とは別の話だ。何なら200年後だっていい。今、スタジアムにいる人は皆、亡くなっている。アルビはどうだろう。その100年か200年の間に何度かJ2へ落ちただろうか。2012年はどうだったかも教えてもらいたい。そんな先にもクラブは存続してるのか。世界へ飛び立つスターは何人出た?
100年200年が経ち、皆、いなくなった後で、例えば古町に所在するアルビレックススタジアムからコールが聴こえる。チームは序盤に失点を食らったのか。励ます調子だ。アルービレックス! あなたはもういない。が、あなたはどこかにいる。アルービレックス! そのコールと溶け合っている。
できたら誰か100年200年前も必死だったんだと「想像力」を働かせてほしい。でないと何もかも消えてなくなってしまうようだ。アルービレックス! 消えてなくなるもんか。序盤の失点にうろたえるな。自分らのリズムをとり戻せ。今日は勝つぞ。アルービレックス!
歴史のタテ糸というのは、たぶんそんな感じなのだと思う。時の重みに耐える強度は、そのときそのときの切実な「現在」が作ってゆく。切実な「現在」は発火し、遠くで見れば花火のように輝く。ぼんやり見ればただ美しいだけだろう。僕らは悔いのないよう「現在」を生きるしかない。
附記1、つまり、アルビサポ必見の映画ですね。2時間40分、圧倒されます。僕は6月2日に見に行ったけど、考えたら前日行けば「映画サービスデー」だった。でも、ぜんぜん1800円惜しくないな。
2、大林宣彦監督は昔、雑誌の対談でご一緒したことがあります。そのときも『北京的西瓜』というドキュメンタリー手法を大胆に取り入れた実験作を公開するタイミングだった。
3、ナビスコ連戦は上野監督代行のまま行くんですね。新監督を迎えるなら早くチームに合流してもらったほうがいいんだけどなぁ。これは上野さんで勝負かけるということか、それとも交渉が難航してるということなのか。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!