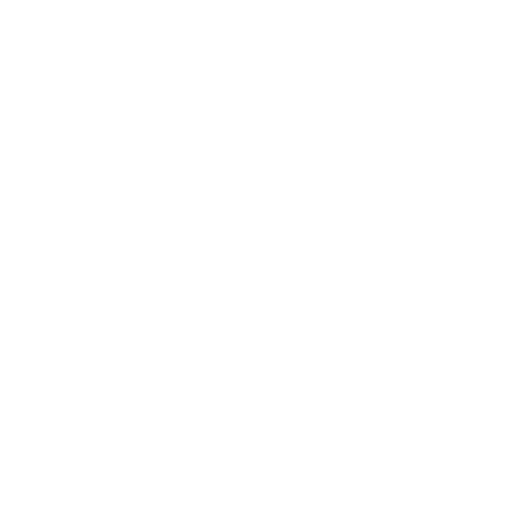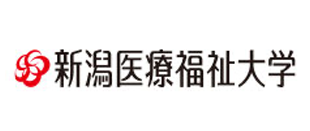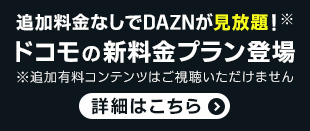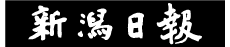【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第137回
2012/7/5
「トンボ返り」
J1第15節、神戸×新潟。
昼ぐらいの新幹線なので余裕だと思ってたら、朝方、母から電話が入り、父が倒れたという。で、あわててるから「延命治療について話し合い」とか物騒なことを口走り、一体何があったのか要領を得ない。これは取材キャンセルかと思いました。で、とにかく落ち着け落ち着け、アルビの課題も落ち着きだと柳下さん言ってるんだから(ここはウソ)と言い聞かせ、事態がわかってくる。父は糖尿の持病があるんだが、どうも低血糖で道端に倒れたらしい。血糖値30くらいまで行ってたというからかなり危険な状態だった。
糖尿病というのは血糖値が高い病気で、一見、低血糖は矛盾するようなんだけど、インシュリンが効きすぎたりして低血糖状態になることがあるようだ。コントロールが難しい。父は先週、風邪をひいて医者から薬を処方されていた。で、それが結構な量出ていて、胃が荒れて食欲がなかったらしい。金曜日、風邪の症状がおさまったと自己判断、朝食後、糖尿の薬を再開したのだが、前日まで食事をとってないから血糖値が低いところへ下げる薬を飲んでしまった。
道端に倒れた。幸い頭は打たずにすんだ。貧血に近い症状だ。意識はあったので通行人に名前と電話番号を言う。で、救急車で地域の病院へ運ばれる。現在はブドウ糖の点滴で血糖値が戻っている。ま、当直の先生が「低血糖は急変があるから、万一のために延命治療について相談しておいて」と言ったようだ。とりあえず病院の管理下で状態は安定している。僕は神戸行きを決めた。念のため、何かあったら知らせろと妹にメールする。東海道新幹線は本数が多いからいつでもとって返すつもりだ。
で、情けない話だけど、やっぱり試合を見る集中力は低かったと思う。切り替えて目の前のプレーに意をこらすんだけど、感じとる力が弱い。僕はきれいごとでなく、柳下アルビの第2戦は見る値打ちがあると考えた。最初の1、2週がとても大事だ。こういうのは計画的にステップアップするような部分とは別に、こう、乾いたスポンジが水を吸うように浸透していく部分があるんじゃないか。
新潟と神戸はチーム状況が似ている。神戸も結果を求めて、実績のある西野朗氏をシーズン途中で監督に迎えている。前節は小川慶治朗のハットトリックでようやく西野体制の初勝利をモノにした。ここから上へ行けるのか。足踏みが続くのか。「直接対決」だ。現在の順位はともかくとして、ここで連勝を得れば両チームとも風景がガラッと変わる。世間が思うよりずっとビッグゲームなのだ。
試合。前半がきつかった。僕は自分が集中できてないのか、内容が散漫なのかずっと考えていた。まぁ、その両方だろう。新潟も新潟だけど神戸も神戸だ。で、えのきどもえのきどなのだ。意図や根拠が薄い。西野ヴィッセルのほうがチーム作りは進んでいるんだろうけど、展開の本筋ができてない。新潟は意識づけの段階だ。柳下監督がピッチサイドに立って忙しく指示を飛ばす。見る側としてはチームの戦術意図をトレースして、自分なりのイメージを重ねていく感じになるんだけど、トレースが一手二手で終わってしまう。
トレースする感じは「こう→こう→こう→こう→おお、こうか!→うわっ、こうしたかったけど失敗したんだな!」みたいなニュアンスだ。それが「こう→こう?」ぐらいで寸断されてしまう。か、「こう→こう→こう?」だとして、それがチームに共有されたイメージではなく、2人ぐらいでやってることだったり。柳下監督も大変だ。といって西野ヴィッセルも大差ない。
両軍とも課題は攻撃を作るときの芯の部分だろうと思う。いったん縦におさめて、そこから配球するような芯。ちょっと前のサッカーならその役割はトップ下が担っていた。今はボランチが担うことが多い。ちなみに新潟はここを省略して、前線の選手にいきなりぶつけるか、もしくは相手DFのウラを狙うようなサッカーを続けてきた。
マルシオ・リシャルデスがいた頃は、構造としてはトップ下が芯になる形だった。が、マルシオほどのキープ力を持ってしてもプレッシャーがきびしい。だから1列下げてボランチを芯にするほうが主流になるのだが、新潟もマルシオをトップ下にする「ちょっと前のサッカー」を見切って、ショートカウンター(前で奪い、すぐ攻撃に結びつける)に活路を見出していた。マルシオ移籍後はこれという「組み立ての芯」は作っていない。
柳下さんはもちろん、西野さんも「時間がかかる」と痛感したと思う。新潟の場合はボランチを芯に据えた後、次は例えばサイドのムーヴの意識づけ、前線のポジション、人数のかけ方、スピードアップのイメージを作っていくような感じになる。この試合のひとつの関心事、チーム改造の進捗状況はこのぐらいのところだ。やることがいっぱいある。そうカンタンにことは運ばない。
が、柳下さんは後半、戦術眼の確かなところを見せた。脚を痛めた田中亜土夢に代えてアラン・ミネイロを投入、相手DFとボランチの間のスペースで仕事をさせる。僕は選手の特徴がかなり手の内に入ったなぁと思う。アラン・ミネイロは物足りない印象の選手だったが、使い方で生きるんだなと勉強になった。しかし、アラン・ミネイロが仕事を始めて、あぁ、あそこスペースできてたんだと気づいたくらいだから僕の観察力もアテにならない。
勝負は運の要素で決した。後半13分、交代で入った森岡が遠めから打ったシュートがGK・東口をかすめゴールイン。最初、何が起きたかわからなかった。どう見ても東口に止められないシュートじゃない。後で確認したらリバウンドを狙ってゴール前へ詰めた小川の太腿に当たり、コースが変わっていた。一方、新潟最大の決定機は後半32分、こちらも交代出場の平井将生が抜けて、相手GKと1対1になった場面。シュートはファーのポストを叩き、そのリバウンドの神戸・田中のクリアがクロスバーを叩くツキのなさ。平井は敵将・西野朗の前で仕事がしたかっただろう。
大差ないのである。それでも神戸は連勝、勝ち点3を得た。新潟は「ひと試合分の反省」しか得るところがなかった。試合後の会見で柳下さんは「前へ運ぶ部分」が足りないと強調する。次のステップはそこだ。目指すのは得点のとれるチーム、連勝できるチーム。この負けは次に生かせばいい。僕らには「得られたかもしれない勝ち点1」なんてものに拘泥しているヒマはない。
帰京は夜行バスだった。病院へ駆けつけると父は点滴をつけて「大変だったな」と言う。大変だったのはあんたでしょうと思うが、とにかく無事でホッとした。それから父はぼそぼそと昏倒したときの不思議な感覚(身体がだるくなって、足が前へ進まなくなり、景色が遠メガネを逆さに見たように遠のく)について語る。声に普段の張りはないんだけど、お前もいっぺんやってみたらいい、あれは不思議だぞくらいの調子だった。
附記1、ナビスコ大宮戦! すごいね0対3からラスト30分で4点とって逆転勝ち! アルビ史上、最も派手な逆転劇ですよ。しかもロスタイムの決勝弾は鈴木武蔵ですよ。柳下アルビ、♪地元じゃ負け知らず~じゃないですか。
2、これは勇気をもたらす勝利ですね。課題がいくらあっても乗り越えていける。チームは正しい方向へ進んでいる。得点はとれる。最後まであきらめちゃいけない。又、ひと試合分、学んだわけです。
3、今回は冒頭から私事が長くてすいませんでした。てか、そういう文章多い気もしますが。まぁ、率直が僕のトリエなんでこういうことになりました。僕は神戸戦ずっと覚えてると思うな。平井の惜しいシュートも、地下鉄海岸線の「平清盛」のアナウンスも。まぁ、こうしてアルビと自分史が重なっていくんだと思います。あのとき親父が倒れたのに見に行ったんだよなぁとか。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!

J1第15節、神戸×新潟。
昼ぐらいの新幹線なので余裕だと思ってたら、朝方、母から電話が入り、父が倒れたという。で、あわててるから「延命治療について話し合い」とか物騒なことを口走り、一体何があったのか要領を得ない。これは取材キャンセルかと思いました。で、とにかく落ち着け落ち着け、アルビの課題も落ち着きだと柳下さん言ってるんだから(ここはウソ)と言い聞かせ、事態がわかってくる。父は糖尿の持病があるんだが、どうも低血糖で道端に倒れたらしい。血糖値30くらいまで行ってたというからかなり危険な状態だった。
糖尿病というのは血糖値が高い病気で、一見、低血糖は矛盾するようなんだけど、インシュリンが効きすぎたりして低血糖状態になることがあるようだ。コントロールが難しい。父は先週、風邪をひいて医者から薬を処方されていた。で、それが結構な量出ていて、胃が荒れて食欲がなかったらしい。金曜日、風邪の症状がおさまったと自己判断、朝食後、糖尿の薬を再開したのだが、前日まで食事をとってないから血糖値が低いところへ下げる薬を飲んでしまった。
道端に倒れた。幸い頭は打たずにすんだ。貧血に近い症状だ。意識はあったので通行人に名前と電話番号を言う。で、救急車で地域の病院へ運ばれる。現在はブドウ糖の点滴で血糖値が戻っている。ま、当直の先生が「低血糖は急変があるから、万一のために延命治療について相談しておいて」と言ったようだ。とりあえず病院の管理下で状態は安定している。僕は神戸行きを決めた。念のため、何かあったら知らせろと妹にメールする。東海道新幹線は本数が多いからいつでもとって返すつもりだ。
で、情けない話だけど、やっぱり試合を見る集中力は低かったと思う。切り替えて目の前のプレーに意をこらすんだけど、感じとる力が弱い。僕はきれいごとでなく、柳下アルビの第2戦は見る値打ちがあると考えた。最初の1、2週がとても大事だ。こういうのは計画的にステップアップするような部分とは別に、こう、乾いたスポンジが水を吸うように浸透していく部分があるんじゃないか。
新潟と神戸はチーム状況が似ている。神戸も結果を求めて、実績のある西野朗氏をシーズン途中で監督に迎えている。前節は小川慶治朗のハットトリックでようやく西野体制の初勝利をモノにした。ここから上へ行けるのか。足踏みが続くのか。「直接対決」だ。現在の順位はともかくとして、ここで連勝を得れば両チームとも風景がガラッと変わる。世間が思うよりずっとビッグゲームなのだ。
試合。前半がきつかった。僕は自分が集中できてないのか、内容が散漫なのかずっと考えていた。まぁ、その両方だろう。新潟も新潟だけど神戸も神戸だ。で、えのきどもえのきどなのだ。意図や根拠が薄い。西野ヴィッセルのほうがチーム作りは進んでいるんだろうけど、展開の本筋ができてない。新潟は意識づけの段階だ。柳下監督がピッチサイドに立って忙しく指示を飛ばす。見る側としてはチームの戦術意図をトレースして、自分なりのイメージを重ねていく感じになるんだけど、トレースが一手二手で終わってしまう。
トレースする感じは「こう→こう→こう→こう→おお、こうか!→うわっ、こうしたかったけど失敗したんだな!」みたいなニュアンスだ。それが「こう→こう?」ぐらいで寸断されてしまう。か、「こう→こう→こう?」だとして、それがチームに共有されたイメージではなく、2人ぐらいでやってることだったり。柳下監督も大変だ。といって西野ヴィッセルも大差ない。
両軍とも課題は攻撃を作るときの芯の部分だろうと思う。いったん縦におさめて、そこから配球するような芯。ちょっと前のサッカーならその役割はトップ下が担っていた。今はボランチが担うことが多い。ちなみに新潟はここを省略して、前線の選手にいきなりぶつけるか、もしくは相手DFのウラを狙うようなサッカーを続けてきた。
マルシオ・リシャルデスがいた頃は、構造としてはトップ下が芯になる形だった。が、マルシオほどのキープ力を持ってしてもプレッシャーがきびしい。だから1列下げてボランチを芯にするほうが主流になるのだが、新潟もマルシオをトップ下にする「ちょっと前のサッカー」を見切って、ショートカウンター(前で奪い、すぐ攻撃に結びつける)に活路を見出していた。マルシオ移籍後はこれという「組み立ての芯」は作っていない。
柳下さんはもちろん、西野さんも「時間がかかる」と痛感したと思う。新潟の場合はボランチを芯に据えた後、次は例えばサイドのムーヴの意識づけ、前線のポジション、人数のかけ方、スピードアップのイメージを作っていくような感じになる。この試合のひとつの関心事、チーム改造の進捗状況はこのぐらいのところだ。やることがいっぱいある。そうカンタンにことは運ばない。
が、柳下さんは後半、戦術眼の確かなところを見せた。脚を痛めた田中亜土夢に代えてアラン・ミネイロを投入、相手DFとボランチの間のスペースで仕事をさせる。僕は選手の特徴がかなり手の内に入ったなぁと思う。アラン・ミネイロは物足りない印象の選手だったが、使い方で生きるんだなと勉強になった。しかし、アラン・ミネイロが仕事を始めて、あぁ、あそこスペースできてたんだと気づいたくらいだから僕の観察力もアテにならない。
勝負は運の要素で決した。後半13分、交代で入った森岡が遠めから打ったシュートがGK・東口をかすめゴールイン。最初、何が起きたかわからなかった。どう見ても東口に止められないシュートじゃない。後で確認したらリバウンドを狙ってゴール前へ詰めた小川の太腿に当たり、コースが変わっていた。一方、新潟最大の決定機は後半32分、こちらも交代出場の平井将生が抜けて、相手GKと1対1になった場面。シュートはファーのポストを叩き、そのリバウンドの神戸・田中のクリアがクロスバーを叩くツキのなさ。平井は敵将・西野朗の前で仕事がしたかっただろう。
大差ないのである。それでも神戸は連勝、勝ち点3を得た。新潟は「ひと試合分の反省」しか得るところがなかった。試合後の会見で柳下さんは「前へ運ぶ部分」が足りないと強調する。次のステップはそこだ。目指すのは得点のとれるチーム、連勝できるチーム。この負けは次に生かせばいい。僕らには「得られたかもしれない勝ち点1」なんてものに拘泥しているヒマはない。
帰京は夜行バスだった。病院へ駆けつけると父は点滴をつけて「大変だったな」と言う。大変だったのはあんたでしょうと思うが、とにかく無事でホッとした。それから父はぼそぼそと昏倒したときの不思議な感覚(身体がだるくなって、足が前へ進まなくなり、景色が遠メガネを逆さに見たように遠のく)について語る。声に普段の張りはないんだけど、お前もいっぺんやってみたらいい、あれは不思議だぞくらいの調子だった。
附記1、ナビスコ大宮戦! すごいね0対3からラスト30分で4点とって逆転勝ち! アルビ史上、最も派手な逆転劇ですよ。しかもロスタイムの決勝弾は鈴木武蔵ですよ。柳下アルビ、♪地元じゃ負け知らず~じゃないですか。
2、これは勇気をもたらす勝利ですね。課題がいくらあっても乗り越えていける。チームは正しい方向へ進んでいる。得点はとれる。最後まであきらめちゃいけない。又、ひと試合分、学んだわけです。
3、今回は冒頭から私事が長くてすいませんでした。てか、そういう文章多い気もしますが。まぁ、率直が僕のトリエなんでこういうことになりました。僕は神戸戦ずっと覚えてると思うな。平井の惜しいシュートも、地下鉄海岸線の「平清盛」のアナウンスも。まぁ、こうしてアルビと自分史が重なっていくんだと思います。あのとき親父が倒れたのに見に行ったんだよなぁとか。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!