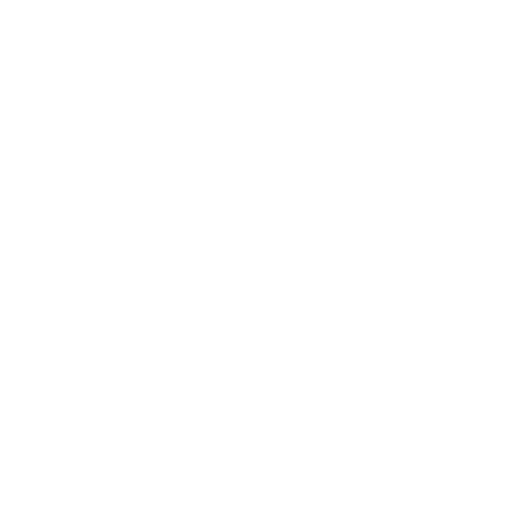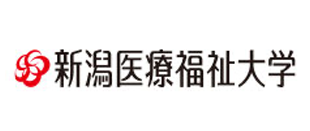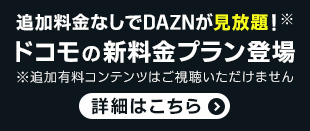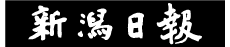【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 特別編「柳下正明監督 11,000字インタビュー」(前編)
2013/3/7
えのきど「おつかれさまです、よろしくお願いいたします」
柳下「ハイ、よろしくお願いします」
えのきど「今日は伺いたいことはいくつかあるんですけれど、主眼としては柳下さんがどんな方かっていうことも、このインタビューの中で具体的にしたいと思っております」
柳下「(笑)」
えのきど「そこはかねてから大変関心がありまして(笑)。昨シーズンでのご様子とか拝見してきて、面白い方だな、話をお聞きしたいなと思っていたんです」
柳下「お願いします」
えのきど「まずはチームのことを。アルビレックスはキャンプ相当長いですよね?キャンプのまま開幕へっていう流れは雪国のチームはしょうがないんですけど。今までのご経験の中ではどうなんですか?」
柳下「そうですね。札幌、山形、仙台、新潟…北のチームはしょうがないですね。まあ、僕も札幌で3年間やってきましたから」
えのきど「そうですね、札幌がありますね」
柳下「札幌の1年目でしたが、同じところでのキャンプが相当長かったんです。グアム、鹿児島・指宿。同じところで長いと、どうしてもダレるんです。ちょっとキツイなと感じてた。ですので、2年目からはひとつの場所を11日間にして、休みを入れずにそのまま一気にぶっ通しで行く。2週間を超えるとどうしても途中で丸一日休まないといけない。いままでの経験で、ひとつの場所で休みを入れずに10日間か11日間のキャンプを集中してやる。場所を変えるんで、移動日も兼ねた休みをあげて、というくり返しを3回くらい、リフレッシュと集中を繰り返す。今回、このやり方で新潟もうまくいってると感じています」
えのきど「選手は開幕までの毎日、だんだんとギューっと集中していく感じですか?」
柳下「それがやっぱり難しいんですよね。外に出続けてるから、そこが難しいでしょうね」
えのきど「選手も、移籍した選手なんか特に勝手が違って難しいかもしれませんね」
柳下「そうですね。他のチームは基本的には長くて2週間のキャンプで一度戻りますから。そこですね」
えのきど「非常事態を引き受ける形で入って来た去年と、シーズンの最初からやってる今年とは違いますか?」
柳下「途中からやったのは去年が初めてでしたけれど、自分のイメージするサッカースタイル、私自身の体のなかに入っているサッカーと新潟がやっていたサッカーはそう離れてなかった。それはやりやすかったですよ。全く違うものを私が求めるとなると、それは相当に時間がかかると思ってましたが、私の体のなかに入ってる部分と同じものがかなりあったんで、そんなに難しいことではありませんでした」
えのきど「僕が思ったのはですね、柳下さんが持ってらっしゃるサイド攻撃とかのイメージを考えると、カウンターサッカーをやらなきゃならないのは不本意だったりするんじゃないかなって」
柳下「それはありました。でも、あの状況だと仕方がない」
えのきど「仕方がない?」
柳下「ただ、どこのチームもカウンターは存在していて、どこのチームも点をたくさん取っているのはカウンターからなんですよ、実は。ポゼッションをしっかりして、崩してっていうシーンはなかなか…。それはシーズンを通してもなかなかあるもんじゃないんですよ」
えのきど「就任最初の試合(14節清水戦)後に、監督会見で『どっから手を付けられたんですか?』という僕の質問に、柳下さんは『攻撃からです』って答えられたんですね。
こんなに状態の悪いチームに入っていく監督さんっていうのは、どこが使えるのか?誰が使えるのか?って問題、課題をあぶりだしながら、どう判断していくんだろうと思っていたんです。苦しい状況のなかで『これで行くしかないんだ』って見極める、手応えを掴むっていうのはどういう風なことなのかって思いながら見てました」
柳下「磐田を率いていた時に新潟とも対戦していました。新潟の選手たちのある程度の特徴も把握していたし、去年の前半なんかは時間があったんで新潟ももちろん、色んなゲームを見ていました。だから、ある程度はわかっていました。ただ実際グランドに行ってみて、思っていたよりミスが多いなって言うのが一番初めに思ったことですね」
えのきど「ミスが多い。それは技術が足りないんですか? 気持ちの問題ですか?」
柳下「これは、よく言っていたんですけれどね。常にハイスピード、トップスピードすぎるんですね。どんなにいい選手でも、全力でトップスピードでやればミスも出る。周りを見る時間も無いし、視野も狭くなるわけです。『もっとゆっくりやりなさい』『保持する時間を長くしなさい』ということを、これはかなり、本当にいろんな言葉を使いながら伝えました。もともと持ってるカウンター攻撃には特徴があって、それは選手みんなの体にしみ込んでいる。カウンターの時にはそういうスピードに乗ったいいプレーをするんですが、カウンターの場面でもないのに同じようにスピードを上げる。それでミスをして相手にボールを渡してしまう。攻撃の方から手を付けたというのはそのことです。ゆっくりとはそういうことなんです」
えのきど「戦力の把握にしても、戦術にしてもスムーズに入ることが出来た?」
柳下「そうです。ある程度の部分はわかっていました、これぐらいはやれるだろうと。誰でもあの状況では守備のところを確立したいと思うんでしょうが、守備の面では一生懸命にすごくいいプレーをしていました。守備面で話したことは少しだけですね」
えのきど「距離感のことをよく言ってらっしゃいましたが、それは?」
柳下「ホントにうまい選手は30、40メートルのパスをミスなく通す。受けても出してもキチンと通す。去年の新潟の選手は20メートルでミスをする。彼らにとっては20メートルの距離はいい距離ではない」
えのきど「なるほど」
柳下「だったら近づいてミスのない距離を保てと。それでもできない。『もっと近くもっと近く』と言い続けました。『お互いのやりやすい距離』、『ミスしてもすぐに取り返すことのできる距離』、『リカバリー出来る距離』、色んな言葉で言い続けてトレーニングをし続けました」
えのきど「結果は劇的には改善されなかったけど、チームが良くなっていくのはわかったんですね。それにしても柳下さん、ブレないなーってびっくりするくらいに感じましたね。もう、これは後光が差してるなーって」
柳下「(笑) まあ、自分のなかに入っているサッカーってそれなんですね。根本のところ。指導者になってから悩んだことも実際にあります。これでいいのかって。でも最終的には、他人がなんと言おうと自分はこれなんだと。これが自分のスタイルで、このサッカーが好きなんだと。そのためにどういうトレーニングがいいのかと。これを指導者はみんな考えると思うんですが、人それぞれにあって、自分はこういうやり方が得意、これしか出来ない。逆に言ったら経験していくなかで他のことを捨てていくことが出来た。伝わりやすい、スムーズなやり方を選んでいって、それがある程度わかってきました。自信を持ってやっていけるって」
えのきど「捨てるってことは、絶対感ですね。経験のなかで出てくる言葉ですね」
柳下「他のやり方では出来ないってことなんですよ。いい指導者だったら色んなアプローチの方法があって伝えていくはずなんですが、でも自分はこのやり方でしか出来ない。だから出来るもので伝えようと思ったんです」
えのきど「僕はライターで、もう50代なんですけれど。若い頃の方がきつかったです。若い頃は何でもやりたかった。いろんな方法でやってみたりしたかったんです」
柳下「そうです、そうです」
えのきど「でも、それで逆にがんじがらめになったり、今はこれでっていう絞ったやり方でやっていって、それが反対に色々と出来るっぞて感覚ですね。あれもこれもであきらめきれないでいた若い頃の方が苦しんだですね」
柳下「色んなことやってきて、ホントに選手のためになっているんだろうかと悩んで、でも何人かの指導者から良くなっているよと言われて、こういうやり方でいいのかってだんだん見つけ出しましたけれどね」
えのきど「結果のこと、それについては考えませんでしたか」
柳下「去年?」
えのきど「去年」
柳下「いえ、それは…いつも気になってましたよ」
えのきど「いや、そうは見えなかったなー」
柳下「監督に就任した時点で、最終的に勝点39をとろうと、そこまで行けば…。自分自身は39あれば大丈夫だと、そう思っていましたよ。でもシーズンが進むにしたがって、大宮にしても他にしても勝ち続ける、勝点を重ねてくるんです。これは40以上行かなければ難しいなと、40取るためにはどうしたらいいんだって。そういう計算はしてました」
えのきど「思うような結果が出ない時にも、それは会見でもどこでもブレてない姿を見せる。ピッチサイドに立ってる姿を見る選手にももちろん、それはサポーターにも、船長がブレてないその姿はすごく助かるんだけど、それはそんなカンタンなことじゃないんだよなーって思って。もう柳下さんにピカーッって後光が差して見えたんですよ。自信あるんだなーって見えたんですよ」
柳下「それはどうかわからないんですが(笑)勝点取れなくても、負けたゲームでも、確実に少しずつでも良くなっていることはわかっていたんで、いいところを見つけて話していたのかもしれないですね。反対に勝ったゲームでは悪いところを見つけて話していました。きっと選手たちにもメディアを通して伝わるだろうからって」
えのきど「例えば野球の野村克也さんが、新聞の紙面やメディアを通して選手たちに伝えるってよく言いますね、もちろんどんなサッカーの監督にもそういうことってあると思います。そこでね、ひとつお聞きしたいのはですね、ちょっと言いにくいことなんですけれど。僕が聖籠に練習を見に行ったときのことなんです。柳下さんが菊地をものすっごく怒ったシーンを見たんですね」
柳下「ええ」
えのきど「あの…あの時はですね。『おまえはずーっとそうだ!』『やる気がないんだ!』『俺が来てから2カ月ずっとそうだ!』って、もうみんなの前で痛罵するんです。でもね、これは想像なんですが、菊地っていう選手はうまいし実力もある選手ってわかるんだけど、柳下さんは監督として戦っているという立場があって、つまり基準を示さないといけないですよね。菊地へのメッセージと併せて他の選手たち全員へのメッセージ、『おまえらも聞いてるな』って伝えてるのかなって思って見ていました。それにしても…ブワーって言ってるんですよ」
柳下「いえ、あの時はね、その以前から菊地に言い続けていたことがあったんですよ。それでも直らなくて。もう最後だぞって言う意味で強く言ったんです。同じように怒鳴ったことがミシェウにもありました。それはミスではなくて、やらなきゃいけないことをやらない、やってるって言うけれどやってないよ、ということです。それは言い続けてることだと。今はこういうやさしい口調で言ってますが…」
えのきど「(笑)」
柳下「ずっと言ってることだから、強く言いました。『やらなきゃならないことをやってない、やっちゃいけないことをやってるぞ』ってことなんです。菊地とはその後、少し話して、それ以降がんばろうとしてくれてましたけれど、今までのツケでなかなかうまく出来ませんでした。今はがんばっている姿を見せてくれてます。僕はそういうとき、特に二度三度続く時には強く言います。たしかに周りの選手も聞いてるからピリッとはしますね。ミシェウは、他の選手のミスをワーッと言ってプレーもやめちゃったんですね。『言うのはいいけれど、プレーは続けなさい』って強く言いました。それは僕が新潟に行ってすぐだったんですね、それでチーム全体はピリっとなりました。行ってすぐだったんでその後はずいぶん楽しました」
えのきど「ほう」
柳下「あとは何も言わなくても、普段からピリピリやってました(笑)」
えのきど「選手への伝え方には、たとえば1対1で話した方が効く場合もあるだろうし、むしろみんなの前で言った方が効く場合も逆にあるだろうし…」
柳下「それはオフトでも、フェリペ(ともに元磐田監督)でも、中心選手が間違ったことをした時にはガツンと言ってました。ミスではなくて、やらなきゃいけないことをやってないときですね。他の選手も『あの選手でも言われるんだ』と思うんです。みんなの前でいうより、1対1で話した方がいいって言う人はいますよ。凹むからって。でも僕の経験では後で呼んで話して良くなった選手はいないんですよ」
えのきど「へー」
柳下「オフトがよく言ってました『指導する人間がグランドの上でどうしたいか、何を求めてるかを言わないと残らない』と。そういうことを僕もずーっと見て来て、その瞬間じゃないと残らないんだなって思いました。そしてそれは、グラウンド上で全部終わりにするってことです」
えのきど「僕も今までに言われたことも言ったことも両方ありますけれどね、受け入れる気持ちになるまではその人に染み透って行かないんですよね。それは弱さなんですけれどね。例えば、僕が思うにワカゾーでこいつ脈あるなっていうライターはダメだけ言ったら、その瞬間から考え始めるんです。じゃないとダメなんですよ。ポイントを言っても、すぐその場で使える実践的な状態にならない。マニュアルを教えても残らないんです。脈がある奴はダメだけ言って、そこから考えることで力をつけていく」
柳下「そうですね」
えのきど「ファンも選手を物語で続きもので見るからそんなことはカッコ悪いことでも何でもないんですけどね、あの悔しさがあったから強くなってるっていう感じでね。菊地のことに限らないですが、柳下さんが人前でもその場で強く言うっていうのはすごくいいことだと思います。曖昧にするっていうのは残らないっていう」
柳下「どうしてもその瞬間でないと残らないんですよ。その瞬間ならば、残る。プレーでもその状況で言ってあげると考えるんですね。これが後でたとえばビデオ見ながらだと、全体が見えてわかってしまうから残らないんです。わかってもプレーは変わっていかないんです。グランドの平面の全体が見えていない場所で言わないとプレーは変わらない。そこまで導いてあげるのが僕らの仕事。賢い選手は一回二回言っただけでも頭のなかでイメージできますね。福西(崇史)、奥(大介)、名波(浩)(いずれも元磐田)とかはパッとした返事こそないんですけれど、その時ぐっと考えるから出来ていきましたね。返事がハイハイっていうヤツほど頭に残ってないですね」
えのきど「早わかりするヤツはね…(笑)」
【後篇に続く】
柳下「ハイ、よろしくお願いします」
えのきど「今日は伺いたいことはいくつかあるんですけれど、主眼としては柳下さんがどんな方かっていうことも、このインタビューの中で具体的にしたいと思っております」
柳下「(笑)」
えのきど「そこはかねてから大変関心がありまして(笑)。昨シーズンでのご様子とか拝見してきて、面白い方だな、話をお聞きしたいなと思っていたんです」
柳下「お願いします」
えのきど「まずはチームのことを。アルビレックスはキャンプ相当長いですよね?キャンプのまま開幕へっていう流れは雪国のチームはしょうがないんですけど。今までのご経験の中ではどうなんですか?」
柳下「そうですね。札幌、山形、仙台、新潟…北のチームはしょうがないですね。まあ、僕も札幌で3年間やってきましたから」
えのきど「そうですね、札幌がありますね」
柳下「札幌の1年目でしたが、同じところでのキャンプが相当長かったんです。グアム、鹿児島・指宿。同じところで長いと、どうしてもダレるんです。ちょっとキツイなと感じてた。ですので、2年目からはひとつの場所を11日間にして、休みを入れずにそのまま一気にぶっ通しで行く。2週間を超えるとどうしても途中で丸一日休まないといけない。いままでの経験で、ひとつの場所で休みを入れずに10日間か11日間のキャンプを集中してやる。場所を変えるんで、移動日も兼ねた休みをあげて、というくり返しを3回くらい、リフレッシュと集中を繰り返す。今回、このやり方で新潟もうまくいってると感じています」
えのきど「選手は開幕までの毎日、だんだんとギューっと集中していく感じですか?」
柳下「それがやっぱり難しいんですよね。外に出続けてるから、そこが難しいでしょうね」
えのきど「選手も、移籍した選手なんか特に勝手が違って難しいかもしれませんね」
柳下「そうですね。他のチームは基本的には長くて2週間のキャンプで一度戻りますから。そこですね」
えのきど「非常事態を引き受ける形で入って来た去年と、シーズンの最初からやってる今年とは違いますか?」
柳下「途中からやったのは去年が初めてでしたけれど、自分のイメージするサッカースタイル、私自身の体のなかに入っているサッカーと新潟がやっていたサッカーはそう離れてなかった。それはやりやすかったですよ。全く違うものを私が求めるとなると、それは相当に時間がかかると思ってましたが、私の体のなかに入ってる部分と同じものがかなりあったんで、そんなに難しいことではありませんでした」
えのきど「僕が思ったのはですね、柳下さんが持ってらっしゃるサイド攻撃とかのイメージを考えると、カウンターサッカーをやらなきゃならないのは不本意だったりするんじゃないかなって」
柳下「それはありました。でも、あの状況だと仕方がない」
えのきど「仕方がない?」
柳下「ただ、どこのチームもカウンターは存在していて、どこのチームも点をたくさん取っているのはカウンターからなんですよ、実は。ポゼッションをしっかりして、崩してっていうシーンはなかなか…。それはシーズンを通してもなかなかあるもんじゃないんですよ」
えのきど「就任最初の試合(14節清水戦)後に、監督会見で『どっから手を付けられたんですか?』という僕の質問に、柳下さんは『攻撃からです』って答えられたんですね。
こんなに状態の悪いチームに入っていく監督さんっていうのは、どこが使えるのか?誰が使えるのか?って問題、課題をあぶりだしながら、どう判断していくんだろうと思っていたんです。苦しい状況のなかで『これで行くしかないんだ』って見極める、手応えを掴むっていうのはどういう風なことなのかって思いながら見てました」
柳下「磐田を率いていた時に新潟とも対戦していました。新潟の選手たちのある程度の特徴も把握していたし、去年の前半なんかは時間があったんで新潟ももちろん、色んなゲームを見ていました。だから、ある程度はわかっていました。ただ実際グランドに行ってみて、思っていたよりミスが多いなって言うのが一番初めに思ったことですね」
えのきど「ミスが多い。それは技術が足りないんですか? 気持ちの問題ですか?」
柳下「これは、よく言っていたんですけれどね。常にハイスピード、トップスピードすぎるんですね。どんなにいい選手でも、全力でトップスピードでやればミスも出る。周りを見る時間も無いし、視野も狭くなるわけです。『もっとゆっくりやりなさい』『保持する時間を長くしなさい』ということを、これはかなり、本当にいろんな言葉を使いながら伝えました。もともと持ってるカウンター攻撃には特徴があって、それは選手みんなの体にしみ込んでいる。カウンターの時にはそういうスピードに乗ったいいプレーをするんですが、カウンターの場面でもないのに同じようにスピードを上げる。それでミスをして相手にボールを渡してしまう。攻撃の方から手を付けたというのはそのことです。ゆっくりとはそういうことなんです」
えのきど「戦力の把握にしても、戦術にしてもスムーズに入ることが出来た?」
柳下「そうです。ある程度の部分はわかっていました、これぐらいはやれるだろうと。誰でもあの状況では守備のところを確立したいと思うんでしょうが、守備の面では一生懸命にすごくいいプレーをしていました。守備面で話したことは少しだけですね」
えのきど「距離感のことをよく言ってらっしゃいましたが、それは?」
柳下「ホントにうまい選手は30、40メートルのパスをミスなく通す。受けても出してもキチンと通す。去年の新潟の選手は20メートルでミスをする。彼らにとっては20メートルの距離はいい距離ではない」
えのきど「なるほど」
柳下「だったら近づいてミスのない距離を保てと。それでもできない。『もっと近くもっと近く』と言い続けました。『お互いのやりやすい距離』、『ミスしてもすぐに取り返すことのできる距離』、『リカバリー出来る距離』、色んな言葉で言い続けてトレーニングをし続けました」
えのきど「結果は劇的には改善されなかったけど、チームが良くなっていくのはわかったんですね。それにしても柳下さん、ブレないなーってびっくりするくらいに感じましたね。もう、これは後光が差してるなーって」
柳下「(笑) まあ、自分のなかに入っているサッカーってそれなんですね。根本のところ。指導者になってから悩んだことも実際にあります。これでいいのかって。でも最終的には、他人がなんと言おうと自分はこれなんだと。これが自分のスタイルで、このサッカーが好きなんだと。そのためにどういうトレーニングがいいのかと。これを指導者はみんな考えると思うんですが、人それぞれにあって、自分はこういうやり方が得意、これしか出来ない。逆に言ったら経験していくなかで他のことを捨てていくことが出来た。伝わりやすい、スムーズなやり方を選んでいって、それがある程度わかってきました。自信を持ってやっていけるって」
えのきど「捨てるってことは、絶対感ですね。経験のなかで出てくる言葉ですね」
柳下「他のやり方では出来ないってことなんですよ。いい指導者だったら色んなアプローチの方法があって伝えていくはずなんですが、でも自分はこのやり方でしか出来ない。だから出来るもので伝えようと思ったんです」
えのきど「僕はライターで、もう50代なんですけれど。若い頃の方がきつかったです。若い頃は何でもやりたかった。いろんな方法でやってみたりしたかったんです」
柳下「そうです、そうです」
えのきど「でも、それで逆にがんじがらめになったり、今はこれでっていう絞ったやり方でやっていって、それが反対に色々と出来るっぞて感覚ですね。あれもこれもであきらめきれないでいた若い頃の方が苦しんだですね」
柳下「色んなことやってきて、ホントに選手のためになっているんだろうかと悩んで、でも何人かの指導者から良くなっているよと言われて、こういうやり方でいいのかってだんだん見つけ出しましたけれどね」
えのきど「結果のこと、それについては考えませんでしたか」
柳下「去年?」
えのきど「去年」
柳下「いえ、それは…いつも気になってましたよ」
えのきど「いや、そうは見えなかったなー」
柳下「監督に就任した時点で、最終的に勝点39をとろうと、そこまで行けば…。自分自身は39あれば大丈夫だと、そう思っていましたよ。でもシーズンが進むにしたがって、大宮にしても他にしても勝ち続ける、勝点を重ねてくるんです。これは40以上行かなければ難しいなと、40取るためにはどうしたらいいんだって。そういう計算はしてました」
えのきど「思うような結果が出ない時にも、それは会見でもどこでもブレてない姿を見せる。ピッチサイドに立ってる姿を見る選手にももちろん、それはサポーターにも、船長がブレてないその姿はすごく助かるんだけど、それはそんなカンタンなことじゃないんだよなーって思って。もう柳下さんにピカーッって後光が差して見えたんですよ。自信あるんだなーって見えたんですよ」
柳下「それはどうかわからないんですが(笑)勝点取れなくても、負けたゲームでも、確実に少しずつでも良くなっていることはわかっていたんで、いいところを見つけて話していたのかもしれないですね。反対に勝ったゲームでは悪いところを見つけて話していました。きっと選手たちにもメディアを通して伝わるだろうからって」
えのきど「例えば野球の野村克也さんが、新聞の紙面やメディアを通して選手たちに伝えるってよく言いますね、もちろんどんなサッカーの監督にもそういうことってあると思います。そこでね、ひとつお聞きしたいのはですね、ちょっと言いにくいことなんですけれど。僕が聖籠に練習を見に行ったときのことなんです。柳下さんが菊地をものすっごく怒ったシーンを見たんですね」
柳下「ええ」
えのきど「あの…あの時はですね。『おまえはずーっとそうだ!』『やる気がないんだ!』『俺が来てから2カ月ずっとそうだ!』って、もうみんなの前で痛罵するんです。でもね、これは想像なんですが、菊地っていう選手はうまいし実力もある選手ってわかるんだけど、柳下さんは監督として戦っているという立場があって、つまり基準を示さないといけないですよね。菊地へのメッセージと併せて他の選手たち全員へのメッセージ、『おまえらも聞いてるな』って伝えてるのかなって思って見ていました。それにしても…ブワーって言ってるんですよ」
柳下「いえ、あの時はね、その以前から菊地に言い続けていたことがあったんですよ。それでも直らなくて。もう最後だぞって言う意味で強く言ったんです。同じように怒鳴ったことがミシェウにもありました。それはミスではなくて、やらなきゃいけないことをやらない、やってるって言うけれどやってないよ、ということです。それは言い続けてることだと。今はこういうやさしい口調で言ってますが…」
えのきど「(笑)」
柳下「ずっと言ってることだから、強く言いました。『やらなきゃならないことをやってない、やっちゃいけないことをやってるぞ』ってことなんです。菊地とはその後、少し話して、それ以降がんばろうとしてくれてましたけれど、今までのツケでなかなかうまく出来ませんでした。今はがんばっている姿を見せてくれてます。僕はそういうとき、特に二度三度続く時には強く言います。たしかに周りの選手も聞いてるからピリッとはしますね。ミシェウは、他の選手のミスをワーッと言ってプレーもやめちゃったんですね。『言うのはいいけれど、プレーは続けなさい』って強く言いました。それは僕が新潟に行ってすぐだったんですね、それでチーム全体はピリっとなりました。行ってすぐだったんでその後はずいぶん楽しました」
えのきど「ほう」
柳下「あとは何も言わなくても、普段からピリピリやってました(笑)」
えのきど「選手への伝え方には、たとえば1対1で話した方が効く場合もあるだろうし、むしろみんなの前で言った方が効く場合も逆にあるだろうし…」
柳下「それはオフトでも、フェリペ(ともに元磐田監督)でも、中心選手が間違ったことをした時にはガツンと言ってました。ミスではなくて、やらなきゃいけないことをやってないときですね。他の選手も『あの選手でも言われるんだ』と思うんです。みんなの前でいうより、1対1で話した方がいいって言う人はいますよ。凹むからって。でも僕の経験では後で呼んで話して良くなった選手はいないんですよ」
えのきど「へー」
柳下「オフトがよく言ってました『指導する人間がグランドの上でどうしたいか、何を求めてるかを言わないと残らない』と。そういうことを僕もずーっと見て来て、その瞬間じゃないと残らないんだなって思いました。そしてそれは、グラウンド上で全部終わりにするってことです」
えのきど「僕も今までに言われたことも言ったことも両方ありますけれどね、受け入れる気持ちになるまではその人に染み透って行かないんですよね。それは弱さなんですけれどね。例えば、僕が思うにワカゾーでこいつ脈あるなっていうライターはダメだけ言ったら、その瞬間から考え始めるんです。じゃないとダメなんですよ。ポイントを言っても、すぐその場で使える実践的な状態にならない。マニュアルを教えても残らないんです。脈がある奴はダメだけ言って、そこから考えることで力をつけていく」
柳下「そうですね」
えのきど「ファンも選手を物語で続きもので見るからそんなことはカッコ悪いことでも何でもないんですけどね、あの悔しさがあったから強くなってるっていう感じでね。菊地のことに限らないですが、柳下さんが人前でもその場で強く言うっていうのはすごくいいことだと思います。曖昧にするっていうのは残らないっていう」
柳下「どうしてもその瞬間でないと残らないんですよ。その瞬間ならば、残る。プレーでもその状況で言ってあげると考えるんですね。これが後でたとえばビデオ見ながらだと、全体が見えてわかってしまうから残らないんです。わかってもプレーは変わっていかないんです。グランドの平面の全体が見えていない場所で言わないとプレーは変わらない。そこまで導いてあげるのが僕らの仕事。賢い選手は一回二回言っただけでも頭のなかでイメージできますね。福西(崇史)、奥(大介)、名波(浩)(いずれも元磐田)とかはパッとした返事こそないんですけれど、その時ぐっと考えるから出来ていきましたね。返事がハイハイっていうヤツほど頭に残ってないですね」
えのきど「早わかりするヤツはね…(笑)」
【後篇に続く】