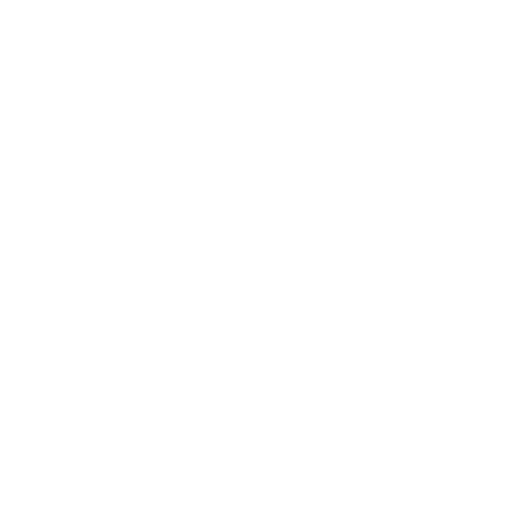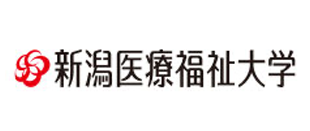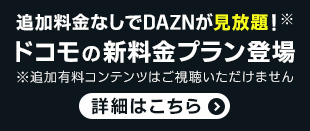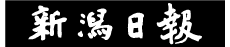【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第181回
2013/8/1
「足のつる人」
今朝未明、右足ふくらはぎがつって、激痛で目を覚ましたのだ。滅多にないことだが、足がつって起きるのはあわてる。暑い時期、水分補給には気をつけているけれど(今週は炎天下の平塚球場へ桐蔭学園高校の甲子園予選を見に行った)、ナトリウム等のミネラル分も補わないといけないそうだ。よく旅先で見かける薬局の広告(?)というのか、張り紙があって、基本、オレンジとかイエローみたいな蛍光色の下地にたったひと言、「足のつる人」と書いてある。
あの、そこはかとないおかしさである。ワンフレーズ何か書いて、ひとを笑わせようと企んでるとしたら「足のつる人」は秀逸だ。まさか、そんなという意外さがある。「血圧高い人」でも「頭痛の人」でもなく、足がつるかどうかを問題にしてるのか。つるでしょう、健康体の人も。アルビレックス新潟の選手も夏場はよく足がつる。
で、けんめいのフィールドワークの結果、「足のつる人」張り紙には、もうひとフレーズ添えられてることを確認した。「足のつる人 ご相談下さい」だ。もちろん印象がなかったくらいだから「ご相談下さい」部分は字も小さく、線も細い。こう、見過してしまえば一生気づかずに終わりそうな感覚だ。例えて言えば東京みやげの定番「東京ばな奈」である。僕は(店の人はともかくとして)あれを「東京ばな奈」以外の呼び方をする人に会ったことがない。が、正確には「東京ばな奈『見ぃつけたっ』」という商品なのである。わざわざカギカッコだ。誰の発言だ。見過ごしてしまえば一生気づかずに終わりそうな疑問点じゃないか。
で、当たり前だがこの際、「東京ばな奈『見ぃつけたっ』」はいいのである。考えねばならないのは「足のつる人 ご相談下さい」だ。まぁ、だから薬局の人に「すいません、あの私、ちょっと足がつるんですけど…」と相談してみる事態だ。これはマグネシウムとかのサプリメントを薦められるらしい。まぁ、薬局がわざわざ張り出しているのだから、そりゃそうなのだ。
だが、僕が相談したいことはそういうことではない。「足がつる」の用法。言葉の問題だ。僕は様々な場面で、サッカーにはまだ日本語にない状況があるんだなぁと実感している。これが気になるのは、たぶん実況アナとライターがいちばんだろう。例えば「三門の足がつった」という言葉、というか状況を検討されたい。僕の語感では「(三門の)足がつった」と足をメインにした言い方が正しく、「三門が足をつった」は間違っている。
僕は日本では「足がつった」のだと思うのだ。おそらく9割9分は私的な場面で。足メインで間違いようがなかった。誰の足かというと、私かあなたか家族の誰かの足だ。そんな私的な足だけがつった。正確なところはわからないが、ことによると年号が大正・昭和になるまで「○○の足がつった」なんてシチュエーションは日本になかったのではないか。何万人収容のスタジアムで「○○の足がつった」のを皆で見ている特殊状況はどうだ。そのつった足は成岡の足でなく大井の足でなく「三門の足」だ。少なくとも江戸時代にはありえない状況だ。
私的な領域だけで事足りた日本語「足がつる」は何と公的領域まで拡大されて、誰の足かを特定されるような運びとなった。で、実況アナウンスや再現記事で、主語を言いたいときにちょっと困った事態が出来(しゅったい)する。つい「三門が」と主語を言う。と「三門が足がつった」では「が」が2つになってしまう。ので「三門が足をつった」と「を」でつないでみる。ニュアンスとしては「あぁ、三門選手が足をつってますね~」みたいな実況を思い浮かべるといいです。
だけどね、僕は「三門が足をつった」「三門が足をつってる」(ていうか、過去形で言う決まりなのか、現在進行形で扱っていいのかすらあいまいですよ、「足がつる」は!)には、ひきつるという意味の「攣(つ)る」がハマらないと思うんですね。ぶら下げる意味の「吊る」ならすんなりハマる。だから「手を吊る」は骨折したりして三角巾で腕を吊ってる状況ですよ。「足を吊る」はもう交通事故かスキーの複雑骨折ですね。患者さんはベッドに寝ていて、石膏で固めた足を吊り下げられている。三門が? 冗談でもそんなの勘弁して下さい。
だから三門雄大ら、アルビレックス新潟の選手は衆人環視のもとで足がつる日本人の第一世代なのかも知れません。せいぜい100年、下手すると50年未満。「誰が」と主語が問題になる公的領域の出来事だから、ついつい「足を吊る」とまぎらわしい言い方をされる。まだ日本語には「私は」「あなたは」「三門は」に続く、正しい「足がつる」がないんだと思うんです。
サッカーを書いていて、ホントに日本語は不自由かつ窮屈なものだなぁと感じているんですよ。「日本語でサッカーを言う」の歴史が浅いのかなぁ。別の例を挙げると「スラす」ですよね。あれ、広辞苑にのってそうな他の日本語で言ってみて下さい。「スラす」ってどう考えてもスラング(俗語)ですよね。「チンチンにする」とかと同じで、サッカー部が昭和のどこかで必要に迫られて作った言葉だと思う。「スラす」は別の日本語にならないんですよ。「バックヘッド」とも違う。英語的には「ディフレクション」なのかな。
だからサッカーの身体的な表現は日本語ではまだ未成熟なんですね。ま、だからこそ「ドリブルする」とか「オーバーラップする」とか、カタカナばっかり使っている。
しかし、「スラす」はNHKアナウンサーも「いわゆる」をつけたりして使っている。他に言いようがないんだなぁ。あれ、頭で角度をちょっと変えるのが「スラす」ですよね。頭以外は「角度を変える」しか言い方がないねぇ。「擦(す)らす」だとしたら、別に頭でなくてもどっかに触れて摩擦が生じてたらよさそうなもんだよなぁ。
まとめますと三門ら選手は衆人環視のもと足がつったり、頭で角度を変えたりする第一世代ってことでしょうか。夢をありがとうと言わせて下さい。
附記1、まさか「足のつる人」でひとネタ行っちゃうとは思いませんでした。本当は菊地直哉選手のサガン鳥栖へのレンタル移籍について書かなきゃダメかなと気が重かったんですよ。「おお」「きく」「なる」がまさか新潟で再集結するとは、しかも監督がヤンツーさんとは! と、サッカーファンなら誰もが楽しみにしていました。今のチームに割って入ってくる「迫力満点の菊地」が見たかった。ま、でもセイローへ足繁く通って取材してるわけでもないし、軽々には論じられない問題ですよね。
2、ただ一般論として、控え組のモチベーションの管理はものすごく難しいとこですよ。控え組のモチベーションこそがチームの質を作るじゃないですか。
3、今週末、隅田川花火なんですけど、久々だなぁ、自宅で花火見るの。花火が見えるってことで川沿いのマンション購入したんですけどね。大概、Jリーグ日程と重なって、家を空けてばっかりでした。うちの辺、通行止めになっちゃうんですよね。早めに出ないと浅草駅までたどり着けない。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!

今朝未明、右足ふくらはぎがつって、激痛で目を覚ましたのだ。滅多にないことだが、足がつって起きるのはあわてる。暑い時期、水分補給には気をつけているけれど(今週は炎天下の平塚球場へ桐蔭学園高校の甲子園予選を見に行った)、ナトリウム等のミネラル分も補わないといけないそうだ。よく旅先で見かける薬局の広告(?)というのか、張り紙があって、基本、オレンジとかイエローみたいな蛍光色の下地にたったひと言、「足のつる人」と書いてある。
あの、そこはかとないおかしさである。ワンフレーズ何か書いて、ひとを笑わせようと企んでるとしたら「足のつる人」は秀逸だ。まさか、そんなという意外さがある。「血圧高い人」でも「頭痛の人」でもなく、足がつるかどうかを問題にしてるのか。つるでしょう、健康体の人も。アルビレックス新潟の選手も夏場はよく足がつる。
で、けんめいのフィールドワークの結果、「足のつる人」張り紙には、もうひとフレーズ添えられてることを確認した。「足のつる人 ご相談下さい」だ。もちろん印象がなかったくらいだから「ご相談下さい」部分は字も小さく、線も細い。こう、見過してしまえば一生気づかずに終わりそうな感覚だ。例えて言えば東京みやげの定番「東京ばな奈」である。僕は(店の人はともかくとして)あれを「東京ばな奈」以外の呼び方をする人に会ったことがない。が、正確には「東京ばな奈『見ぃつけたっ』」という商品なのである。わざわざカギカッコだ。誰の発言だ。見過ごしてしまえば一生気づかずに終わりそうな疑問点じゃないか。
で、当たり前だがこの際、「東京ばな奈『見ぃつけたっ』」はいいのである。考えねばならないのは「足のつる人 ご相談下さい」だ。まぁ、だから薬局の人に「すいません、あの私、ちょっと足がつるんですけど…」と相談してみる事態だ。これはマグネシウムとかのサプリメントを薦められるらしい。まぁ、薬局がわざわざ張り出しているのだから、そりゃそうなのだ。
だが、僕が相談したいことはそういうことではない。「足がつる」の用法。言葉の問題だ。僕は様々な場面で、サッカーにはまだ日本語にない状況があるんだなぁと実感している。これが気になるのは、たぶん実況アナとライターがいちばんだろう。例えば「三門の足がつった」という言葉、というか状況を検討されたい。僕の語感では「(三門の)足がつった」と足をメインにした言い方が正しく、「三門が足をつった」は間違っている。
僕は日本では「足がつった」のだと思うのだ。おそらく9割9分は私的な場面で。足メインで間違いようがなかった。誰の足かというと、私かあなたか家族の誰かの足だ。そんな私的な足だけがつった。正確なところはわからないが、ことによると年号が大正・昭和になるまで「○○の足がつった」なんてシチュエーションは日本になかったのではないか。何万人収容のスタジアムで「○○の足がつった」のを皆で見ている特殊状況はどうだ。そのつった足は成岡の足でなく大井の足でなく「三門の足」だ。少なくとも江戸時代にはありえない状況だ。
私的な領域だけで事足りた日本語「足がつる」は何と公的領域まで拡大されて、誰の足かを特定されるような運びとなった。で、実況アナウンスや再現記事で、主語を言いたいときにちょっと困った事態が出来(しゅったい)する。つい「三門が」と主語を言う。と「三門が足がつった」では「が」が2つになってしまう。ので「三門が足をつった」と「を」でつないでみる。ニュアンスとしては「あぁ、三門選手が足をつってますね~」みたいな実況を思い浮かべるといいです。
だけどね、僕は「三門が足をつった」「三門が足をつってる」(ていうか、過去形で言う決まりなのか、現在進行形で扱っていいのかすらあいまいですよ、「足がつる」は!)には、ひきつるという意味の「攣(つ)る」がハマらないと思うんですね。ぶら下げる意味の「吊る」ならすんなりハマる。だから「手を吊る」は骨折したりして三角巾で腕を吊ってる状況ですよ。「足を吊る」はもう交通事故かスキーの複雑骨折ですね。患者さんはベッドに寝ていて、石膏で固めた足を吊り下げられている。三門が? 冗談でもそんなの勘弁して下さい。
だから三門雄大ら、アルビレックス新潟の選手は衆人環視のもとで足がつる日本人の第一世代なのかも知れません。せいぜい100年、下手すると50年未満。「誰が」と主語が問題になる公的領域の出来事だから、ついつい「足を吊る」とまぎらわしい言い方をされる。まだ日本語には「私は」「あなたは」「三門は」に続く、正しい「足がつる」がないんだと思うんです。
サッカーを書いていて、ホントに日本語は不自由かつ窮屈なものだなぁと感じているんですよ。「日本語でサッカーを言う」の歴史が浅いのかなぁ。別の例を挙げると「スラす」ですよね。あれ、広辞苑にのってそうな他の日本語で言ってみて下さい。「スラす」ってどう考えてもスラング(俗語)ですよね。「チンチンにする」とかと同じで、サッカー部が昭和のどこかで必要に迫られて作った言葉だと思う。「スラす」は別の日本語にならないんですよ。「バックヘッド」とも違う。英語的には「ディフレクション」なのかな。
だからサッカーの身体的な表現は日本語ではまだ未成熟なんですね。ま、だからこそ「ドリブルする」とか「オーバーラップする」とか、カタカナばっかり使っている。
しかし、「スラす」はNHKアナウンサーも「いわゆる」をつけたりして使っている。他に言いようがないんだなぁ。あれ、頭で角度をちょっと変えるのが「スラす」ですよね。頭以外は「角度を変える」しか言い方がないねぇ。「擦(す)らす」だとしたら、別に頭でなくてもどっかに触れて摩擦が生じてたらよさそうなもんだよなぁ。
まとめますと三門ら選手は衆人環視のもと足がつったり、頭で角度を変えたりする第一世代ってことでしょうか。夢をありがとうと言わせて下さい。
附記1、まさか「足のつる人」でひとネタ行っちゃうとは思いませんでした。本当は菊地直哉選手のサガン鳥栖へのレンタル移籍について書かなきゃダメかなと気が重かったんですよ。「おお」「きく」「なる」がまさか新潟で再集結するとは、しかも監督がヤンツーさんとは! と、サッカーファンなら誰もが楽しみにしていました。今のチームに割って入ってくる「迫力満点の菊地」が見たかった。ま、でもセイローへ足繁く通って取材してるわけでもないし、軽々には論じられない問題ですよね。
2、ただ一般論として、控え組のモチベーションの管理はものすごく難しいとこですよ。控え組のモチベーションこそがチームの質を作るじゃないですか。
3、今週末、隅田川花火なんですけど、久々だなぁ、自宅で花火見るの。花火が見えるってことで川沿いのマンション購入したんですけどね。大概、Jリーグ日程と重なって、家を空けてばっかりでした。うちの辺、通行止めになっちゃうんですよね。早めに出ないと浅草駅までたどり着けない。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!