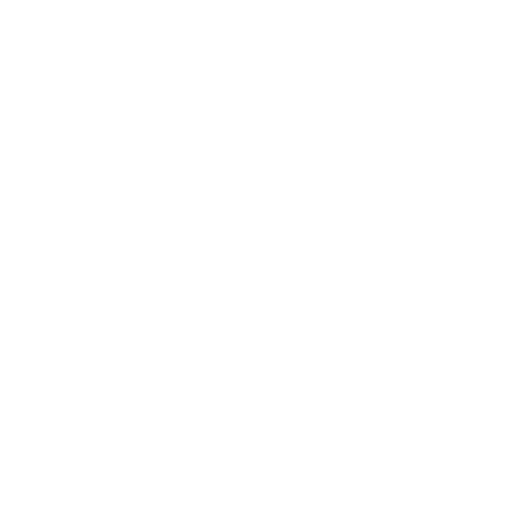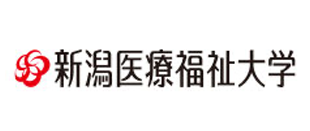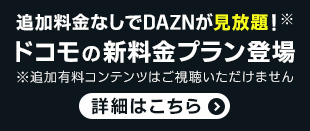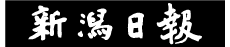【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第190回
2013/10/3
「山陰なう。」
J1第26節、広島×新潟。
試合翌日、松江駅前のスタバでこれを書いている。昨日はエディオンスタジアム広島(は、元の言い方をすると広島ビッグアーチだが)のデーゲームを終えて、中国山脈を越え、山陰側へ移動した。『週刊サッカーマガジン』で連載をしてた時代の担当編集者、石倉利英さんが郷里に戻ってるのだ。現在はフリーランスとしてガイナーレ鳥取をメインに健筆をふるっている。広島へもクルマでしょっちゅう取材に来てるという。
そりゃ「26節は記者席待ち合わせな!」ってことになるでしょう。で、終わったら石倉車で松江移動。だから広島県滞在時間短かったよ~。試合も含めて正味5時間くらい? 山越えの自動車道は月明かりに照らされていた。車中の話題は当然、今、見たばかりの試合だ。ジーコジャパン当時の代表担当記者とサッカー談義しながら山越えするという、ぜいたくかつ実にダイナミックな道中。
「楽な展開にしちゃいましたね。広島は2点リードして、出ていく理由がなくなった」
石倉さんがそう言うのも道理だ。新潟は早々と2失点(前半28分、ファン・ソッコ、同36分、佐藤寿人)を喫する。これは気温30.7℃のデーゲームだったというファクターを加味すると痛恨だ。「ほぼ試合は決まった」ぐらいの話だ。広島は(ますます)引いて、佐藤寿人のカウンターに特化する戦法になる。新潟はそこをこじ開けなくちゃならないが、ギャップやスペースをつくる動きが暑さで鈍っていく。
「1点め、高萩(洋次郎)が凄かったですね。左に行かず、右に行った、あれで勝負あった」
試合展開的には先取点が最重要だったと思う。広島の得点はカウンターからの速い展開だ。中央で受けた高萩が右に持ちだして石原直樹にあずける。左をファン・ソッコが猛然と上がってるのをわかってて、逆(石原の側)を選んだ。この一瞬の選択が新潟を混乱させる。石原からもらったファン・ソッコはフリーだった。あれは完全にやられました。
「広島は早い時間の先制点があんまり取れてないんです。3連敗中でもあったし、先制点は意識してたでしょう。10分経たないで追加点が奪えたのも久々じゃないかな。あぁなると広島は省エネに徹しますからね。やっぱり去年、優勝してリアリズムを身につけた部分はあると思うんです。省エネでもしっかり勝ち点取っていこうっていう」
話は省エネいうのか、炎天下のデーゲームに自然と振れていく。僕は最初、キックオフから互いにやりあって、しばらくして何となく「こんなペースじゃもたないから、ちょっと落とそうや」的な無言の会話がピッチ上にあった感じが面白かった。これは八百長みたいなことじゃないんだな。手合わせして、感覚で通じ合うような事柄だ。場合によってはわかった上でそれを裏切ったりもする。敵味方に分かれているが、彼らは同じ「通じるもの=身体的言語」を共有する、サッカー人なんだね。
僕もあんなペースじゃ(両軍とも)最後までもたなかったと思うけど、新潟は序盤、もうしばらく「アグレッシブ」を続ける手もあった気がしている。つまり、おつき合いしないで。そうだったらどうなってたかなぁと想像するのだ。
石倉さんは後半、新潟が盛り返した時間帯に注目した。あそこで1点でも返せていれば全然違う試合になったと言う。広島は案外、失点して追い着かれるようなもろさがあるそうだ。広島サポはあの時間帯、ヒヤヒヤしてたんじゃないか。まぁ、試合終盤は新潟もガス欠で、得点入る感じじゃなくなってたし、勝負どころは後半アタマだったかなぁ。
無得点試合に関して思うことを2つ。ひとつは川又堅碁が研究されてるね。マークがきびしくて、なかなか思うようにやらせてもらえない。ま、当然なんだけどね。Jリーグのスカウティングは相当なもんだと思いますよ。で、ケンゴは研究されてるなかで自分の仕事ができないと一流にはなれない。これは乗り越えるべき壁だ。がんばれケンゴ!
あと、攻めにかかったところで「新潟の宿命」的な問題があるかなぁ。柳下正明監督はマンマークで、人についていけって指示出してるね。責任を持って最後までつき切れ。これはもちろん一定以上の効果をもたらしている。おかげで今季は残留争いと無縁でいられそうだ。が、(新潟の選手は素直だから余計に)ついていく結果、いざ攻めにかかったとき、人数が足りなくなったりしている。ここの(選手個人の)判断は難しいね~。相当に高度なところだ。ま、原則は指示通り、マークにつき切れ、なんだけどね。
試合はとにかく完敗でしたね。山越えの車中は試合後の柳下さんのコメント、「悔しいですね。あんなつまらないサッカーに負けたのが悔しい」に移る。石倉さんは「負け惜しみにしか聞こえない。終始攻め続けたのにポストに嫌われるとかしたっていうならまだわかりますけど…」という意見。僕も大前提として戦った相手にリスペクトを持ちたいから、会見コメントを聞いてちょっと驚いた。
が、会見後、中継を担当したJスポーツの土屋雅史さんとバッタリ出くわし、TV用のフラッシュインタビューのウラ話を聞いて、あ、なるほどなと思った。柳下さんはわざわざ確認したそうだ。フラッシュインタビューがスタジアムの大型モニターに映るかどうか。で、順序としてはTV用のフラッシュインタビューでコメントして、しかるが後に監督会見で同じコメントを出した。つまり、僕が言いたいのは確信犯的にわざわざ出したコメントだいうこと。
で、意図は何だろう。わざわざサンフレッチェ広島と遺恨試合のギミックをつくろうみたいな話じゃないのは明白だ。僕はこれは新潟の選手へ向けた発信だと思う。チームの方向性をブレさせない。自信を失わせたくない。まぁ、それでも広島サポは「ヤンツー、俺らをダシにすんな」と気持ちがおさまらないと思うが、真意はそんなところだね。
自分たちでアクションを起こせるサッカー。仕掛けるサッカー。
「奪う力」で注目されてる新潟が目指しているのは、自在型の攻撃サッカーだった。柳下さんはその宣言をしたようなもんじゃないか。で、それは「面白いサッカー」だと言い切ったに等しい。面白いねぇ、その「面白いサッカー」を僕らは見るんだ。
附記1、東口順昭選手の全身オレンジユニが超レアでしたね。あれは惑星直列級の偶然が重ならないと見ることができないらしい。僕は「あ、オレンジも持ってるんだ」と妙な感心の仕方でした(笑)。
2、松江駅前のスタバって今年3月にオープンして、大騒ぎになった店ですよ。島根県初出店ってことでオープン当日はどえらい行列ができていた。地元ニュースのトップ項目扱いだったはずです。さすがに9月にはもう落ち着いてました。
3、松江市には2泊して、毎日、宍道湖畔をウォーキングしたりして、僕的には非常に充実してたんですけど、どうも石倉さんにはショック続きな連休でしたね。まず、この原稿書き上げた後、僕は石倉家へお邪魔して、岐阜×鳥取の「J2裏天王山」をスカパー観戦するんですけど、ガイナーレ鳥取が敗れて最下位転落。翌・秋分の日はヤフーのホットワードに「サカマガ 月刊化」が出た日です。石倉さんも僕もその情報は既に知っていて、今回の松江旅行の主要な議題は「週刊サッカーマガジンが月刊化する、サッカー業界縮小の動きにどう向き合うべきか」だったですね。しかしなぁ、シーズン途中での月刊化ってよくよくのことなんだと思います。
4、だから月刊になる前に新潟特集号(2013年10月1日号、「新アルビ主義/柳下新潟の進化とは何か?」)が出てよかったですね。県内の争奪戦もいい思い出です。サカマガは僕にとってはお世話になった「古巣」ですからね。ホントに寂しいです。ま、休刊するわけじゃないからネガティブに考えないようにはしたいけど。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!

J1第26節、広島×新潟。
試合翌日、松江駅前のスタバでこれを書いている。昨日はエディオンスタジアム広島(は、元の言い方をすると広島ビッグアーチだが)のデーゲームを終えて、中国山脈を越え、山陰側へ移動した。『週刊サッカーマガジン』で連載をしてた時代の担当編集者、石倉利英さんが郷里に戻ってるのだ。現在はフリーランスとしてガイナーレ鳥取をメインに健筆をふるっている。広島へもクルマでしょっちゅう取材に来てるという。
そりゃ「26節は記者席待ち合わせな!」ってことになるでしょう。で、終わったら石倉車で松江移動。だから広島県滞在時間短かったよ~。試合も含めて正味5時間くらい? 山越えの自動車道は月明かりに照らされていた。車中の話題は当然、今、見たばかりの試合だ。ジーコジャパン当時の代表担当記者とサッカー談義しながら山越えするという、ぜいたくかつ実にダイナミックな道中。
「楽な展開にしちゃいましたね。広島は2点リードして、出ていく理由がなくなった」
石倉さんがそう言うのも道理だ。新潟は早々と2失点(前半28分、ファン・ソッコ、同36分、佐藤寿人)を喫する。これは気温30.7℃のデーゲームだったというファクターを加味すると痛恨だ。「ほぼ試合は決まった」ぐらいの話だ。広島は(ますます)引いて、佐藤寿人のカウンターに特化する戦法になる。新潟はそこをこじ開けなくちゃならないが、ギャップやスペースをつくる動きが暑さで鈍っていく。
「1点め、高萩(洋次郎)が凄かったですね。左に行かず、右に行った、あれで勝負あった」
試合展開的には先取点が最重要だったと思う。広島の得点はカウンターからの速い展開だ。中央で受けた高萩が右に持ちだして石原直樹にあずける。左をファン・ソッコが猛然と上がってるのをわかってて、逆(石原の側)を選んだ。この一瞬の選択が新潟を混乱させる。石原からもらったファン・ソッコはフリーだった。あれは完全にやられました。
「広島は早い時間の先制点があんまり取れてないんです。3連敗中でもあったし、先制点は意識してたでしょう。10分経たないで追加点が奪えたのも久々じゃないかな。あぁなると広島は省エネに徹しますからね。やっぱり去年、優勝してリアリズムを身につけた部分はあると思うんです。省エネでもしっかり勝ち点取っていこうっていう」
話は省エネいうのか、炎天下のデーゲームに自然と振れていく。僕は最初、キックオフから互いにやりあって、しばらくして何となく「こんなペースじゃもたないから、ちょっと落とそうや」的な無言の会話がピッチ上にあった感じが面白かった。これは八百長みたいなことじゃないんだな。手合わせして、感覚で通じ合うような事柄だ。場合によってはわかった上でそれを裏切ったりもする。敵味方に分かれているが、彼らは同じ「通じるもの=身体的言語」を共有する、サッカー人なんだね。
僕もあんなペースじゃ(両軍とも)最後までもたなかったと思うけど、新潟は序盤、もうしばらく「アグレッシブ」を続ける手もあった気がしている。つまり、おつき合いしないで。そうだったらどうなってたかなぁと想像するのだ。
石倉さんは後半、新潟が盛り返した時間帯に注目した。あそこで1点でも返せていれば全然違う試合になったと言う。広島は案外、失点して追い着かれるようなもろさがあるそうだ。広島サポはあの時間帯、ヒヤヒヤしてたんじゃないか。まぁ、試合終盤は新潟もガス欠で、得点入る感じじゃなくなってたし、勝負どころは後半アタマだったかなぁ。
無得点試合に関して思うことを2つ。ひとつは川又堅碁が研究されてるね。マークがきびしくて、なかなか思うようにやらせてもらえない。ま、当然なんだけどね。Jリーグのスカウティングは相当なもんだと思いますよ。で、ケンゴは研究されてるなかで自分の仕事ができないと一流にはなれない。これは乗り越えるべき壁だ。がんばれケンゴ!
あと、攻めにかかったところで「新潟の宿命」的な問題があるかなぁ。柳下正明監督はマンマークで、人についていけって指示出してるね。責任を持って最後までつき切れ。これはもちろん一定以上の効果をもたらしている。おかげで今季は残留争いと無縁でいられそうだ。が、(新潟の選手は素直だから余計に)ついていく結果、いざ攻めにかかったとき、人数が足りなくなったりしている。ここの(選手個人の)判断は難しいね~。相当に高度なところだ。ま、原則は指示通り、マークにつき切れ、なんだけどね。
試合はとにかく完敗でしたね。山越えの車中は試合後の柳下さんのコメント、「悔しいですね。あんなつまらないサッカーに負けたのが悔しい」に移る。石倉さんは「負け惜しみにしか聞こえない。終始攻め続けたのにポストに嫌われるとかしたっていうならまだわかりますけど…」という意見。僕も大前提として戦った相手にリスペクトを持ちたいから、会見コメントを聞いてちょっと驚いた。
が、会見後、中継を担当したJスポーツの土屋雅史さんとバッタリ出くわし、TV用のフラッシュインタビューのウラ話を聞いて、あ、なるほどなと思った。柳下さんはわざわざ確認したそうだ。フラッシュインタビューがスタジアムの大型モニターに映るかどうか。で、順序としてはTV用のフラッシュインタビューでコメントして、しかるが後に監督会見で同じコメントを出した。つまり、僕が言いたいのは確信犯的にわざわざ出したコメントだいうこと。
で、意図は何だろう。わざわざサンフレッチェ広島と遺恨試合のギミックをつくろうみたいな話じゃないのは明白だ。僕はこれは新潟の選手へ向けた発信だと思う。チームの方向性をブレさせない。自信を失わせたくない。まぁ、それでも広島サポは「ヤンツー、俺らをダシにすんな」と気持ちがおさまらないと思うが、真意はそんなところだね。
自分たちでアクションを起こせるサッカー。仕掛けるサッカー。
「奪う力」で注目されてる新潟が目指しているのは、自在型の攻撃サッカーだった。柳下さんはその宣言をしたようなもんじゃないか。で、それは「面白いサッカー」だと言い切ったに等しい。面白いねぇ、その「面白いサッカー」を僕らは見るんだ。
附記1、東口順昭選手の全身オレンジユニが超レアでしたね。あれは惑星直列級の偶然が重ならないと見ることができないらしい。僕は「あ、オレンジも持ってるんだ」と妙な感心の仕方でした(笑)。
2、松江駅前のスタバって今年3月にオープンして、大騒ぎになった店ですよ。島根県初出店ってことでオープン当日はどえらい行列ができていた。地元ニュースのトップ項目扱いだったはずです。さすがに9月にはもう落ち着いてました。
3、松江市には2泊して、毎日、宍道湖畔をウォーキングしたりして、僕的には非常に充実してたんですけど、どうも石倉さんにはショック続きな連休でしたね。まず、この原稿書き上げた後、僕は石倉家へお邪魔して、岐阜×鳥取の「J2裏天王山」をスカパー観戦するんですけど、ガイナーレ鳥取が敗れて最下位転落。翌・秋分の日はヤフーのホットワードに「サカマガ 月刊化」が出た日です。石倉さんも僕もその情報は既に知っていて、今回の松江旅行の主要な議題は「週刊サッカーマガジンが月刊化する、サッカー業界縮小の動きにどう向き合うべきか」だったですね。しかしなぁ、シーズン途中での月刊化ってよくよくのことなんだと思います。
4、だから月刊になる前に新潟特集号(2013年10月1日号、「新アルビ主義/柳下新潟の進化とは何か?」)が出てよかったですね。県内の争奪戦もいい思い出です。サカマガは僕にとってはお世話になった「古巣」ですからね。ホントに寂しいです。ま、休刊するわけじゃないからネガティブに考えないようにはしたいけど。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!