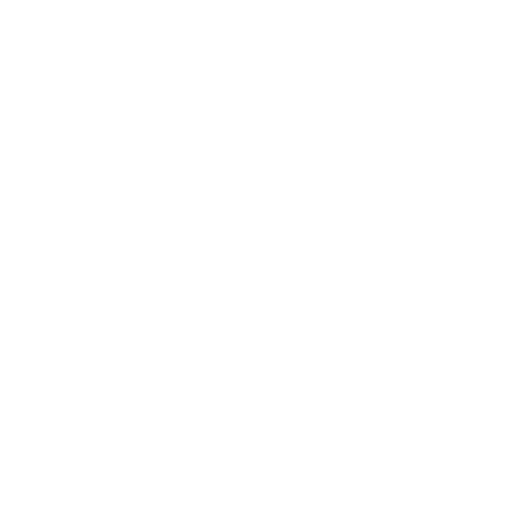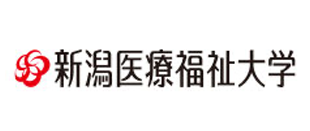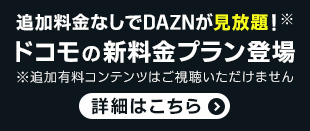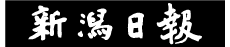【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第196回
2013/11/14
「コートサイズの話」
僕は珍しい人間で、サッカースタジアムよりも圧倒的にアイスアリーナでセルジオ越後さんに会うことが多い。先日もアリーナ正面玄関に並んで「こんにちは。今日はナビスコカップ決勝の日なんですけど、セルジオさんはこっちにいます!(笑)」と観客のお出迎えをしていた。最初に会ったのはスカパーの番組顔合わせで、表参道のブラジル料理店だった。2001年だ。
たぶん読んでる人全員が同じだと思うけど、「明日、セルジオ越後さんと会食」ってめっちゃ緊張でしょう。TVのサッカー討論番組なんかの相手を一方的にやり込めるシーンが浮かぶ。口ゲンカになったらちょっと勝ち目がないなと思う。だけど、当時、僕のすすめていた番組企画は「台本なしの完全フリートーク」で、セルジオさんだろうと誰だろうとテーマによってはきっちりやり合う性質のものだった。
番組にはトータルで何度か出ていただいて、完全に凹まされもしたけど、僕も負けん気が強いから納得いくまでスタジオでは一切引かなかった。(ブラジル料理店での僕なりスカウティングによると)セルジオさんには「せルジオ話法」とでもいうべきものがあって、それが彼をして討論の強者に仕立てている。セルジオさんは相手の質問が何だろうと、自分の言いたいことをいうのだ。TV番組では特にそうだけど、MCはゲストスピーカーの勘違いを正しづらい。質問と答えがかみ合ってなくても、そのコメントが面白ければそっちに乗っかる場合が多い。ましてセルジオさんは(来日して長いのだけど)「言葉が不自由」というエクスキューズが成立するブラジル人だ。質問の意味をとり違えてもしょうがないでしょう。
で、いちばん面白かったゲスト回は、僕がセルジオさんに同じ質問を3回繰り返したのだった。質問と答えがかみ合うまで、話をストップさせた。異常にスタジオ内が緊迫していくのがわかって面白いの何の。まぁ、だけど、僕としては誠実な対応のつもりだ。話がかみ合ってないのに流しちゃうほうが礼を失するでしょう。僕は自分の聞きたいことについてコメントを求めているので、「いつものセルジオ節」が聞きたいわけじゃない。たぶんスタジオトークであれだけガチに挑んだ人間は初めてじゃないかな。
で、そりゃ仲良くなるんだね。スタジオが面白いんだから。で、何かの折に日光アイスバックスの話をした。古河電工アイスホッケー部が廃部になって、市民クラブとして再スタートを切った貧乏チームがあるんです。よかったらいっぺん選手らに話を聞かせてやってください。あいつら、絶対得るところあると思います。たぶんセルジオさんも他の競技の選手らに会うのは新鮮だと思いますよ。
そしたら快諾してくれたんだね。試合を見に来て、日光という歴史的なホッケータウンを面白がってくれる。僕が意外だったのは、セルジオさんがアイスホッケーの現場に「昔の日本サッカー(界)」を見出したことだ。セルジオさんに言わせると、「今のアイスホッケーは、ボクが来日した頃のサッカーにそっくりね」なのだった。企業スポーツの論理が幅をきかせ、プロとして見せるという発想がない。これはJリーグ発足以前、日本リーグ時代の不人気だったサッカーそのものだ。
選手らと会食をセットしたらすっかり気に入ってくれて、そこからサッカー人・セルジオ越後とアイスホッケー選手らの奇妙な交流がスタートする。僕が思い出深いのはフットサルの試合を組んだんだね。セルジオチームvsアイスバックス。ホッケー選手はわりとサッカー好きが多い。北海道出身の選手は高校時代、夏場はサッカー部の試合に出たなんて逸話の持ち主がザラにいる。今も試合前のウォーミングアップでは必ずボールを蹴っている。
でね、僕はホントに感じ入ったんだけど、セルジオさんが真剣に勝とうとするんだ。あれは鬼ですよ。まず、GK探して、元サガン鳥栖って選手を押さえる。それからブラジル人を3人ブッキングした(そのひとりが元日産サッカー部、元フットサル日本代表監督のマリーニョさん!)。他にも高校サッカー選手権のスターだったMFを入れた。ただの親睦を深める試合ですよ。そこまでする必要ない。けど、勝たなきゃおさまらないんだね。こてんぱんにホッケーチームをやっつけるつもりだった。
なかでも勉強になったのはコートサイズを決めるときだね。ルール決めのとき、絶対引かない。セルジオさんがこだわったのは小さいコートだった。そりゃね、現役のアイスホッケー選手は体力あるよ。大きなコートサイズだと動けるほうが有利だ。僕はこれは外国人的な発想だと思ったな。たぶん今、TPP交渉とかでも同じことが起きてるんだろうと思うけど、外国人はルール決め(あるいはルール変更)にものすごく熱を入れるんだ。そこがいちばんクリエイティブだと思ってるフシがある。
要するに勝てるルールで戦おうとするんだね。勝てるルールをつくろうとする。僕らは学校時代から「決まったことは守りましょう」一本槍で来てるでしょ。ルールは守るもので、自分らに合わせて変更するものじゃない。実際は皆で話しあって、変更も可能だというのが民主主義ってもんじゃないかと思うんだけどね。そういう感じにはあんまりならない。例えばマンション自治会なんかでも「入居時に規約を読んで入居してるはずだから、ルールは守ってもらう」って論法を出されると、ちょっと反論する人いないもんなぁ。
決まりは変えてもいい。自分に有利なようにクリエイトしていい。「勝てるルールで戦う」で有名なのは19世紀の大英帝国だよね。この時代、彼らがクリエイトしたスポーツは沢山残ってて、例えばボクシングやフットボール(サッカー、ラグビー)が代表例だ。で、植民地支配したとこの先住民と試合するんだよ。もちろん自分らのルールで。で、負かして屈服させる。先住民が反撃するとやたら反則を取る。「ボクシングは腰から下を打ったら反則だ」みたいに。そんなの先住民は知らないよ。
だもんで「植民地のチームが旧・宗主国のチームに勝つ」(この場合のパターンは似通っていて、「混ぜてもらって」技術的に熟達した先住民が、自分たちのクラブをつくり、それがいつしか強くなる)は、一種の革命のような出来事であり、その一方、競技がワールドスタンダード化するプロセスでもあった。今、例えばブラジルサッカーやラグビーのオールブラックスは欧州勢を翻弄するでしょう。あそこにも「混ぜてもらった先住民vs旧・宗主国の文明人」の図式が残滓(ざんし)としてうかがえる。
決まりは変えてもいい。契約は守られないこともあり得る。「決まったことは守りましょう」で暮らしてきた日本人には違和感があるが、そのためにビジネス上、違約金という制度があるのだ。
あるいはカトリックの婚姻は「死が二人を分かつまで」の神前契約という形をとり、表向きは「離婚」が認められない。そこで抜け道として「婚姻の無効」を申し立てる制度がつくられた。このケースでは、神様の前で契約したことが守られないのではなく、そもそも契約自体が成立してなかった(から守らなくていい)を言い立てる考え方だ。「勝てるルールで戦う」のアナロジーで言うならアレだ、試合に負けることになったからそもそものルールを問題にして、試合そのもの(あるいは大会そのもの)の無効を主張する感覚だ。
もちろんフットサルの試合はセルジオチームの勝利だ。勉強になったなぁ。僕自身は「決められたルールのなかで正々堂々と戦う」を尊しとする日本的な感覚がしっくり来る。けれど、それやってるだけじゃダメなんだ。セルジオさんは交流を通じて親しくなったアイスホッケー選手のために、いつしか仕組みづくりに着手する。今はもう、チーム運営会社の代表取締役だ。
たぶんアルビレックス新潟も「2ステージ制」とか「秋冬制」をはじめとした、様々なルール変更の議論につき合わされるのだと思う。それは一種の政治ではあるけれど、積極的に参加し、発言していく必要がある。まぁ、帝国主義の海洋国家じゃないから「勝てるルールで戦う」だけを押し通せるものじゃない。それに公益性を軽んじて、自らの損得ばかりを見ていくと必ずしっぺ返しを食らう。といってそれが黙っていていい理由になんかならないよ。
実際のセルジオ越後さんは(TVのサッカー討論番組の印象と違って)、実に細やかに気づかいするタイプだ。が、ここというところで黙ってる習慣がなかった。「細やか」と「議論でやり込める」は別に矛盾しないんだな。
附記1、11月最初の週末、アイスバックスの試合(韓国の強豪・アニャンハルラ戦)にボランティア参加して、ま、いつものように場内放送やヒーローインタビューのMCを務めたんですけど、ふとね、これだけふんだんに接してて、散歩道にあんまりセルジオさんのこと書いてないなぁと思ったんですよ。すんごい面白い人ですよ。僕は空いた時間にJリーグのことや、ブラジルのサッカー環境の話を聞いている。今回はそのおすそ分けですね。
2、今週末は大分県臼杵市に前泊することにしました。大友宗麟の城下町ですよ。
3、11月23日の仙台戦は「J1昇格10周年」アニバーサリーということで、田村社長から異例の参戦要請が出ましたね。ホーム連勝中に記念日を迎えるなんてすごいです。是非、4万人のビッグスワンを実現させましょう!
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!

僕は珍しい人間で、サッカースタジアムよりも圧倒的にアイスアリーナでセルジオ越後さんに会うことが多い。先日もアリーナ正面玄関に並んで「こんにちは。今日はナビスコカップ決勝の日なんですけど、セルジオさんはこっちにいます!(笑)」と観客のお出迎えをしていた。最初に会ったのはスカパーの番組顔合わせで、表参道のブラジル料理店だった。2001年だ。
たぶん読んでる人全員が同じだと思うけど、「明日、セルジオ越後さんと会食」ってめっちゃ緊張でしょう。TVのサッカー討論番組なんかの相手を一方的にやり込めるシーンが浮かぶ。口ゲンカになったらちょっと勝ち目がないなと思う。だけど、当時、僕のすすめていた番組企画は「台本なしの完全フリートーク」で、セルジオさんだろうと誰だろうとテーマによってはきっちりやり合う性質のものだった。
番組にはトータルで何度か出ていただいて、完全に凹まされもしたけど、僕も負けん気が強いから納得いくまでスタジオでは一切引かなかった。(ブラジル料理店での僕なりスカウティングによると)セルジオさんには「せルジオ話法」とでもいうべきものがあって、それが彼をして討論の強者に仕立てている。セルジオさんは相手の質問が何だろうと、自分の言いたいことをいうのだ。TV番組では特にそうだけど、MCはゲストスピーカーの勘違いを正しづらい。質問と答えがかみ合ってなくても、そのコメントが面白ければそっちに乗っかる場合が多い。ましてセルジオさんは(来日して長いのだけど)「言葉が不自由」というエクスキューズが成立するブラジル人だ。質問の意味をとり違えてもしょうがないでしょう。
で、いちばん面白かったゲスト回は、僕がセルジオさんに同じ質問を3回繰り返したのだった。質問と答えがかみ合うまで、話をストップさせた。異常にスタジオ内が緊迫していくのがわかって面白いの何の。まぁ、だけど、僕としては誠実な対応のつもりだ。話がかみ合ってないのに流しちゃうほうが礼を失するでしょう。僕は自分の聞きたいことについてコメントを求めているので、「いつものセルジオ節」が聞きたいわけじゃない。たぶんスタジオトークであれだけガチに挑んだ人間は初めてじゃないかな。
で、そりゃ仲良くなるんだね。スタジオが面白いんだから。で、何かの折に日光アイスバックスの話をした。古河電工アイスホッケー部が廃部になって、市民クラブとして再スタートを切った貧乏チームがあるんです。よかったらいっぺん選手らに話を聞かせてやってください。あいつら、絶対得るところあると思います。たぶんセルジオさんも他の競技の選手らに会うのは新鮮だと思いますよ。
そしたら快諾してくれたんだね。試合を見に来て、日光という歴史的なホッケータウンを面白がってくれる。僕が意外だったのは、セルジオさんがアイスホッケーの現場に「昔の日本サッカー(界)」を見出したことだ。セルジオさんに言わせると、「今のアイスホッケーは、ボクが来日した頃のサッカーにそっくりね」なのだった。企業スポーツの論理が幅をきかせ、プロとして見せるという発想がない。これはJリーグ発足以前、日本リーグ時代の不人気だったサッカーそのものだ。
選手らと会食をセットしたらすっかり気に入ってくれて、そこからサッカー人・セルジオ越後とアイスホッケー選手らの奇妙な交流がスタートする。僕が思い出深いのはフットサルの試合を組んだんだね。セルジオチームvsアイスバックス。ホッケー選手はわりとサッカー好きが多い。北海道出身の選手は高校時代、夏場はサッカー部の試合に出たなんて逸話の持ち主がザラにいる。今も試合前のウォーミングアップでは必ずボールを蹴っている。
でね、僕はホントに感じ入ったんだけど、セルジオさんが真剣に勝とうとするんだ。あれは鬼ですよ。まず、GK探して、元サガン鳥栖って選手を押さえる。それからブラジル人を3人ブッキングした(そのひとりが元日産サッカー部、元フットサル日本代表監督のマリーニョさん!)。他にも高校サッカー選手権のスターだったMFを入れた。ただの親睦を深める試合ですよ。そこまでする必要ない。けど、勝たなきゃおさまらないんだね。こてんぱんにホッケーチームをやっつけるつもりだった。
なかでも勉強になったのはコートサイズを決めるときだね。ルール決めのとき、絶対引かない。セルジオさんがこだわったのは小さいコートだった。そりゃね、現役のアイスホッケー選手は体力あるよ。大きなコートサイズだと動けるほうが有利だ。僕はこれは外国人的な発想だと思ったな。たぶん今、TPP交渉とかでも同じことが起きてるんだろうと思うけど、外国人はルール決め(あるいはルール変更)にものすごく熱を入れるんだ。そこがいちばんクリエイティブだと思ってるフシがある。
要するに勝てるルールで戦おうとするんだね。勝てるルールをつくろうとする。僕らは学校時代から「決まったことは守りましょう」一本槍で来てるでしょ。ルールは守るもので、自分らに合わせて変更するものじゃない。実際は皆で話しあって、変更も可能だというのが民主主義ってもんじゃないかと思うんだけどね。そういう感じにはあんまりならない。例えばマンション自治会なんかでも「入居時に規約を読んで入居してるはずだから、ルールは守ってもらう」って論法を出されると、ちょっと反論する人いないもんなぁ。
決まりは変えてもいい。自分に有利なようにクリエイトしていい。「勝てるルールで戦う」で有名なのは19世紀の大英帝国だよね。この時代、彼らがクリエイトしたスポーツは沢山残ってて、例えばボクシングやフットボール(サッカー、ラグビー)が代表例だ。で、植民地支配したとこの先住民と試合するんだよ。もちろん自分らのルールで。で、負かして屈服させる。先住民が反撃するとやたら反則を取る。「ボクシングは腰から下を打ったら反則だ」みたいに。そんなの先住民は知らないよ。
だもんで「植民地のチームが旧・宗主国のチームに勝つ」(この場合のパターンは似通っていて、「混ぜてもらって」技術的に熟達した先住民が、自分たちのクラブをつくり、それがいつしか強くなる)は、一種の革命のような出来事であり、その一方、競技がワールドスタンダード化するプロセスでもあった。今、例えばブラジルサッカーやラグビーのオールブラックスは欧州勢を翻弄するでしょう。あそこにも「混ぜてもらった先住民vs旧・宗主国の文明人」の図式が残滓(ざんし)としてうかがえる。
決まりは変えてもいい。契約は守られないこともあり得る。「決まったことは守りましょう」で暮らしてきた日本人には違和感があるが、そのためにビジネス上、違約金という制度があるのだ。
あるいはカトリックの婚姻は「死が二人を分かつまで」の神前契約という形をとり、表向きは「離婚」が認められない。そこで抜け道として「婚姻の無効」を申し立てる制度がつくられた。このケースでは、神様の前で契約したことが守られないのではなく、そもそも契約自体が成立してなかった(から守らなくていい)を言い立てる考え方だ。「勝てるルールで戦う」のアナロジーで言うならアレだ、試合に負けることになったからそもそものルールを問題にして、試合そのもの(あるいは大会そのもの)の無効を主張する感覚だ。
もちろんフットサルの試合はセルジオチームの勝利だ。勉強になったなぁ。僕自身は「決められたルールのなかで正々堂々と戦う」を尊しとする日本的な感覚がしっくり来る。けれど、それやってるだけじゃダメなんだ。セルジオさんは交流を通じて親しくなったアイスホッケー選手のために、いつしか仕組みづくりに着手する。今はもう、チーム運営会社の代表取締役だ。
たぶんアルビレックス新潟も「2ステージ制」とか「秋冬制」をはじめとした、様々なルール変更の議論につき合わされるのだと思う。それは一種の政治ではあるけれど、積極的に参加し、発言していく必要がある。まぁ、帝国主義の海洋国家じゃないから「勝てるルールで戦う」だけを押し通せるものじゃない。それに公益性を軽んじて、自らの損得ばかりを見ていくと必ずしっぺ返しを食らう。といってそれが黙っていていい理由になんかならないよ。
実際のセルジオ越後さんは(TVのサッカー討論番組の印象と違って)、実に細やかに気づかいするタイプだ。が、ここというところで黙ってる習慣がなかった。「細やか」と「議論でやり込める」は別に矛盾しないんだな。
附記1、11月最初の週末、アイスバックスの試合(韓国の強豪・アニャンハルラ戦)にボランティア参加して、ま、いつものように場内放送やヒーローインタビューのMCを務めたんですけど、ふとね、これだけふんだんに接してて、散歩道にあんまりセルジオさんのこと書いてないなぁと思ったんですよ。すんごい面白い人ですよ。僕は空いた時間にJリーグのことや、ブラジルのサッカー環境の話を聞いている。今回はそのおすそ分けですね。
2、今週末は大分県臼杵市に前泊することにしました。大友宗麟の城下町ですよ。
3、11月23日の仙台戦は「J1昇格10周年」アニバーサリーということで、田村社長から異例の参戦要請が出ましたね。ホーム連勝中に記念日を迎えるなんてすごいです。是非、4万人のビッグスワンを実現させましょう!
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動が覚める前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!