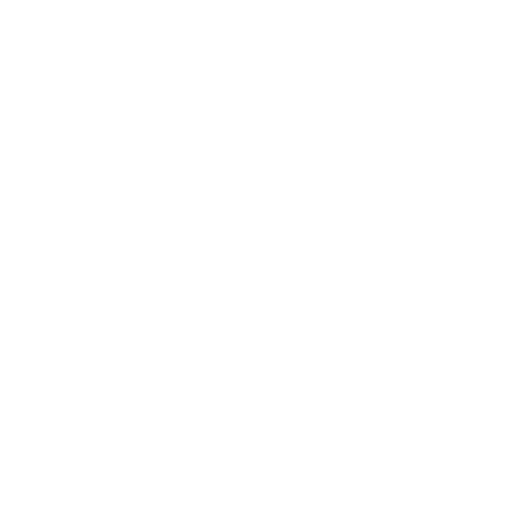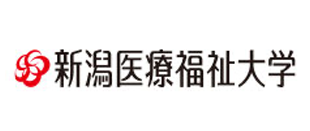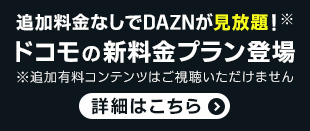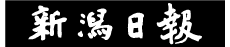【コラム】えのきどいちろうのアルビレックス散歩道 第288回
2016/4/28
「宣福の右足クロス」
J1第7節(第1ステージ)、広島×新潟。
この試合はサンフレッチェ広島のACL日程を考慮して、金曜夜の開催になった。僕は夕方まで普段通り仕事して、19時半のキックオフぎりぎりに新宿のサッカーバー・フィオーリに飛び込む。既に20人くらい客がいた。ほぼ全員が新潟サポ。そのなかに何食わぬ顔で元サッカーマガジン編集長、平澤大輔さんがいる。平澤さんは春の異動で東京へ戻ったんだけど、すっかり新潟びいきになっている。この日は会社の引っ越し作業(ベースボールマガジン社は水道橋から浜町に移転した)を終えて、フィオーリに駆けつけてくれた。
スタメンの注目は何といってもGK・川浪吾郎だ。吉田達磨監督は初めてリーグ戦で守田達弥を外した。いったん休ませて気持ちの整理をつけさせる狙いもあるだろう。が、それ以上に競争原理だ。川浪にとっては大チャンス到来である。ここで好パフォーマンスを発揮して、第1ゴーリーの座を奪いたい。もちろん守田は明け渡すつもりなんかない。フェアに火花を散らしてほしい。それがチーム力をアップさせる。
スタメンもうひとつの注目点はキャプテン小林裕紀の累積欠場だ。アンカーに小泉慶が入り、レオ、加藤大と「中盤の三角形」を形成する。慶は「慣れないSBで起用されていたが、本職に戻った」とも言えるし、「2ボランチの一角ではなく、慣れないアンカーに起用された」とも言える。それから右SBには酒井宣福が入った。「慣れない」の話をすれば、これだって「慣れない慶に代わって、慣れない宣福が務めた」的な言い方が可能だ。だけどね、プロだからね。「慣れない」って言ってたらチャンスは永遠に来ない。「慣れない吾郎」上等! 「慣れない慶」「慣れない宣福」上等! 可能性の扉をひらくんだ。「慣れないサイドハーフ」「慣れない短髪」(?)で見事再生した田中達也のプロ根性を見習え。
試合が始まって平澤さんが「ギュンギュンがトップですね」と言う。「前線の三角形」は山崎亮平がトップで、左に田中達也、右にラファエル・シルバ。あ、ちなみにこの表現は「4-1-4-1」を「4-3-3」で解釈している。単に数え方の問題だからあんまり気にしないでほしい。ひとつね、平澤さんと話になったのは「この布陣ならトップはラファじゃないだろうか?」だ。(指宿洋史が使える状態ならまた話が変わってくるだろうが)このスタメンで山崎がトップというのは、ハッキリ達磨さんに意図があるのだ。それが面白いとこだなぁと思う。
僕はラファは前線に置いたほうが怖さがあると思うのだ。劣勢の局面でもウラへ抜けさせれば一発がある。だけど、アレかな、「レオ(あるいはコルテース)が持ち上がって出したところに後から入ってくる」みたいなパターンが狙いなのかな。一度、達磨さんにうかがってみたい。「ラファのベストポジションはどこだ?」問題ひとつで新宿フィオーリは何時間でも盛り上がれそうだ。
「ラファの最大の特長は、スピードとシュートです。選手の特長をうまく組み合わせることを『チーム作り』と呼ぶのなら、ラファのポジションはサイドではないでしょうね。ゴールに近い位置でフラフラしていればいい。相手は嫌でしょう。捕まえにくいし、突然のダッシュで置き去りにされますから」(平澤メモより)
この平澤メモ抜粋の勘どころはどこかというと「選手の特長をうまく組み合わせることを『チーム作り』と呼ぶのなら」じゃないだろうか。もちろんそれが絶対じゃなくて、別の「チーム作り」の考え方だってあり得る。「ラファありき」で発想してしまう弊害も指揮官は考慮する。難しいとこなのだ。面白いとこなのだ。
試合はざっくり言うと「ザ・サンフレッチェ」だった。テンポの遅い守備ベースの試合運びに新潟はつき合った格好だ。これは「相手の土俵で相撲を取った」わけで、決して上策とは言えない。完成期の広島に「ザ・サンフレッチェ」で試合して勝てる道理がない。だが、それなら新潟は広島をかきまわして別のサッカーをさせる地力があるんか、という問題である。この何年、全てのチームが戦術的に挑み、結局は「ザ・サンフレッチェ」にされているのだ。
しかしね、「相手の土俵で相撲を取った」わりには新潟がなかなかよかった。少なくとも2回、決定機を作り、鉄壁の広島DF陣をあわてさせた。具体的には前半13分、酒井宣福から田中達也に渡り、それを達也が芸術的なジャンピングヒールで落とし、ボールがレオに出たシーン。これがフィオーリ店内を大騒ぎさせた。が、残念なことにレオが外してしまう(ちなみに「少なくとも2回」のもう1回は後半開始早々のラファのドリブル突破です)。
「今、宣福、右足でしたね」
レオのシュートが外れてのけぞってるとき、平澤さんが言った。確かに宣福は右足でクロスを入れた。実はこの件に関して平澤さんは前々から指摘していたのだ。「酒井宣福はいつも右足で内側に切り返して、左足でクロスを蹴ってる」。タイミングが1個遅れて全体がノッキングを起こす。それがこの日、初めて右足で入れた。いや、初めてかどうか知らないが、見たのは初めてだ。
「フツーに言えば凄かったのは断然、達也のジャンピングヒールですけど、僕的には宣福が右足で蹴ったのが事件ですね。いつ乗り越えるのかなと思っていたんです。これは考えて練習して、課題を克服したんですよ。それが決定機に直結したんです」
平澤さんは嬉しそうだ。逆に言えば、だからこそゴールを決めて、宣福にもチームにも(課題を克服する)成功体験としたかった。
ディフェンディング王者・広島は苦しんだと思う。前半は終了間際まで見せ場なし。瀬戸内海くらいのベタ凪(なぎ)だなぁと見てたら、後半11分、ミキッチのクロスがポストに当たって跳ね返り、かつそれがGK川浪の身体に当たってゴールインしてしまう。いやぁ、これは広島の勝負強さをたたえるべきか新潟の不運を嘆くべきか。川浪は悔しかったろうなぁ。このシーン以外はグレートジョブだった。
「組織の構築は、守備の際によく表れます。奪われた場所や状況によって、それぞれの選手がどこに戻るべきか、といった決まり事です。でも攻撃は、もちろん組織で崩すけれど、最終的には個人戦術の領域が広い。むしろ、個人戦術を擦り合わせていくことが、攻撃の組織を作ることとも言えます」
「前向きに捉えれば、この試合であぶり出されたのは、こういうことだったかもしれません。”チーム作りも守備の約束事はまずまず実行できるようになってきて、さあその次へ、という段階までようやくたどり着いた”」(同上)
「相手の土俵」で戦った評価の難しい試合(0-1で完敗)に、平澤さんが目安をくれた。なるほど、新潟は次のフェーズに踏み込むわけか。確かになぁ、とりあえずここまでのところはいったん終了って感触がある。行き着いたというのか煮詰まったというのか。
この先へ進むにはブレイクスルーが要るだろう。それは例えば宣福の右足クロスのようなことだ。無数の「宣福の右足クロス」的なものが芽をふけばいい。その集積がある日、劇的にチームを変えるんじゃないかな。
附記1、この日、出場しなかった小林裕紀と守田達弥は、心中穏やかじゃなかった気がしますね。自分がいなくてチームが成立するくらい悔しいことはありません。次、出てきたときの姿を見たいですね。っていう意味じゃ端山豪とか、出れないワカゾーももっとぐつぐつ煮えてていいなぁ。
2、この日はフィオーリからゴールデン街の「きしめん双葉」へ流れました。「きしめん双葉」店内の、奇跡の新潟感には腰を抜かしました。都会のオアシスじゃないですか。そのオアシスが危うく火事になりそうになって、しばらく停電してたとはなぁ。
3、「平成28年熊本地震」には衝撃を受けました。亡くなられた方へお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。広島戦でさっそくサポーターが激励のダンマクを出してくれましたね。クラブも義援金募金の実施を決めています。(去年までロアッソ熊本に在籍していた)北嶋秀朗コーチもブログで支援の動きを公表しています。被災地を助けましょう。やれることをやれる範囲で(しかし、息長く)やっていきましょう。とりあえず僕は近所のローソンでロッピー募金してみました。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。 新潟日報で隔週火曜日に連載されている「新潟レッツゴー!」も好評を博している。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動がさめる前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!

J1第7節(第1ステージ)、広島×新潟。
この試合はサンフレッチェ広島のACL日程を考慮して、金曜夜の開催になった。僕は夕方まで普段通り仕事して、19時半のキックオフぎりぎりに新宿のサッカーバー・フィオーリに飛び込む。既に20人くらい客がいた。ほぼ全員が新潟サポ。そのなかに何食わぬ顔で元サッカーマガジン編集長、平澤大輔さんがいる。平澤さんは春の異動で東京へ戻ったんだけど、すっかり新潟びいきになっている。この日は会社の引っ越し作業(ベースボールマガジン社は水道橋から浜町に移転した)を終えて、フィオーリに駆けつけてくれた。
スタメンの注目は何といってもGK・川浪吾郎だ。吉田達磨監督は初めてリーグ戦で守田達弥を外した。いったん休ませて気持ちの整理をつけさせる狙いもあるだろう。が、それ以上に競争原理だ。川浪にとっては大チャンス到来である。ここで好パフォーマンスを発揮して、第1ゴーリーの座を奪いたい。もちろん守田は明け渡すつもりなんかない。フェアに火花を散らしてほしい。それがチーム力をアップさせる。
スタメンもうひとつの注目点はキャプテン小林裕紀の累積欠場だ。アンカーに小泉慶が入り、レオ、加藤大と「中盤の三角形」を形成する。慶は「慣れないSBで起用されていたが、本職に戻った」とも言えるし、「2ボランチの一角ではなく、慣れないアンカーに起用された」とも言える。それから右SBには酒井宣福が入った。「慣れない」の話をすれば、これだって「慣れない慶に代わって、慣れない宣福が務めた」的な言い方が可能だ。だけどね、プロだからね。「慣れない」って言ってたらチャンスは永遠に来ない。「慣れない吾郎」上等! 「慣れない慶」「慣れない宣福」上等! 可能性の扉をひらくんだ。「慣れないサイドハーフ」「慣れない短髪」(?)で見事再生した田中達也のプロ根性を見習え。
試合が始まって平澤さんが「ギュンギュンがトップですね」と言う。「前線の三角形」は山崎亮平がトップで、左に田中達也、右にラファエル・シルバ。あ、ちなみにこの表現は「4-1-4-1」を「4-3-3」で解釈している。単に数え方の問題だからあんまり気にしないでほしい。ひとつね、平澤さんと話になったのは「この布陣ならトップはラファじゃないだろうか?」だ。(指宿洋史が使える状態ならまた話が変わってくるだろうが)このスタメンで山崎がトップというのは、ハッキリ達磨さんに意図があるのだ。それが面白いとこだなぁと思う。
僕はラファは前線に置いたほうが怖さがあると思うのだ。劣勢の局面でもウラへ抜けさせれば一発がある。だけど、アレかな、「レオ(あるいはコルテース)が持ち上がって出したところに後から入ってくる」みたいなパターンが狙いなのかな。一度、達磨さんにうかがってみたい。「ラファのベストポジションはどこだ?」問題ひとつで新宿フィオーリは何時間でも盛り上がれそうだ。
「ラファの最大の特長は、スピードとシュートです。選手の特長をうまく組み合わせることを『チーム作り』と呼ぶのなら、ラファのポジションはサイドではないでしょうね。ゴールに近い位置でフラフラしていればいい。相手は嫌でしょう。捕まえにくいし、突然のダッシュで置き去りにされますから」(平澤メモより)
この平澤メモ抜粋の勘どころはどこかというと「選手の特長をうまく組み合わせることを『チーム作り』と呼ぶのなら」じゃないだろうか。もちろんそれが絶対じゃなくて、別の「チーム作り」の考え方だってあり得る。「ラファありき」で発想してしまう弊害も指揮官は考慮する。難しいとこなのだ。面白いとこなのだ。
試合はざっくり言うと「ザ・サンフレッチェ」だった。テンポの遅い守備ベースの試合運びに新潟はつき合った格好だ。これは「相手の土俵で相撲を取った」わけで、決して上策とは言えない。完成期の広島に「ザ・サンフレッチェ」で試合して勝てる道理がない。だが、それなら新潟は広島をかきまわして別のサッカーをさせる地力があるんか、という問題である。この何年、全てのチームが戦術的に挑み、結局は「ザ・サンフレッチェ」にされているのだ。
しかしね、「相手の土俵で相撲を取った」わりには新潟がなかなかよかった。少なくとも2回、決定機を作り、鉄壁の広島DF陣をあわてさせた。具体的には前半13分、酒井宣福から田中達也に渡り、それを達也が芸術的なジャンピングヒールで落とし、ボールがレオに出たシーン。これがフィオーリ店内を大騒ぎさせた。が、残念なことにレオが外してしまう(ちなみに「少なくとも2回」のもう1回は後半開始早々のラファのドリブル突破です)。
「今、宣福、右足でしたね」
レオのシュートが外れてのけぞってるとき、平澤さんが言った。確かに宣福は右足でクロスを入れた。実はこの件に関して平澤さんは前々から指摘していたのだ。「酒井宣福はいつも右足で内側に切り返して、左足でクロスを蹴ってる」。タイミングが1個遅れて全体がノッキングを起こす。それがこの日、初めて右足で入れた。いや、初めてかどうか知らないが、見たのは初めてだ。
「フツーに言えば凄かったのは断然、達也のジャンピングヒールですけど、僕的には宣福が右足で蹴ったのが事件ですね。いつ乗り越えるのかなと思っていたんです。これは考えて練習して、課題を克服したんですよ。それが決定機に直結したんです」
平澤さんは嬉しそうだ。逆に言えば、だからこそゴールを決めて、宣福にもチームにも(課題を克服する)成功体験としたかった。
ディフェンディング王者・広島は苦しんだと思う。前半は終了間際まで見せ場なし。瀬戸内海くらいのベタ凪(なぎ)だなぁと見てたら、後半11分、ミキッチのクロスがポストに当たって跳ね返り、かつそれがGK川浪の身体に当たってゴールインしてしまう。いやぁ、これは広島の勝負強さをたたえるべきか新潟の不運を嘆くべきか。川浪は悔しかったろうなぁ。このシーン以外はグレートジョブだった。
「組織の構築は、守備の際によく表れます。奪われた場所や状況によって、それぞれの選手がどこに戻るべきか、といった決まり事です。でも攻撃は、もちろん組織で崩すけれど、最終的には個人戦術の領域が広い。むしろ、個人戦術を擦り合わせていくことが、攻撃の組織を作ることとも言えます」
「前向きに捉えれば、この試合であぶり出されたのは、こういうことだったかもしれません。”チーム作りも守備の約束事はまずまず実行できるようになってきて、さあその次へ、という段階までようやくたどり着いた”」(同上)
「相手の土俵」で戦った評価の難しい試合(0-1で完敗)に、平澤さんが目安をくれた。なるほど、新潟は次のフェーズに踏み込むわけか。確かになぁ、とりあえずここまでのところはいったん終了って感触がある。行き着いたというのか煮詰まったというのか。
この先へ進むにはブレイクスルーが要るだろう。それは例えば宣福の右足クロスのようなことだ。無数の「宣福の右足クロス」的なものが芽をふけばいい。その集積がある日、劇的にチームを変えるんじゃないかな。
附記1、この日、出場しなかった小林裕紀と守田達弥は、心中穏やかじゃなかった気がしますね。自分がいなくてチームが成立するくらい悔しいことはありません。次、出てきたときの姿を見たいですね。っていう意味じゃ端山豪とか、出れないワカゾーももっとぐつぐつ煮えてていいなぁ。
2、この日はフィオーリからゴールデン街の「きしめん双葉」へ流れました。「きしめん双葉」店内の、奇跡の新潟感には腰を抜かしました。都会のオアシスじゃないですか。そのオアシスが危うく火事になりそうになって、しばらく停電してたとはなぁ。
3、「平成28年熊本地震」には衝撃を受けました。亡くなられた方へお悔やみを申し上げますとともに、被災された方々にお見舞い申し上げます。広島戦でさっそくサポーターが激励のダンマクを出してくれましたね。クラブも義援金募金の実施を決めています。(去年までロアッソ熊本に在籍していた)北嶋秀朗コーチもブログで支援の動きを公表しています。被災地を助けましょう。やれることをやれる範囲で(しかし、息長く)やっていきましょう。とりあえず僕は近所のローソンでロッピー募金してみました。
えのきどいちろう
1959/8/13生 秋田県出身。中央大学経済学部卒。コラムニスト。
大学時代に仲間と創刊した『中大パンチ』をきっかけに商業誌デビュー。以来、語りかけられるように書き出されるその文体で莫大な数の原稿を執筆し続ける。2002年日韓ワールドカップの開催前から開催期までスカイパーフェクTV!で連日放送された「ワールドカップジャーナル」のキャスターを務め、台本なしの生放送でサッカーを語り続け、その姿を日本中のサッカーファンが見守った。
アルビレックス新潟サポータースソングCD(2004年版)に掲載されたコラム「沼垂白山」や、msnでの当時の反町監督インタビューコラムなど、まさにサポーターと一緒の立ち位置で、見て、感じて、書いた文章はサポーターに多くの共感を得た。
著書に「サッカー茶柱観測所」(週刊サッカーマガジン連載)。 新潟日報で隔週火曜日に連載されている「新潟レッツゴー!」も好評を博している。
HC日光アイスバックスチームディレクターでもある。
アルビレックス新潟からのお知らせコラム「えのきどいちろうのアルビレックス散歩道」は、アルビレックス新潟公式サイト『モバイルアルビレックス』で、先行展開をさせていただいております。更新は公式携帯サイトで毎週木曜日に掲載した内容を、翌週木曜日に公式PCサイトで掲載するスケジュールとなります。えのきどさんがサポーターと同じ目線で見て、感じた等身大のコラムは、試合の感動がさめる前に、ぜひ公式携帯サイトでご覧ください!